政治不信下の総選挙
新政権と自民・立憲民主党の課題
政治学者・飯尾潤氏に聞く

第2回 政党はどう変わっていくべきか
政治不信が強まっている中で行われている総選挙は10月27日の投開票に向け終盤を迎えています。各党の主張や候補者に触れる機会も増えており、日本政治を担う政党の本来あるべき姿について考えてみます。与野党の現状はどうか、そして政治をよくするために政党はどう変わったらいいのか。政治学者の飯尾潤氏(政策研究大学院大学教授)に語ってもらいました。
◇組織として人事や政策を決める仕組みを
今回の総選挙における各党の政策を見ても、なかなか日本の将来がイメージできないところに問題があります。その前の、自民党と立憲民主党の党首選でも、日頃からじっくり考えていない人が、急に準備した政策の部品を並べている印象でした。そもそも、選挙の時だけが政策論争の機会だと思っていることが間違いなのです。本来、日頃から政党内あるいは政党間で、いろいろ議論の機会があるべきなのです。党首選が終わったら、あとは党首の思い通り、国政選挙が終わったら、あとは与党内あるいは政府内で好きなように政策を決めるというあり方が日本の政治を貧しくしています。
日本の政党の問題は、自分たちで内部の意思形成ができないことです。党首を決めてしまったら人事も何も「党首一任」にしてしまいますが、組織として、人事や政策を決めていく道筋がきちんと付けられていないことの反映です。政策問題になれば、自民党などは、官僚の力を借りて議員間の調整をすることで、ようやく意思決定できるという状況です。
◇「決め方への不満」が大きかった岸田政権
岸田文雄政権の問題点はそれが大きく影響していたのです。安倍晋三政権の官邸主導というモデルに従っていることは確かですが、首相が決めると言っても、安倍首相はチームワークで根回しして、首相の決断を演出していました。ところが岸田首相は代わりに調整してくれる人があまりいないので、首相1人が走り回って調整する姿が見えていました。外から見ていて、議論の道筋が見えないなかで、どんどん政策が決まったという印象です。有権者の岸田政権への不満は、政策自体への不満よりも、決め方への不満の方が大きかったと思います。
納得感のある政策決定をするためには、それなりの舞台が必要です。政府内での検討や、国会における政策論争ももちろんですが、前提として政党が大方針をきちんと決めて、そのうえで政策論争や具体的な検討に入るということが不可欠です。そこで、政党が政策を決めるための仕組みを備えなければなりません。その意味で、政治がある程度制度化されなければならないのですが、制度化と言えば有権者を含む形での政党のあり方がポイントになります。
どこの国が良いかと聞かれることもありますが、現状では、ヨーロッパの政党が今大きく崩れていて、アメリカはガタガタなので、新しい政党モデルが必要です。これまで個人政治モデルが幅を効かしてきた日本で、新たな政党モデルができるかどうか、日本の将来を決めるだけではなく、世界の民主政治においても重要な意味を持つと考えています。

国家と有権者を繋ぐのが政党の仕事だ。写真は衆院第一議員会館
◇野党も組織を強化し勢力拡大を目指す必要
自民党が、政策について官僚頼みで、なかなか納得感のある政策を展開できないということになると、それに対抗しようとする野党を中心に、新しい動きが出てくるべきでしょう。たとえ小さな政党であっても、政治スタイルを新しくすることで、着実に勢力を拡大するという道筋を描くべきなのです。
その点で、野党第一党の立憲民主党は、政権担当能力がないと見られているところに弱点があります。政権交代を目指すなら、少なくとも2021年の前回総選挙からは政権担当能力を作るために、まさに政党の組織性を強化しないといけなかったはずです。自民党は利権があるから損得勘定で組織性の不足を補えるけれども、野党は自分で組織強化の方策を考えないといけない。
これについて、民主党の失敗は内部でグチャグチャ言う人がいたからだという説明をする人がいますが、それは間違いです。文句を言う人まで納得できるようなモノの決め方がなかったから、と思わなければいけないのです。国民が多様なのですから党の中が一様だったら多数の支持は取れません。国民の多様な意見を説得するためには、多様な意見を一つにまとめる工夫が要るのです。
日本維新の会は、大阪で府政や市政を担うことで、行政運営能力のある政党だという評価もされて勢力を伸ばしましたが、今回は、そうした評価が剥げかかって苦労しています。やはり政党としてのガバナンスを高める必要があるでしょうか。
そのほかの諸政党についても、工夫次第で伸びる余地はあるはずで、何らかの新しい組織化の方策を模索していくべきでしょう。
◇政党の主人は政治家ではなく有権者
政党の組織化を論じる際に、まず確認しておく必要があるのは、政党は有権者のものだということです。今の日本では、政治家が政党の主人になっているところに問題があります。有権者中心の政党の仕組みを考えるべきなのです。小選挙区が悪いと言っている政治家は、政治家の自由が足らないというのですが、全く逆でしょう。中選挙区制に戻したいというのは、個人プレーをもっと強めるべきだという主張で、これは政治家のワガママをもっと強めようという主張です。
世界をみると、小選挙区制と比例代表制が代表的な選挙制度です。小選挙区でなければ、比例代表制だけにするのも一つのアイデアです。ただ、政党が比例代表で拘束名簿(政党が当選順位を決める名簿)も作れない現状を考えると、一挙に比例代表制にもできません。
現行の衆議院の小選挙区比例代表並立制の改善を考えるなら、まず惜敗率によって当選する仕組みを止めたらいいのです。小選挙区と比例代表との重複立候補はあってもいい。この人を絶対当選させるという政治家を上の順位にし、政党の評価をもとに比例名簿を作るべきです。女性議員を増やすために、比例名簿の奇数なり偶数なりの順番は女性にして、半分は女性が当選できるようにすることもできます。組織性がないとそういう名簿も作れないので、そのためにも政党の組織性の強化が必要です。
◇政党を通じての政治参加が必要
組織性が必要な理由のひとつは有権者とのやり取りを組織的にするためです。いまのところ、政党における一般有権者の政策への参加の機会がほとんどありません。50年ぐらい前に発明された有権者との対話集会や車座集会。30年前に生み出された駅前挨拶。あとはそれ以前からある有力者との懇談。この3つだけで政治をしているのはおかしいです。 IT 化が進んでいるのですから、もう少し工夫できるはずです。IT活用と言っても、一方的に X (旧ツイッター)で垂れ流しているだけでは不十分です。
有権者の政治参加ということで言えば、政党を通じての参加を、真剣に考える必要があります。普通の有権者がきちんと政党の意思決定に参加していく。そうすれば、政党の意見が違っているとしても、みんなが参加しているから、そう極端なことは言わないというのがあるべき姿なのです。
選択しても差し支えない範囲で政党が争っているのが良くて、ある政党が政権を取ったらとんでもないことになってしまうのではいけません。与野党で、外交、安全保障、社会保障、 国民生活などについて、ある程度共通の基盤があった方がいいのです。具体的な争点で違ってくればいい。左右の軸がなくなっている以上、対立軸を作るのは簡単ではないのですが、作っていかなければいけません。
有権者が政党に参加する道がもっともっと開かれないといけないのです。すぐには進んでいきません。そこで、政治参加を練習するには、地方レベルがいいと思います。とりわけ市町村の政治課題は具体的なので参加しやすいのです。国は制度の話になってくるので、少し難しくなります。日頃から市町村で参加している人が増えることで政策リテラシーが広がり、そして政党がその受け皿として参加の経路を使えば、大変良いということです。
政党への参加をあまり考えてなかったのは、政党を政治家の都合で勝手に集まっているものだと皆が思っていたからです。一般の有権者が中心になって政党を作るという本来の姿に戻らないといけません。政党は有権者の一部なのです。だから国家と有権者を繋ぐのが政党の仕事なのに、政党が国家側になって、国会議員だけでやっている。しかし、それでは不十分です。
◇政策リテラシーが不足している政治家、官僚
一般の有権者に、政策リテラシー(政策についての知識や政策効果についての判断能力)が不足していると言われますが、それだけではありません。政治家についても大きく不足していて、政策問題は官僚に聞けば分かるとばかり、政策を簡単に考えてしまう政治家が多い。ところが最近は官僚の政策能力も怪しくなっています。政治主導になって、政策リテラシーのない政治家の注文に応えているうちに、官僚の方の感覚も鈍っているからです。
たとえば、グリーンイノベーションを言う人がガソリン代の補助をいつまでも続けることもそうです。「ガソリン価格が急に上がったので、こういう計画で激変緩和しますが、高い価格にいずれなるのはやむを得ない」ということの説明がなく、いつ止めるかもわからない。ところがメディアも野党も、みんな批判しない。政策にはプラスとマイナスの両面があり、誰もが満足するとか、絶対的に正しいという政策はそうはないのです。そこで、政策の限界を理解しながら、政策を論じることが必要です。
また、選挙になると、すぐに何々対策といった話が出てきますが、これも要注意です。もちろん、急に生じた現象に、対策をとるのも大切です。しかし、個別の対策が、どういう考え方で、何を解決するために、何を犠牲にするのか、あるいはどんなコストがかかるのかという話がセットであるべきです。政策においては、そうした基本的な考え方を整理して示すということがないと、バランスがとれた政治はできません。
そして、打ち出せば実現するほど政策は簡単ではなく、政策を実施するには、それなりの準備もいりますし、それなりの時間とコストがかかることも理解しておく必要があります。政策をめぐる基本条件について、だいたいの了解があるというのが、政策リテラシーがあるということの意味だと考えます。
◇政策リテラシーと政党の役割
もちろん、政治家の議論が貧困だと、それを聞いている国民にも政策リテラシーがつきません。今は政党や政治家も、有権者のうち政党内部に取り込もうとするのは、選挙のときに手足になる人とか、選挙のときに義理ができる人たちだけです。しかし、政策について議論する機会を作って、人々を誘い込むということが是非とも必要です。
政策について疑問を持ったら、政党のチャットに質問を入れると答えてくれる、それを巡って政治家を交えて、普通の人が議論できるというのがあるべき姿です。ところが、現状では、有権者の政策リテラシーを上げ、理解してもらって支持を受けるという双方向のやり取りがありません。政党の本来の役割は、政治家個人では無理な部分を、組織的にサポートすることです。そのとき政党は政策論争のキュレーターであるべきです。政治家個人では無理ですが、政党組織としてはちゃんと疑問に答えられて、多くの人は政党のサイトを渡り歩いて、納得できたりあるいは提言してみたりする。そして親近感のあるとこに投票する、というのがあるべき姿です。
今回の総選挙は、さまざまな政党が出てきて賑やかですが、それだけでは済まなくて、政党の内実を強化するきっかけにしていくべきでしょう。選挙の時に持った政治への関心を、有権者が失わずに持ち続け、それに政党や政治家が応えていくというのが、日本の将来にとって、重要な意味を持っています。
(取材・構成 冠木雅夫)
飯尾 潤 (いいお・じゅん)
1962年生まれ。政策研究大学院大学教授(政治学、現代日本政治論)。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。埼玉大学助教授などを経て現職。著書に『日本の統治構造』(中公新書、2007年、サントリー学芸賞、読売・吉野作造賞)、『民営化の政治過程』(東京大学出版会)、『政局から政策へ』(NTT出版)、『現代日本の政策体系』(ちくま新書)など。
-1-300x265.jpg)
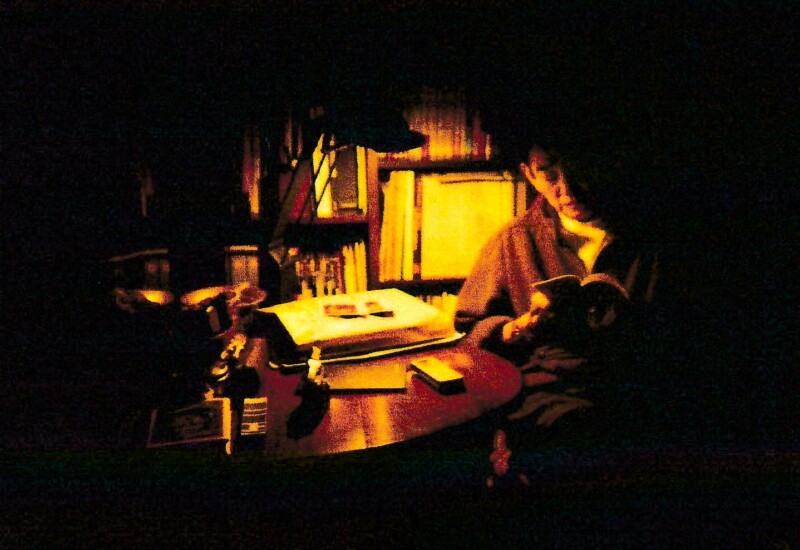








-500x500.jpg)
