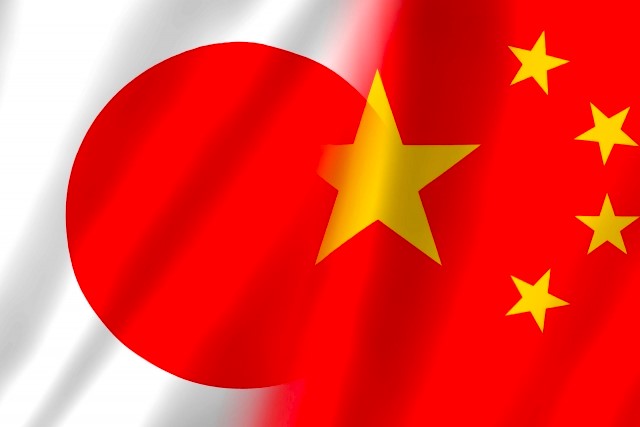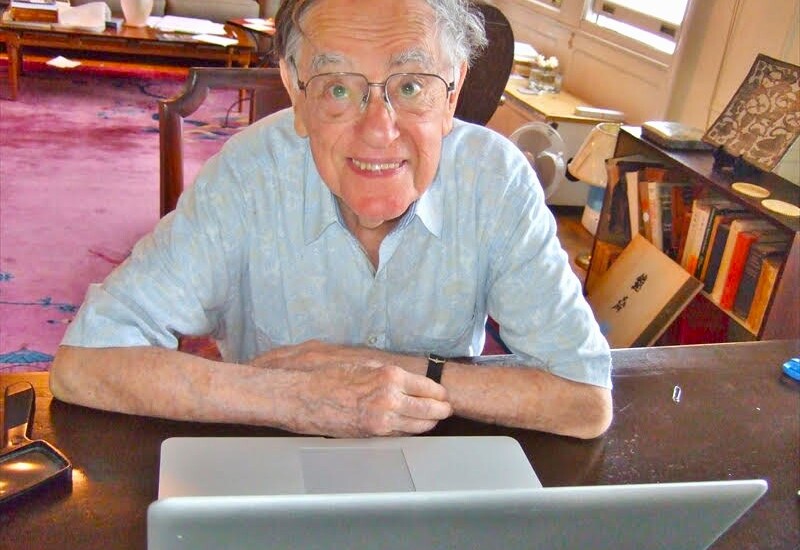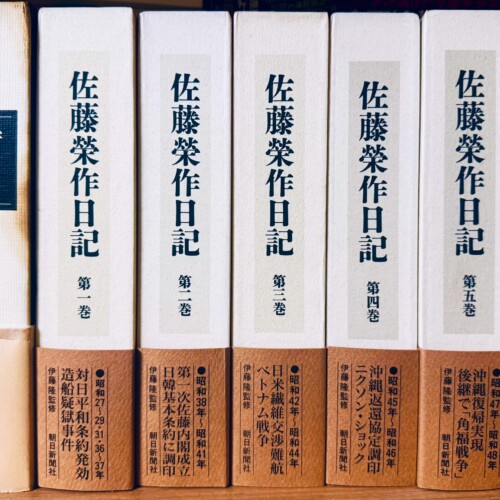コラム 論壇透かし読み 鈴木英生
第4回 女性が政治家であるということ
自民党総裁選で高市早苗氏に期待を示していた雑誌も。
「安倍(晋三)さんが女装して現れた」「中は男でしょ」。先の自民党総裁選に絡んで、田中優子・元法政大総長が高市早苗氏を評した発言で批判を浴びている。
(産経新聞HP2024年10月18日付「サンモニ出演者、相次ぎ炎上 田中優子前法大総長『高市氏は安倍氏の女装。中は男でしょ』」
(https://www.sankei.com/article/20241018-4CSHHGZBYNEURFMZEY2U7DH2WA/?utputType=theme_election2024&utm_campaign
=20241019&utm_content=news&utm_source=newsletter&utm_medium=morning)
田中氏の発言が穏当とは言いがたい。確かに、高市氏は靖国神社参拝などでタカ派なだけでなく、選択的夫婦別姓のような多くの女性を利する可能性が高い政策に反対している。が、本来、女性の政治家だからといって女性という属性に特化した主張をする必要はないし、一口に女性といっても、それぞれの経験や価値観はさまざまだ。「女性の権利に反対する女性」「男女共同参画に反対する女性」がいても、おかしくはない。
そのうえで、自民党の女性議員は高市氏以外にも、「右派」的、復古的な主張の人物が目立つ。今回は、高市氏への支持を分析した論考などを読み、その大きな背景までも考えたい。
総裁選で高市氏は次点に終わったが、<議員の支持獲得で最大のネックになったのは、強烈な高市応援団>だったという(『文藝春秋』11月号、赤坂太郎氏)。高市氏以外を<媚中派>と決めつけ、前回総裁選で高市氏を支持し、今回は他候補を支持する議員を<「裏切り者」「国賊」などと断罪>。高市氏を支持する萩生田光一・前政調会長さえ<少し黙っていてもらいたい>と眉間にしわを寄せたとか。
この「高市応援団」が議員か、SNS上の声か、論者らなのかは判然としない。ただ、特に総裁選前日に最新号の出た『WiLL』『Hanada』といった「保守」系論壇誌(『正論』は直後の10月1日発売)は、「高市首相誕生」への期待に満ちていた。
ともあれ、「高市応援団」のスタンスは、党員全体の傾向とはズレるようだ。中北浩爾・中央大教授が『中央公論』11月号で引用した2019年の読売新聞の調査の場合、党員が自民党に優先してほしい政策や課題で憲法問題は約40%と高くはなく、一般有権者とほぼ変わらない。「保守・リベラルに偏らない中道的な政策」を望む人が45%で、「自民党ならではの保守的な政策」(28%)を大きく上回っている。安倍晋三政権下ですら、こうだったのだ。
にもかかわらず、1回目の投票の党員・党友票で高市氏はトップに立った。想定される理由の一つとして、中北氏らは、高市陣営のみが全国約30万人の党員に郵送した政策リーフレットの効果をあげる。手元に届いたリーフレットがこれだけならば、個人後援会などの集合体という側面のある自民党の場合、「うちの代議士先生は高市氏支持だ」と誤解する人がいてもおかしくない。
個人後援会の集合体、言いかえると<政党組織の脆弱性>(『世界』11月号、大川礼子・駒澤大名誉教授)は、日本政治の特徴の一つだ(公明党、共産党除く)。勢い、世襲候補や業界団体の組織内議員ら、個人で集票マシーンを持つ人が選挙に強い。また、大川氏によると、今年8月現在で衆院議員の女性比率10・8%は世界184カ国中116人。2021年衆院選の当選者の平均年齢は55・5歳。つまり、衆院議員の圧倒的多数は中高年男性である。
世襲議員や組織内議員が強いことと女性議員の少なさ、「右派」の女性議員が目立つこととの関係は、別で論じたので繰り返さない。(毎日新聞HP2024年10月14日付「24色のペン:高市早苗氏らが「代表」するもの」https://mainichi.jp/articles/20241013/k00/00m/010/047000c)
この拙稿に近い指摘として、中野円佳・東京大准教授は<とりわけ与党では、特別に男性に求められ仲間に入れてもらえる女性、つまり「名誉男性」化した女性のみが登用されてこなかっただろうか>(『Voice』11月号)とする。高市氏ら「右派」的な議員を念頭に置いた言葉と受け取れた。
中野氏は逆に、過去最多と並ぶ5人の女性が入閣した岸田文雄政権の内閣改造(23年9月)後、岸田首相が「女性ならではの感性や共感力も十分発揮」と記者会見で発言した点にも触れる。
「名誉男性」化しないと出世できなかったり、逆に<「女性としての」「女性ならではの」という期待>をされたりする。いずれにせよ、一人の政治家、人間である以前に、「女性であること」で評価される。本稿冒頭でとりあげた田中氏の発言も、女性の議員に自らの望む「女性としての」立場を求め、そこに反する高市氏を批判している点で、実は同じ思考の枠内にあると解釈できそうだ。
無論、政治の世界で多数派である男性が「名誉女性」であることを求められたり、「男性としての」「男性ならではの」という期待をされたりすることはない。言い換えると、多様な女性が議員となり、「女性も一枚岩ではない」ことが政治でも常識となれば、本稿のような議論は必要なくなる。そこで具体的に何をすべきか。
たとえば、中野氏によると、内閣府の男女共同参画局の調査報告書(21年)で、選挙への立候補を断念した理由で男女差が大きい項目の一つは、「当選した場合、家庭生活との両立が難しい」だった。そこで、自民党ですら「女性議員の育成、登用に関する基本計画」(23年6月)で、今後10年で女性議員の割合30%を目標にしている。この基本計画は、女性候補者支援金制度創設や衆院の比例代表上位を女性にすることのほか、ベビーシッターや一時保育利用料の費用負担、有権者からのハラスメント対策強化なども盛り込んだ。
菅野志桜里・元衆院議員は、X(旧ツイッター、2024年10月18日)で<そもそも高市議員は「全国民の代表」であるべきで「女性の代表」である必要は全くない>と田中氏の発言を批判した。
(https://twitter.com/ShioriYamao/status/1847143057642475638)
その通りのはず。が、「全くない」と言い切れるためには、実現すべきことがまだまだ山積しているのだとも思う。
鈴木英生(すずき・ひでお)
1975年生まれ。毎日新聞青森・仙台両支局などを経て現職。学芸部で長く論壇を担当し、「中島岳志的アジア対談」など連載を元に書籍複数。
 鈴木英生(毎日新聞専門記者)
鈴木英生(毎日新聞専門記者)