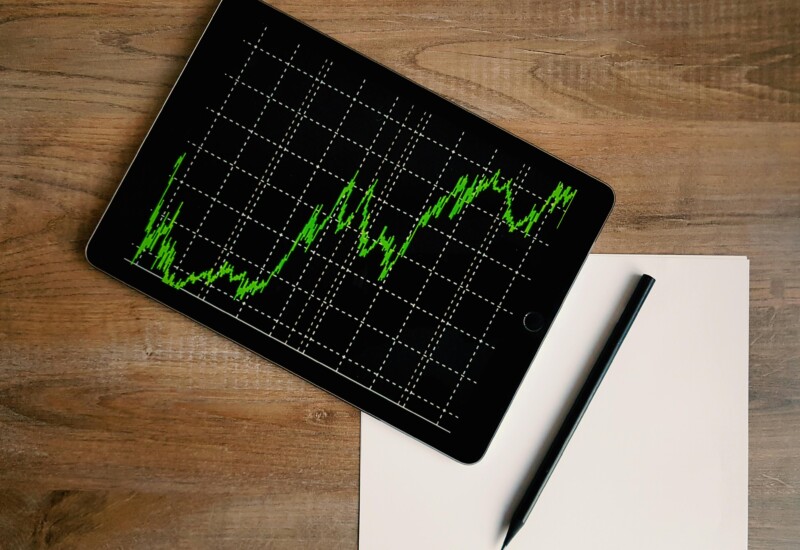難民と日本社会を考える(全2回)
橋本直子・国際基督教大学准教授に聞く

写真は東京出入国在留管理局の庁舎。
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、2023年末現在、「紛争や迫害によって故郷を追われた人」は1億1730万人にのぼり、その後も増え続けています。各国はそれぞれに国内での葛藤を抱えながら、難民保護の取り組みを続けています。受け入れが少ないとされる日本ですが、どういう課題があるのでしょうか。実務経験の豊富な研究者、橋本直子氏(国際基督教大准教授)に、日本社会にとって無理のない難民保護策や社会に溶け込んでもらう方策について語ってもらいました。
第1回 日本にとって無理のない保護政策
◇必ずしも排外主義的ではない日本社会
日本で難民認定が出るケースは極めて少なく、2023年は13823人が難民申請を行い、認定されたのは303人と、G7各国と比べて非常に厳しい数字になっています。
しかし一方で、日本社会が難民受け入れに後ろ向きで排外主義的かと言えば、必ずしもそうではありません。グローバル・マーケティング・リサーチ会社のイプソスが毎年発表している難民に対する意識の国際比較調査によれば、日本人は世界平均と同じか、それ以上に「難民受け入れが必要」と考えていることがわかります。
例えば「迫害や戦争を逃れる人は、あなたの国(日本)を含む他国で保護されるべきだと思いますか」という質問に、「はい」と答えた人は67%に上り、世界平均の73%と比べてもそう低くはありません。
また、「他国と比較して、あなたの国(日本)の難民の受け入れは十分だと思いますか」という質問に「十分すぎる」と答えた人は16%と世界最下位。「少なすぎる」と答えた人は31%でした。一方で、「日本に来る難民は日本社会になじむことができると思いますか」という質問には「はい」と答えた人が22%という結果も出ています。
つまりこの調査からは、日本人が「難民をもっと受け入れるべきであり、日本の受け入れ人数が少ないことは理解しているが、外国人が日本に来ても社会になじめないのではないかと心配している」ことが浮かび上がってきます。
だからこそ、これまでの日本は難民の受け入れ数こそ少ないものの、海外にいる難民への財政的支援には力を入れてきたのかもしれません。
◇第三国定住制度を増やす選択肢
また、受け入れに関して言えば、日本は1970年代後半に、インドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)から難民が大量流出した際、その一部を受け入れています。20年近くの間に1万人以上が日本で生活するようになりました。また軍事クーデターが起きたミャンマーからは第三国定住という制度に基づき、2010年以降、122家族305人の難民を受け入れています(2024年4月時点)。
第三国定住制度とは、自力で日本にわたってきて難民申請をする方法(「待ち受け方式」という)ではなく、自国を出て近隣諸国の難民キャンプなどにとどまっている難民のうち、家族要件や健康状態等を考慮し、面接を経て「受け入れ可能」とみなされた人に第三国への定住を許可するという制度です(「連れてくる方式」ともいう)。
日本社会は順法精神の高さから、不法な状態でやってくる難民に対する目が厳しい。であれば、「連れてくる方式」であるところの第三国定住を増やすのは選択肢の一つになるでしょう。この第三国定住型の難民受け入れは世界の潮流になりつつあります。
この第三国定住制度では来日後、6カ月にわたる日本語や日本社会での生活ルールなどを知るための研修を受ける義務があります。そのため、研修後も日本社会になじみやすい状況があり、実際にこの制度で日本にやってきた難民はその後、様々な職業に就き、日本社会の一員として、ごく普通の生活を送っています。

日本は、日本なりの難民受け入れの形を作っていくことも重要だ。
◇難民はその国でのエリート(強者)的な人が多い
ただし、やはり人数が少な過ぎること、自国で迫害を受けた立場であることから身元を明かしてメディアの取材などを受けられないことで、なかなかその生活ぶりが日本で知られないという課題もあります。
この「知られていない」ことも、日本人の難民に対する意識に影響を及ぼしています。冒頭でイプソスの調査結果をご紹介しましたが、この調査における日本の回答はいずれの質問でも「分からない」「どちらでもない」「無回答」の割合が他国と比べて多く、そもそも難民についての情報をあまりよく知らないという姿勢も見えてきます。
インターネットなどでは時折、難民批判の極端な言説が書き込まれますが、その中には「難民が飛行機でやってくるはずがない」「難民なんて抱えたら、生活保護を払わなければならない」といった、実態とはかけ離れた「難民像」を前提としたものも少なくありません。
難民というと、戦争で住むところを追われ、難民キャンプに身を寄せる、お腹を空かせた貧しい生活を強いられている人たち、という印象を持つ人もいるかもしれません。しかし実際の難民の定義において中核をなすのは「自国で政治的迫害を受けた人」。つまり、政府に反対するような政治的立場を確立している人、となります。そのため、難民申請をしている人たちの中には、反政府的なジャーナリスト、野党政治家、人権活動家などが多く含まれます。
実際に、私がイギリスで知り合ったエチオピア出身の難民は自国で検察官を務めており、政府高官の汚職を追及しようとして当局から命を狙われることになったために難民申請をしたという人でした。また、あるミャンマー難民は、自国では五か国語を使いこなすジャーナリストでしたが、民主化活動家でもあったために拘禁され、命からがら日本に来て難民申請しました。現在は大学教員を務めており、いわゆる「かわいそうな、生活支援を必要とする難民像」とは一致しないのです。
もちろん、自国にいれば迫害を受け、拷問や著しい人権侵害の危険がありますから、気の毒な境遇であることに違いはないのですが、こうした難民たちは日本へ当然飛行機でやってきますし、生活保護を受ける対象になるどころか、日本でしっかり働いて税金や社会保障費を納めてくれている人が大半です。
このように、実際には、難民はあらゆる意味で「強者」であることが多いのですが、日本で「難民」と言った場合にイメージされるのは、あらゆる意味での「弱者」。そのため一部ではそのイメージを逆手に取り、「こういう人たちが大量に日本に来たら、社会保障費がかさんでしまう」「だから受け入れは慎重であるべきだ」という発想につながるのでしょう。
◇日本社会に合った受け入れ方式を
こうした「難民像のズレ」がおきるのも、ひとえに情報が少ないから。新著『なぜ難民を受け入れるのか』(岩波新書)では、日本だけでなく各国の難民受け入れの現状や課題とともに、難民たちの実態にも触れています。イメージの修正は今後の課題ですが、先にも述べた通り、難民として日本に来た人たちをメディアが大々的に取り上げるのは難しい面があるのも事実です。
本国で受けた迫害から逃れるために国を出ていますから、顔がわかってしまうと追跡の手が伸びてこないとも限りませんし、家族や親戚が本国に残っている場合には何をされるか分からないという事情は汲む必要があります。
2022年のロシアによるウクライナ侵攻によって、日本にもウクライナ人が3000人近く、避難してきています。彼らが顔を出してメディアの取材を受けられるのは、ウクライナ人の大多数がゼレンスキー政権から迫害を受けて逃げてきた難民ではなく、あくまでもプーチンの侵攻からの避難を余儀なくされた避難民だからです。ウクライナの人々は侵攻が終われば、またウクライナに帰って国の復興に尽力するでしょう。一方、難民は本国に帰れば命の危険があるのです。
順法精神の高い日本社会では、非正規滞在の難民に対する抵抗があるのは事実でしょう。であれば、「連れてくる方式」の一つである第三者定住の人数を増やすことは、十分検討に値します。世界には難民受け入れに長年多くの経験を積んできた国はたくさんあります。他国の成功例・失敗例をしっかり学んだうえで、日本は日本なりの難民受け入れの形を作っていくことも重要です。
(取材・構成 梶原麻衣子)
橋本直子(はしもと・なおこ)
1975年、東京都生まれ。国際基督教大学准教授。オックスフォード大学強制移住学修士号、ロンドン大学国際人権法修士号、サセックス大学政治学博士号取得。専攻は国際難民法、強制移住学、庇護政策研究。国際組織論。在ニューヨーク国連日本政府代表部人権人道問題担当専門調査員、国際移住機関ジュネーヴ本部人身取引対策課プログラム・オフィサー、国連難民高等弁務官事務所北部スリランカ(ワウニヤ事務所)准法務官、外務省総合外交政策局人権人道課国際人権法・人道法調査員、国際移住機関駐日事務所プログラム・マネージャー、一橋大学大学院社会学研究科准教授などを歴任。現在、(法務省)難民審査参与員などを務める。著書に『難民を知るための基礎知識』(共著,明石書店)、Migration Policies in Asia(共編著、Sage)、『なぜ難民を受け入れるのか 人道と国益の交差点』(岩波新書)ほか。