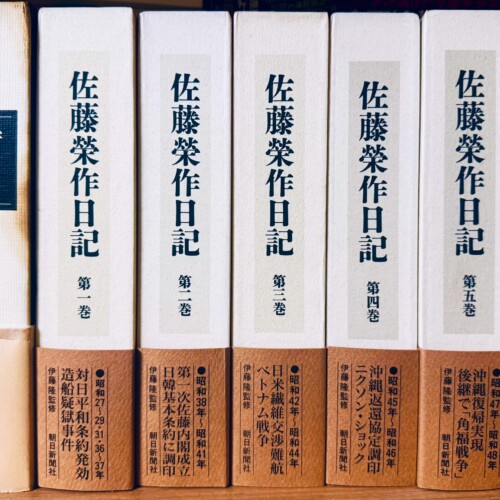コラム 論壇透かし読み
鈴木英生

与那国島(沖縄県)から見た東シナ海。台湾までわずか約110キロだ=2024年10月、鈴木英生撮影
第5回 中国と沖縄の接近?
中国海警局の船と日本の巡視船が目の前でにらみ合う――。山田正彦・東海大教授が、尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺の東シナ海での石垣市と東海大による海洋調査の模様を写真付きでルポした(『正論』12月号)。その一コマだ。
中国は尖閣周辺に近年、海洋観測用とおぼしきブイの設置を繰り返してきた。山田氏はブイ設置を、時間をかけて少しずつ他国領土・領海を侵略する「サラミ戦術」の一環だと警鐘を鳴らす。先の日中首脳会談でも、石破茂首相は東シナ海情勢に深刻な懸念を表明したが……。
東シナ海での中国の攻勢は、物理的なものだけではない。紀実作家(ルポライター)の安田峰俊氏によれば、最近の特筆すべき動きとして<沖縄に仕掛けている浸透工作>がある(『Voice』12月号での益尾知佐子・九州大教授との対談)。
中国側には<尖閣諸島だけではなく、沖縄に日本の主権が及んでいる現実をも揺さぶろうという意図>(益尾氏)があり、沖縄の政治家や琉球独立を掲げる団体に近づいているという。東京の中国大使館や福岡の中国総領事館から沖縄県庁に高官がしばしば訪れたり、彼らが県庁からの訪問を受け入れたりしている。インターネット上には、中国発とおぼしき「琉球独立」の動きなどを報じるフェイク記事が何本もアップされてきた。
たとえばそうした記事に「コメント」が載った「琉球民族独立総合研究学会」元共同代表の松島泰勝・龍谷大教授は、取材を受けた覚えがなく「完全なディスインフォメーション(偽情報)だ」と批判していた(『朝日新聞』9月25日https://digital.asahi.com/articles/ASS9P3FHJS9PUTIL032M.html)。こうした記事は、沖縄の人が「反日」だと強調することで、「日本と琉球の対立を生み出そうとしているのだろうか」とも。
ともあれ、安田氏らは、沖縄が事実上の対中接近をしていると警鐘を鳴らす。が、<沖縄は中国に取り込まれないようにすべきだ、という日本本土の識者の主張は沖縄側には響かない>(山本章子・琉球大准教授、『朝日新聞』11月7日https://digital.asahi.com/articles/ASSC534K9SC5UPQJ019M.html)。すわ、やはりそれほど親中なのか?
いや。薩摩藩による侵略(1609年)、明治政府の琉球処分(1872~79年)、米軍統治(1945~72年)と、大国に翻弄され続けてきた沖縄にとって、自分たちが外部から都合よく解釈されたり警戒されたりするのは、「またか」という話。1944年に米海軍が作った「ハンドブック」も、<琉球島民は日本人から民族的に平等だとはみなされていない>と指摘したうえで、<島民は島の伝統と中国との積年にわたる文化的つながりに誇りを持っている>ことを<政治的に利用できる>と分析していた。
なお、小泉悠・東京大准教授が少し前、沖縄の基地負担などに触れて<日本政府が自身を正さずにいると、他国が仕掛ける陰謀論やプロパガンダにお墨付きを与えてしまう>としていた(『東京新聞』7月16日https://www.tokyo-np.co.jp/article/336296)。つまり、沖縄工作は日本の「国内問題」が許している面もある。
『世界』12月号でも、毛利亜樹・筑波大助教が中国の覇権主義と抑圧体制を強く批判していた。ただし中国は、尖閣諸島のある東シナ海を「平和・協力・友好の海」とする2008年の日本との合意を19年にも再確認して見せたり、11月15日の日中首脳会談でも「戦略的互恵関係」の包括的推進と建設的、安定的な関係構築を確認したりしてきた。単に攻勢一本槍ではない。
毛利氏は、益尾氏ら同様に既存国際秩序への挑戦者として中国を批判するが、個人的経験から<党国家としての中国と個々の中国人>を区別する大切さも強調している。国家間の関係が困難であり続ける以上、日中社会の紐帯は重要な安全装置でもある。中国のエリート研究者らの胸の内などを描いた佐々木れな氏(米ジョンズ・ホプキンス大博士課程在籍)のコラム(『Foresight』https://www.fsight.jp/articles/-/50990)も参考になるだろう。
益尾氏も<日本側から露骨な反中シグナルを送ることはやめたほうがよいのでは>として、蔡英文前総統時代の台湾の事例を挙げる。安全保障を確保しつつ、経済や国民生活も守るため、米国に<戦争の可能性を過度に強調すべきではない>と説得していたらしい。
隣国から逃げることはできない。であれば、中国という国家の行動原理をよく理解して適切な警戒と抑止を怠らず、かつ<私たちの日常生活を運営し続ける工夫が必要です>(益尾氏)。さて、今日は「ガチ中華」(日本人の舌に忖度しない味の現代中国料理)の店にでも出かけてみようか。
鈴木英生(すずき・ひでお) 毎日新聞専門記者
1975年生まれ。毎日新聞青森・仙台両支局などを経て現職。学芸部で長く論壇を担当し、「中島岳志的アジア対談」など連載を元に書籍複数。





-500x457.jpg)

-500x457.jpg)
-500x500.jpg)