石破外交 出遅れどうする?
手探りの対トランプ関係
鈴木 美勝(ジャーナリスト)

米ホワイトハウスのホームページ (https://www.whitehouse.gov/)
外交裏舞台「番外」編──地殻変動下の日米関係
1月20日に幕を開けた「トランプ劇場2.0」──。第47代米大統領ドナルド・トランプは就任式初日から、議会の承認なしで直ぐに法的拘束力を持つ大統領令を連発、中ロ両国にも似た独裁者張りの政権運営を始動させた。「米国を再び偉大に(MAGA)」を政権目標に掲げるトランプにとって、当面の戦略目標は中国に対する国際的優位性の保持と確立、ウクライナ戦争の停戦、2年後の中間選挙での勝利だ。まずは、節目の100日を念頭にロケットスタートを切り、満を持して研ぎ澄ましてきた“武器(関税や暴言・妄言交じりの発言)”で攻勢をかけている。こうした中で対応を迫られる首相・石破茂。第1期トランプ政権下での安倍晋三(首相)のサクセス・ストーリーは、トランプが大統領職を経験し、国際環境も激変した今では参考にならない。
◇日本の「裏舞台外交」喪失
新年が明けるや、日米両国間では、退陣間近のバイデン政権下での駆け込み外交が活発化した。国務長官ブリンケンが来日、外相・岩屋毅との会談、首相・石破への表敬訪問を皮切りに、日本側はカーター元大統領の国葬に首相特使として送った菅義偉(元首相)が上院議員ハガティ(前駐日大使)と会談、さらには岡野正敬外務事務次官(現・国家安全保障局長)とウォルツ下院議員(現・国家安全保障担当大統領補佐官)の会談、日米比3カ国首脳オンライン会談などが相次いで行われた。
そして、トランプ政権が誕生すると、外相・岩屋が、自身出席した大統領就任式の翌21日に新国務長官ルビオと会談、加えて、豪印を含めた「QUAD(クアッド)」4カ国外相会合に出席するなど、石破・トランプ初の日米首脳会談に向けて地ならしを行った。
こうした一連の動きは表舞台の外交。石破は2月6~8日に訪米し、「日米同盟のさらなる強化」に向けて大統領トランプと初めて対面での会談に臨む。駐米大使・山田重夫の精力的な外交活動や米国の政治コンサルタントを活用した情報収集が行われてきたが、政治、防衛、経済各分野での責任分担(バードン・シェアリング)の在り方やUSスチール買収問題等々で米側が具体的にどのように出てくるのか、定かではない。特に、肝心のトランプ自身の腹が読めず、日本側には不安が広がる。不安要因は何か。その一因は、これまで石破がトランプと接触したのが、わずか5分間で終わった大統領選直後の電話会談のみという点。「表」舞台の外交を補強する「裏」舞台での首脳外交が実質的に皆無のためだ。

トランプ第二次政権の始動を伝える主要紙(2025年1月22日付朝刊)
石破は11月、20カ国・地域首脳会議(G20サミット)出席の帰途、米国に立ち寄る形でのトランプ会談を模索。実際、会談を申し入れたのだが、「民間人が政府の許可なく外国政府との交渉を禁じる」ローガン法(1799年制定)を理由に、体良く断られた。12月半ばになると、元首相夫人・安倍昭恵とソフトバンク・グループ会長・孫正義が南部フロリダ州の次期大統領トランプ邸「マールアラーゴ」に、個別に招かれて懇談の機会を持った。もっとも、元首相夫人の場合は、非業の死を遂げた安倍に弔意を表すため、トランプ夫人のメラニアが招いたプライベート色強い社交の域を出ず、孫正義はと言えば、ビジネス本位の懇談。どちらも「裏舞台外交」への有効打にはならなかった。
◇マールアラーゴでの「裏舞台外交」
その点、注目すべきは、「マールアラーゴ」を目指した各国の対トランプ・アプローチ競争の中で、特別に遇されたアルゼンチンとイタリアだ。
トランプが対応した「マールアラーゴ」での裏舞台外交──ここでは昨年11月の大統領選勝利後、今年1月20日の就任前──の次期大統領時の外交を指す。ちなみにこの間、トランプが自身の邸宅で会談した外国の要人(VIP)は、次の限られた首脳たちだった。
「マールアラーゴ」に招かれた最初の外国政府のVIPは、アルゼンチン大統領ミレイ(11月14日)で、次いで北大西洋条約機構(NATO)事務総長ルッテ(11月23日)、カナダ首相トルドー(11月29日)、ロシア寄りの姿勢で知られるハンガリー首相オルバン(12月9日)らがトランプ邸を相次いで訪問した。年が明けると、イタリア首相メローニ(1月4日)が賓客として招かれた。
このうち、国家の財政難に苦悩するトルドーの場合は、トランプがカナダからの輸入品に大幅な関税をかけると発言していることを憂慮、半ば押し掛ける格好で「マールアラーゴ」を訪れた。が、席上、トランプは言い放ったという。「(関税アップを回避したいなら)米国の51番目の州になるべきだ」。そそくさと帰国したトルドーは、支持率低迷もあって、その約一カ月後に退陣を表明する羽目になった。

米国とカナダの国旗が並ぶ国境
こうした中で、トランプが自身の戦略遂行に最も有効な「手駒」として最重視し、邸宅に招いたのが、アルゼンチン大統領と伊首相だ。二人の共通点は一介の起業家から大富豪に成り上がったイーロン・マスクとの緊密さだ。
◇アルゼンチンとイタリアを重視
アルゼンチン大統領ミレイは「世界初のリバタリアン(自由至上主義)国家元首」と称される人物。就任後、大胆な行財政改革を推進、国家財政・経済の立て直しに手腕を発揮するなど、パナマ運河の運営に影響を強めようとする中国の拡張政策と不法移民の出処と見なす、米国の「裏庭」──中南米地域での存在感も増している。また、マスク率いる新組織「米連邦政府効率化省(DOGE)」は、ミレイの改革案をモデルにしたと言われ、マスクとの親交の深さも伝えられる。その新組織は、20日にトランプが署名した大統領令で、「米国DOGEサービス」と改称してホワイトハウス内に設置された。当のマスクはホワイトハウス別棟の一室を占有、トランプに強い影響力を持っていることを内外に示している。

風にはためくアルゼンチン国旗
もう一人、トランプが対欧州・ロシア外交政策で重きを置くのが、主要七カ国(G7)の中で、政局が安定しているイタリアの首相メローニだ。マスクと親交がある上、極右政党「イタリアの同胞」(FDI)を率いて政権基盤も強固。11月6日、「トランプ大統領勝利」が報じられた後の対応は迅速だった。早々と電話で祝意を伝えると共に、8日には、欧州理事会非公式会合後の記者会見で、トランプの対欧心理を読み解き、次のように強調した。「米国の関税率引き上げ問題の根源は、2022年にEUが(気候変動対策の観点から)成立させたインフレ抑制法(IRA)にある。欧州は、米国が何をしてくれるかではなく、自らのために何ができるかを考えるべきだ」。また、1月4日の「マールアラーゴ」会談では、夕食を共にしながらじっくり話し込み、「二人は一緒に仕事をする準備ができている」と胸を張った。さらに「(トランプは)戦略的に重要な地域が中国など競争国の手に落ちることを許さないと言っているだけ」などとも発信、トランプが求める欧州国防費の増額も支持するなど、欧米間の調整役を果たすことに強い意欲を示した。

青空に映えるイタリア国旗
国際政治の平時が過ぎた現在、世界には乱世を飛び越えて「大乱世」が到来した。まさに危機的な地殻変動期、日本も大胆かつ巧みに対応しなければならない。昨年11月下旬、首相補佐官・長島昭久が渡米、米政府関係者や上下両院議員、外交安全保障関係の有識者と会談したが、石破外交に出遅れ感は否めない。今後、外相・岩屋が高校時代から友人である孫正義のルート、そして隠れたる有力な人的ラインとして、日米安保コミュニティで多彩なネットワークを持つ髙橋杉雄(防衛省防衛政策局戦略企画参事官、防衛研究所防衛政策研究室長併任)─エルブリッジ・コルビー(国防次官)のルートがどれだけ機能するか注目される。
◇「情」より「理屈」が先立つ危うさ
昨年12月24日、石破は、大統領選最中の4月にトランプと会談した麻生太郎(当時・自民党副総裁、現・党最高顧問)に、1月7日には、孫正義とそれぞれ会って助言を求めた。共に「長々とした説明を避けて簡潔に結論を言わなければいけない」「ストレートな方なので回りくどい話をせず、日米関係の重要課題について端的に伝えれば良いのではないか」などとの助言を受けたが、当の石破は「それが一番苦手だ」と本音を漏らしたと言われる。
政治指導者の在り方、心得に関して数多くの至言を残したリチャード・ニクソン(米第37代大統領)にこんな言葉がある。「経営はprose(散文)だが、指導はpoem(詩)だ」──。いわく「人間は、理屈によって納得するが、感情によって動く。指導者は、人々を納得させると共に、人間を動かさなければならない」。これは内政・外交─政治一般に当てはまる普遍的原理・原則だが、先行き不確実な状況を踏まえてニクソンの至言を念頭に置くと、「情」より「理屈」が先に立つ政治家・石破の危うさが見えてくる。幸いにしてトランプの視線は今、中国、ロシア、欧州、メキシコ、カナダに向けられており、裏舞台外交を機能させる猶予はまだある。今後、裏舞台で使える人脈を掘り当てて、トランプと直結する太いパイプを構築することが求められる。(敬称略)
※ 本サイトで好評連載コラム「外交裏舞台の人びと」で使っている<裏舞台>という言葉は、「楽屋」や「舞台の裏側」を意味する「舞台裏」と峻別した筆者の造語で、「裏街道・裏通り・裏道」が意味する「主要な道路の背後にある道、表街道に沿ってその裏手にある公式でない道、比喩的に本道に外れた正攻法でないやり方」からイメージされる言葉を模して使っている。
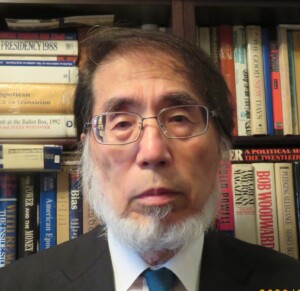
鈴木 美勝(すずき・よしかつ)
ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(いずれも筑摩書房)、『いまだに続く「敗戦国外交」──「衆愚」の時代の新外政論』(草思社)、『小沢一郎はなぜTVで殴られたか──「視える政治」と「視えない政治」』(文藝春秋)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。

-800x550.jpg)









