シリーズ「戦後80年 日本の変革」
あるべき日中関係を築くために──(上)
宮本 雄二(元駐中国大使、宮本アジア研究所代表)
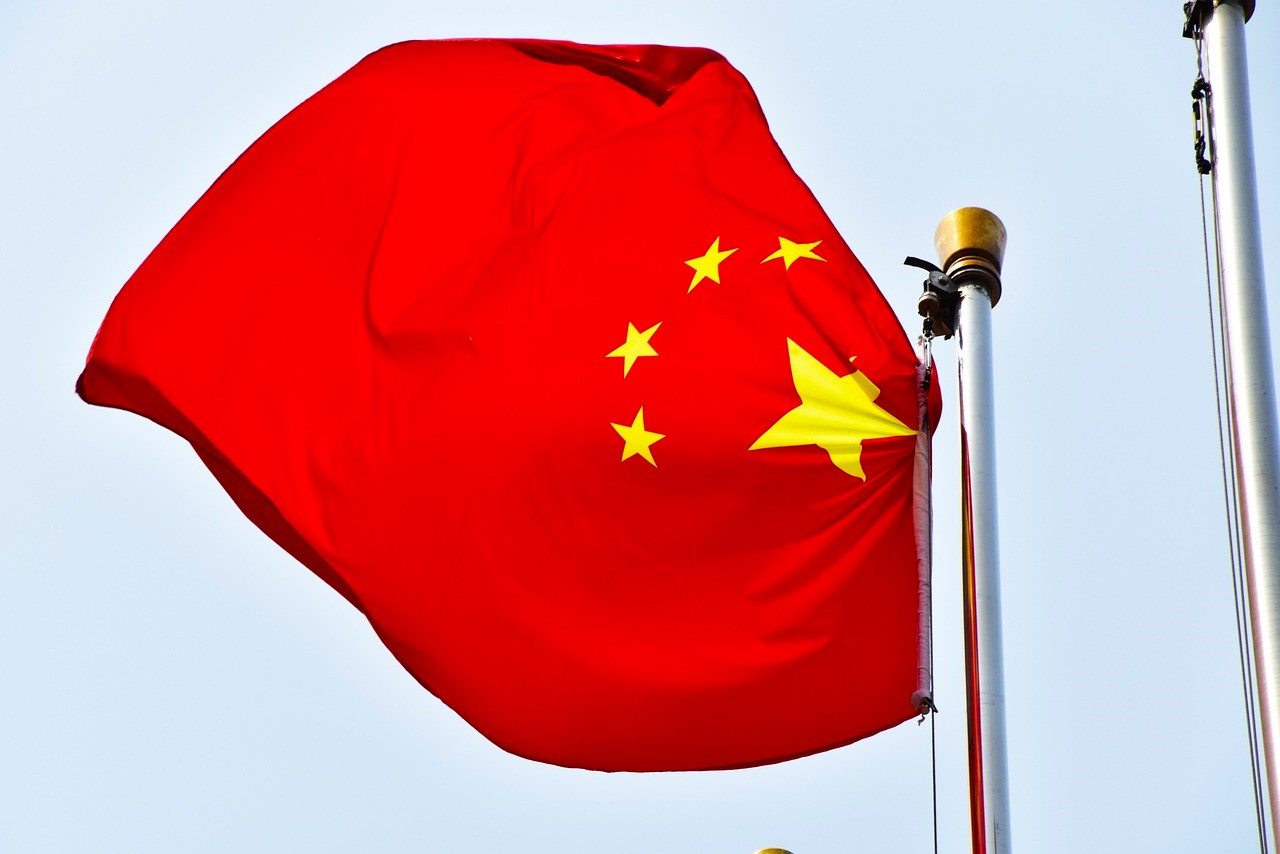
過去を振り返り、未来を展望する――言い古された言葉だが、今日ほど、このことが必要なときはない。過去と未来の間に現在がある。現在は瞬時にして過去になるのだが、先ず現時点において日本と中国、そして世界が置かれている情況から眺めていこう。ここを正確に把握することによって、無数に存在する「過去」から何を学んだら良いかが分かるし、無限に展開する「未来」にどういう方向性を与えたら良いかが見えてくる。
1.われわれが直面している世界
◇トランプ大統領再選の衝撃
2016年の大統領選挙でトランプ氏が当選し、われわれはあり得ないことが起こったと驚愕した。20年にバイデン氏がトランプ氏に勝利し、これで米国は元の線に戻ってくれるのではないかと安堵したのもつかの間、24年にトランプ氏が再選を果たした。これにより米国の有識者やマスコミの「常識」が米国社会の多数派の「常識」ではないことが証明された。つまり米国社会は深層において大きく変化していたのだ。
それは戦後80年、米国社会を主導してきた自由民主主義(リベラル・デモクラシー)の終焉であり、リベラリズム(自由主義)に代わる新たな形の「デモクラシー」を米国民が見つけ出すプロセスの始まりでもある。それがどういうものになるのかは、まだ分からない。リベラル・デモクラシーを支える平和、自由、平等、人権などの理念は、また、第二次世界大戦後、ルーズベルト大統領が主導して作った戦後国際秩序を支えた。その同じ理念は、日本国憲法にも国連憲章にも高らかに謳われている。
だが今や、米国社会の多数は少数者の人権の擁護に嫌気がさし、移民の増大に苛立ち、“不公正な”自由貿易が、自分たちの仕事を奪っていると思っている。こういう米国にしたのは、米国社会を牛耳ってきたリベラルな高学歴のエリ-トたちだと思っている。戦後国際秩序からは、もう「配当金」は来ないし、持ち出しばかりだと感じている。トランプ後の米国は、当分の間、徹底した米国第一主義であり、自分に都合の良い形でしか国際社会とは付き合わないであろう。

◇米国の変化の世界への影響
米国の持ち出し分を取り戻す動きが「関税」となるし、同盟国への国防費負担増の要求となる。しかしトランプ政権のやり方は、多国間主義の否定であり、国際協調の放棄であり、自由貿易の否定である。何にもましてルールに基づく世界の、ルールそのものの破壊となる。これでは戦後80年、世界の平和と発展を支えてきた国際秩序は持たない。
トランプ政権の欧州に対する姿勢、ウクライナ問題への対応は、米欧関係を変化させた。米国の関与が低下しても欧州に対するロシアの核兵器を含む軍事的脅威は続く。欧州は自分たちでロシアの脅威に対処する方向に舵を切った。欧州は、4億5千万の人口と、ほぼ米国に並ぶ経済規模を持つ。しかも英仏は核兵器を保有する。最後は、自分で自分を守ることは可能なのだ。
東アジアに目を転じれば、米中の経済戦争は始まったばかりだ。米国の東アジアの安全保障に対する関与は、今回の日米首脳会談後の共同声明で担保されたはずなのに、どこにも安心感はない。米国の多数意見は、中国との競争に負けるつもりはなく、中国に対する押さえ込みは続ける、というものだろう。だが、トランプ大統領の、東アジアの安全保障に対する思い入れは伝わってこない。東アジアの不確実性は、この意味でも大きくなった。東アジアの安全保障は、核兵器国化に邁進する北朝鮮と軍事力の増強が止まらない中国、そしてロシアの動きに焦点が当たる。しかし東アジアには欧州のような諸国連合もなければ、この地域の平和と安全を話し合う場もない。そのなかで中国の力が突出し、北朝鮮やロシアが蠢動することになる。事態は、欧州以上に、遙かに厳しいのである。

◇将来をどう見るべきか
米国社会は何度も大きく変わってきた。「トランプ・シンドローム」は、米国の自己変革の始まりだと見ておくべきだ。米国が、米国憲法の根幹を全面否定して全く別の、例えば専制国家になることはない。移民の国である米国は、憲法の指し示す価値観と原則を唯一の核としてまとまってきた。歴史的、文化的背景を異にする人たちをまとめるものは、これ以外にないからだ。現在起こっていることは、この価値観や原則の解釈をめぐる対立であり、その否定ではない。現に全ての人が「自由」を口にしている。米国社会は、いずれ新たな妥協点を見出し、国際社会との折り合いをつける日が来るであろう。しかも、その間、世界第一の大国であり続ける。
問題は、米国が落ち着くまでの間をどうするかだ。私は、世界の平和と発展は、現行国際秩序の骨格を維持する以外に、持続不可能だと考えている。2つの世界大戦の経験を踏まえ、人類の平和と経済的繁栄を実現する仕組みとして考え出されたのが、現在の国際秩序であり、それを越えるものを人類はまだ持たないし、その影さえ見えない。現行国際秩序に問題は山ほどある。特にグローバルサウスの国々の不満は大きい。それでも現行国際秩序の故に、グローバルサウスの国々を含めた戦後80年の世界の発展がある。これが崩壊すれば、「ジャングルの掟」が待っているだけだ。現行国際秩序を護持し、改善し、発展させることこそが、国際社会の生きる道であり、多数意見であると確信する。
激変する世界と戦後80年の日中関係
◇日中関係の原点
1972年の日中国交正常化に伴う日中共同声明及び78年の日中平和友好条約こそが、日中関係の原点であり、基本的枠組みを構築する。それは直接、戦火を交えた世代の方々が、日中は2度と戦ってはならないという不動の信念に基づき作りあげた、国と国との約束である。われわれに対する遺言と言っても良い。よくルールに基づく国際秩序などというが、ルールの根幹をなすものが国際法であり、二国間条約及び国連憲章のような多国間条約である。ここをいい加減して、ルールに基づく国際秩序を云々するのは偽善である。故に日中平和友好条約は、必ず履行されなければならない。
日中平和友好条約は、日中の恒久的な平和と友好、そして協力関係の構築を求めている。これが日中関係の目指すべき方向である。その後、98年の共同宣言、2008年の共同声明が付け加わり、日中の4つの政治文書となったが、日中が目指すべき方向については毫も修正はない。今日においても変わりはないと言うことである。この基本的方向性は、しっかりと再確認しておく必要がある。平和、友好、協力の反対語は、戦争、敵対、妨害である。隣国の大国同士の関係にある日中が、そのような関係に陥れば、東アジアに平和と安定はなく、経済の発展も、また不可能となる。故に、日中は所与の内外情勢の中で、平和、友好、協力の共通目標に向かって、ともに努力する以外に、日中両国にとり、選択の余地はない。
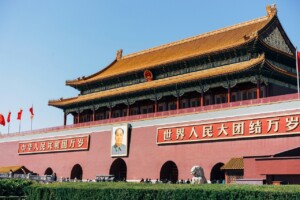
◇日中関係の変質
2012年の、所謂「尖閣国有化問題」を契機に、中国は力による現状変更を始めたことで、日中関係は大きく変わった。お互いに主権を主張する尖閣諸島をめぐり、日中は軍事衝突の危機を迎えた。これまで日中関係の後景にあった軍事安全保障が、日中関係の大きな柱として立ち、深刻な影響を及ぼすようになった。日中それぞれに言い分はあるが、私は、この尖閣問題をめぐる両国の一連の行動は、日中平和友好条約の「全ての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えない」という条項の精神にもとると考えている。対応を間違ったのだ。
その後、日中関係は緊張し、漂い、不安定な状況が続いている。この日中関係の変質は、2008年の共同声明において「戦略的互恵関係」の全面的推進を打ち出した当時から、日中関係と国際情勢が大きく変化したことも影響している。
日中関係に関して言えば、2010年に中国は、当時世界第2位であった日本の経済規模を越え、しかも24年には、日本の4倍へと、さらに差を広げている。世界最大の製造業大国となり、世界をリードする産業分野も少なくない。中国の軍事力も、この15年間で国防予算ベ-スで3倍強となり、日本の防衛予算の4倍強となっている。12年に登場した習近平政権は、自己主張の強い大国外交を推進し、対外援助を増大させ、発言権の強化に努めている。中国の国力の増大とともに、その国際的影響力を顕著に増大させた。

もう1つが、米中関係の悪化である。2008年当時は、米国ブッシュ政権も中国との安定的な協力関係の構築に努力していた。現在は厳しい米中対峙の構造が定着した。トランプ大統領の持つ不確実性はあるが、中国の行動が東アジアの不安定要因とみられているときに、安全保障面での日本の対米依存度は著しく高い。日米関係と日中関係を両立させることは、それだけ難しくなっている。
この日中両国をめぐる与件の変化が、平和、友好、協力関係の構築という大目標の達成に、どの程度、影響を与えるのかを見てみたい。
先ず、日中の経済力、軍事力の格差が、これだけ大きくなると、果たして中国に、そのような日中関係を作る気があるのかという疑問が出てこよう。だが、日本のソフトパワーを含む総合国力は依然として大国の地位にある。今日、中小国であっても大国の意のままに動かすことは難しい。他の大国に付く選択肢があるからである。ましてや日本が、そういう上下関係に置かれることはない。自国と東アジアの平和と発展を考えれば、日本との間に平和、友好、協力の関係を構築することは、中国の利益でもあるのだ。念のために付言しておけば、国交正常化の時点で圧倒的に強い立場にあった日本は、上下関係で中国を扱ったことはない。
そのような日中関係を、米国との関係を損なわずに作っていくことは、相当の技術を要するが、決して不可能なものではない。なぜなら、そのような東アジアの構築は、初めから米国の存在を前提としており、米国の利益にも適切な配慮をしながら進められるからである。東アジアのいかなる枠組みも、米国を排除したものは成り立たない。米中関係と折り合いをつけた東アジアの構築が、日本の目指すべき方向となる。(つづく)

宮本 雄二(みやもと・ゆうじ) 元駐中国大使、宮本アジア研究所代表
1946年、福岡県生まれ。京都大学法学部卒。69年、外務省に入省し、国際連合局軍縮課長、アジア局中国課長、米アトランタ総領事、軍備管理・科学担当審議官(大使)、駐ミャンマー大使、沖縄担当大使などを歴任し、2006~10年まで駐中国大使を務めた。現在は公益財団法人・日中友好会館会長、一般財団法人・日本アジア共同体文化協力機構(JACCCO)理事長も務める。近著に『2035年の中国』(新潮社)など著書多数。



-500x500.jpg)
のグラビア(国立公文書館デジタルアーカイブより)-500x500.jpg)





