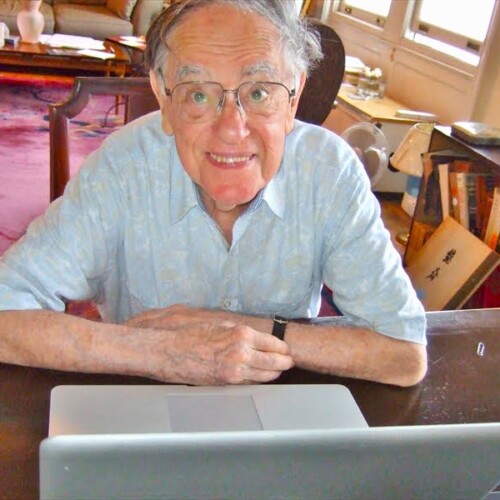「ふてほど」考──がんじがらめの世の中を疑え!
中森 明夫(作家、評論家)

「不適切」というキーワード
暴走する時代に「正気を保つ」──より良い武器とせよ
◇『不適切にもほどがある!』──突きつけられた“常識”の変化
2025年が始まった。政治・社会・文化を含め大きな変動を予感させる年だ。まずは一つの言葉(とドラマ)を導きの糸としてこの国の世相を読み解きたい。
「ふてほど」が昨年の流行語大賞に選ばれた。宮藤官九郎脚本のドラマ『不適切にもほどがある!』の略である。1986年から現代にタイムスリップしてきた中学校教師(阿部サダヲ)が主人公だ。この典型的な昭和の中年オヤジが、令和の常識や価値観とぶつかって騒動を巻き起こすコメディーである。
コンプライアンス、ガバナンス、ハラスメント等、こんにち話題となる言葉たちを、たしかに40年前、1980年代半ばに生きる人々に急にぶつけてもポカンとされるだけだろう。私たちの社会はゆるやかに時間をかけて変化を受け入れてきた。しかし、ドラマ『ふてほど』の主人公のように急に時を超えて、目の前にその現実を突きつけられたら、どうだろう?
たとえば過去の映像、昭和の映画を見ていて、驚くことがある。とにかく人々がよく煙草を吸っている。しかも、電車の中だろうが、職場だろうが、お構いなしだ。みんなスパスパやっている。中年上司が部下の若い女性社員のお尻を触り「××ちゃん、彼氏はいるの?」とかニヤついたりして、ギョッとしたりもする。即座にセクハラ! これは一発アウトだろ、不同意猥褻罪で逮捕されるのでは……とびびってしまう。よくこんな映画、平気で見ていたなあ、と。私たちの常識は時を経て、大きく変化しているのである。
◇「不法」ではなく、「不適切」で大敗した自民党
件のドラマで上手いのは、タイトルの「不適切」という一語だ。これほど現代の問題を核心的にえぐっている言葉もあるまい。たとえば昨年から世を騒がせている「政治とカネ」、裏金問題である。自民党の最大派閥・安倍派に属する多くの議員がパーティー券収入をキックバックして収支報告書に記載しなかった。ところが、ほとんどの裏金議員を検察は嫌疑なしとして放免したのだ。国民の怒りは沸騰して先の衆議院選挙で自民党は大敗、自公は過半数割れ、少数与党に転落する。つまり「不法」ではない、「不適切」によって自民党は大敗したのである。

◇テレビ界から「追放」されたジャニーズ事務所…………
これは政治だけではない。近年、芸能界を揺るがしたジャニーズ問題も同様だろう。ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー喜多川の少年たちに対する性加害が明らかとなった。英国BBC放送のドキュメンタリーによって世界的に告発されたのだ。実に千人単位の被害者がいるものとされ「人類史上最悪の性加害」と指弾もされた。しかし、ジャニー喜多川は既に故人である。民事裁判では彼の性加害の真実相当性が認められたが、刑事上は法に問われることはなかった。やはり「不法」ではなく「不適切」である。それでもジャニーズ事務所は消滅するに至ったのだ。
昨年、芸能界を揺るがした松本人志の件があり、今年は中居正広の件が世を騒がせている。松本はお笑い界のレジェンドだ。中居は国民的アイドルグループ・SMAPの元リーダーである。共にテレビのレギュラー番組を多数持っていた。それがいわゆる「文春砲」を食らって、テレビの世界から完全に消える(だろう)。この衝撃は大きい。両者とも女性とのトラブルが原因だが、これもまた刑事上の法に問われたわけではない。やはり「不適切」によって芸能界の2トップがテレビの世界を追放されたのだ。大きなターニングポイントとなる出来事だろう。
◇SNS、「文春砲」──世論に訴えて「断罪」する意味
ここで考えなければならない問題がある。まず、先の「政治とカネ」の問題だが、本来なら法に問われるべきなのだ。しかし、政治資金規正法がザル法であり、しかも件の法律を作るのが当の政治家なのだから困ったものである。泥棒に警備を任せているようなものだ……との辛辣な批判もある。さらには検察の起訴/不起訴の判断が恣意的で、ことに政治家に対して甘々に見える(これは検察審査会を経ても同様だ)。よって法に問えないがゆえに「不適切」として断罪されるというわけである。

これは芸能界のレジェンドによる性加害疑惑にも言える。昨年7月の刑法改正により、不同意性交罪が導入された。性犯罪における刑事上の基準が、我が国では被害者にとって不利だと言われていた。それを大きく見直す改正である。
とは言え、いまだ被害申告のハードルは高い。警察に訴えても却下されるケースが多いとの声も聞く。そこで芸能人の性加害疑惑の場合、「文春砲」の出番になるという次第である。世論に訴えて断罪する。いわば「不適切」警察の役割を「文春砲」やSNSが担っているというわけだ。
◇法律上の公正性が担保されない“「不適切」警察”の暴走
ここに危うさを感じる。「不適切」警察は本当の警察ではなく、公的機関ではない。つまり法律上の公正性が担保されていないのだ。2021年の東京オリンピックの開会式で音楽を担当する(はずだった)アーティスト・コーネリアスが、過去の雑誌インタビューで少年時代の壮絶なイジメ加害体験を語っていた。それがSNSで堀り起こされ大炎上して、猛抗議に発展、あげくに降板するに至る。さらには演出家やプロデューサーらの解任・降板が相次いだ。
著名人の過去の言動等を探索・批判して、社会的にキャンセル(抹殺)する、いわゆる「キャンセルカルチャー」が西欧で猛威を振るったが、その日本版として先の東京五輪問題は端緒を開いたかの感がある。しかし、法律によらないこの種のキャンセルは、きわめて野蛮な私刑(リンチ)にもなりかねない。

これはX(旧ツイッター)やLINE、YouTubeといったSNSの普及と軌を一にしている。昨年、パワハラ・おねだり問題でテレビのワイドショー等で猛バッシングを浴びて失職した斎藤元彦兵庫県知事が、出直し選挙に出馬、大方の予想を覆して圧勝した。これはSNSのパワーによるもので「テレビはSNSに負けた」とも言われた。たしかに現在のテレビ報道の問題は多数あるだろう。しかし、SNSでばらまかれる不確かな情報、デマや陰謀論の類は比較にならないほどひどいものだ。はたして、こうした事態が加速化して大丈夫なのだろうか?
これは先の法が機能しなくなったがゆえに「不適切」警察が出動する事態とパラレルな現象である。法やマスメディアといったこの国の大枠となる基盤が機能不全に陥っているがゆえに、新興のソーシャルメディアや新たな世論が力を得ているという事態だ。
◇社会規範でがんじがらめの現代 無神経でブラックな慣習がはびこった過去
ドラマ『不適切にもほどがある』の昭和からタイムスリップしてきた中年男は、令和の世の中がコンプライアンスやハラスメントやと様々な社会規範でがんじからめになっているその厳しさに息苦しさを覚え、悲鳴を上げる。しかし、過去の時代に生還を果たした時、それがいかに無神経でブラックな慣習がはびこるひどい社会だったかとも気づいて驚く。そう、ドラマ『ふてほど』は単純な「昔はよかった」という物語ではない。過去にも現在にも良し悪しはある。それを杓子定規な机上の論理や倫理ではなく、肌感覚として我々に思考をうながす極上のエンターテインメントだった。

さらには、こうも考える。人はどうしても現在の感覚が絶対だという意識から逃れられない。だが、未来から見れば、きっとこの現在さえ「不適切にもほどある」時代に違いないのだ。そうした「現在を疑う」感覚の重要性を教えてもくれる。
2025年、大きな社会変動が予想されるこの年に、「不適切」というキーワードは、そうした私たちのバランス感覚を研ぎ澄ますために役立つはずだ。暴走するこの時代に、正気を保つ一つのより良い武器として利用したいものである。

中森 明夫(なかもり・あきお) 作家、評論家
1960年、三重県生まれ。80年代から「新人類の旗手たち」(『朝日ジャーナル』)の一人として活躍し、各種メディアに執筆・出演。「おたく」という語の生みの親となる。小説『アナーキー・イン・ザ・JP』が三島由紀夫賞候補となる。主著に『アイドルにっぽん』『東京トンガリキッズ』『午前32時の能年玲奈』『寂しさの力』『アイドルになりたい!』『青い秋』『TRY48』など多数。近著に『推す力 人生をかけたアイドル論』。エンタメからアイドル、政治、社会、文芸、映画など多彩な視点で世相を切り取ってみせ、11年目を迎えた『毎日新聞』「ニッポンへの発言」も好評連載中。