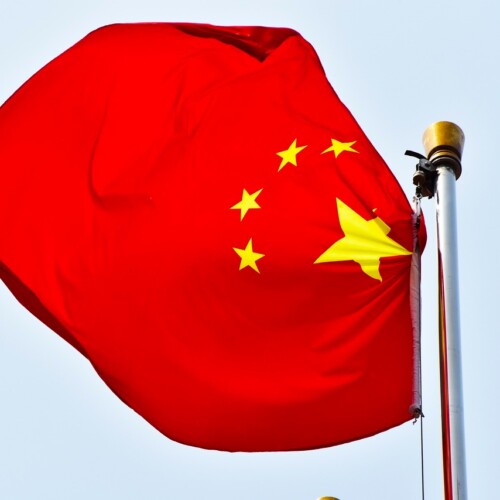シリーズ「戦後80年 日本の変革」
トランプはどこまで世界を壊すのか
渡部 恒雄(笹川平和財団上席フェロー)

安保と経済の世界秩序──
歴史的岐路の日本、自立性高める必要
第二次トランプ政権が成立すれば国際秩序への大きな挑戦になる、というのは、トランプ候補に投票した人たちを除けば、多くの人間が漠然とは警戒していた。しかし、現在、ビデオの早回しのようなスピードと激しさで、第二次世界大戦後に築かれてきた国際秩序を崩壊させている。これまで秩序を支えてきた米国の運転席に破壊者が座ると、予想を超えて破壊が進むという現実を世界は見ている。本稿では、トランプ氏の狙いとそれがもたらす結果を想像し、日本がどのような戦略をとるべきかを考える。
◇国連ウクライナ決議、米が反対票の衝撃
トランプ氏が国際秩序を守る立場を放棄し、むしろ破壊者側に立って世界に衝撃を与えたものが、2月24日の国連総会の米国の投票だった。その日、ロシアのウクライナ侵攻から満3年となるため、国連は特別会合を開き、欧州諸国がロシアの侵略を非難し、ウクライナの領土保全を支持する決議案を93カ国の賛成多数で採択した。この採決で、米国は、ロシアなど17カ国とともに反対票を投じた。
関係者の言によれば、米国の投票により、天と地がひっくり返ったような衝撃が、会場にもたらされた。ウクライナ戦争終結のためにロシアへの歩み寄りが必要だったとはいえ、国連憲章や人道に反するロシアのウクライナ戦争を非難する欧州の同盟国の決議を、ロシア側について反対するというトランプ政権の行動は、これまでの第二次世界大戦後の国際秩序の擁護者から米国の立場を離脱させる劇的なものだった。

◇関税賦課は同盟国にこそ厳しいものに
それでも我々日本人にはまだ他人事だった。4月2日、世界中を巻き込む衝撃が走った──。世界すべての国に一律10%の関税と、貿易赤字国への追加関税である。それは米国の貿易赤字額を輸入額で割った数字の半分にするという根拠のない数字であった。同盟国のEU(20%)、日本(24%)、韓国(25%)に「相互関税」を課す決定を下し、ライバルの中国にこそ34%を課したものの、同じライバル国のイラン(10%)ベネズエラ(15%)には同盟国を下回る関税を課した。
この決定を受け、中国などは対抗措置を打ち出し、世界を巻き込む貿易戦争から景気後退を予測する市場は、世界の株価を急落させた。4月4日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は1日の下落幅としては過去3番目の大きさを記録し、4月7日の東京株式市場の日経平均株価も2644円下落し、終値としてはブラックマンデー(1987年10月20日)の翌日の3836円に次ぐ過去3番目に大きい下落幅となった。
4月6日、トランプ大統領は、記者団から質問に対して「何も下落してほしくはないが、何かをなおすために、時には薬が必要だ。私たちは他国からひどい扱いを受けてきた。これを許してきた愚かな政権があったからだ」と述べて自身の関税措置を擁護した。
トランプ大統領が関税政策を武器に外交や経済政策を行うという意図は理解されていた。しかし、トランプ氏に多額の政治資金を提供してきた米ビジネス界に大きな損害をもたらしてまで、世界経済にダメージを与えるような政策は、大方の予想を裏切るものだった。
第二次世界大戦以後、米国は、投資や貿易の自由な活動を担保する国際経済秩序を支えてきた。それにより米国は依然として圧倒的な経済力を持ち、米国の企業も収益を上げてきており、トランプ氏の現状認識とは異なり、現在の米国経済は世界の中でも「一人勝ち」といわれるほどの強い状況にあるからだ。
トランプ氏の「理屈」は、経済のグローバル化により儲けてきた米国の繁栄から取り残されて、苦境にある米国の労働者を豊かにするために、これまで米国の自由貿易にただ乗りしてきた同盟国に厳しい関税をかけ、製造業を米国内に取り戻すというものだ。おそらく、それはかなりの部分、選挙向けの「メッセージ」であり、自身の望む関税策の国内向けの言い訳だろう。
4月4日の『ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)』社説は、トランプ氏が、これまでの関税に加え、医薬品、銅などへの分野別関税の実施に踏み切った場合は、全体の関税は27%になり、1930年の「スムート・ホーリー関税法」施行後の税率を上回り、トランプ氏が考えている以上の打撃を、世界と米国に与えると警告している。スムート・ホーリー法とは、米国が世界恐慌下で国内産業保護のために高関税策をとったが、世界も高関税策をとったことで国際貿易の停滞を招き、世界恐慌をさらに拡大させた法律だ。
◇景気後退、インフレの懸念、中間選挙で逆風も
今後のアメリカ経済にとって最も深刻なのは、景気後退とインフレが同時に起こるスタグフレーションであり、米国経済が1970年代後半のカーター政権から80年代のレーガン政権下で苦しんだ状況を彷彿させる。そうなった場合、少なくとも2026年11月の中間選挙では、共和党議員に逆風が吹くはずだ。
トランプ氏が国際秩序の維持に関心がないことは皆知っていたが、少なくとも自分自身の地位を守り、刑務所の「塀の内側に落ちない」ようにことだけは考えていると思われていた。そうであれば中間選挙で民主党が下院の過半数を取れば、大統領を弾劾できるようになり、選挙民から突き上げられた上院の共和党議員の一部から見放されれば大統領罷免もあり得る。罷免されたトランプ氏に待っているのは、すでに一件の有罪判決がでている4件の刑事訴追だ。トランプ氏はその後、報復措置をとらず交渉を求めている日本などに対して
今回の関税の決定は、経済を理解できないトランプ氏の誤算なのか、今後、大きな妥協策に応じるつもりもあるのか、あるいはミラン大統領経済諮問委員会(CEA)委員長の「マールアラーゴ合意」のような国際経済秩序大転換の戦略構想の一環なのか、こればかりは神のみが知ることだ。
今後は景気悪化とインフレについて、直接、不満を持つ有権者の圧力を受ける共和党議会が、どのように動くのかを注目すべきだろう。そもそも、米国の通商における権限は議会にあり、議会がトランプ氏の無軌道な関税を抑制することも理論的には可能だからだ。
◇「トランプ・ワールド」を理解して交渉せよ
日本が行うべきことは、まずはトランプ氏との交渉ではあるが、抜本的な認識変化の下で交渉する必要がある。それ抜きには、米国に無駄な譲歩を重ねるだけになる。まず「トランプ・ワールド」を理解することだ。同盟国を守ることが米国の利益になるとは考えず、むしろ「負債」となっているという考えだ。だから関税も、むしろ同盟国の日本や韓国、EUなどに多く課せられた。
これは「トランプ・ワールド」では合理性がある。米国は第二次世界大戦後、ソ連・中国および共産主義陣営と戦い勝利するための冷戦体制の中で戦略を作り上げた。それは、統制経済という自由主義経済に比べて効率が悪い経済を持つソ連ブロックに対抗して、自由主義ブロックを作った。
米国はその陣営に入る国家に対しては、安全保障条約を結んで軍事面での援助により味方に付け、同時に米国の市場を開いてマーケットアクセスを担保して経済成長の機会を与えた。さらに共産主義ブロックに参加していた中国を切りくずし、米国の市場へのアクセスを与え経済を成長させ、ソ連に対抗させたことで、ソ連ブロックの経済が行き詰まり、戦うことなくして、ソ連は崩壊した。

実にこの構造を利用して、どん底の敗戦国から経済大国にのし上がったのが、日本とドイツであり、米国に防衛を依存して、経済成長に資源を集中する日本の戦略が、吉田茂首相の名前から「吉田ドクトリン」と呼ばれるようになった。日本の高まった競争力は70年代から90年代にかけて米国経済を脅かすことになり、日米貿易摩擦を経験することになるが、日本はその経験から米国との同盟における日本の役割を拡大し、経済上も安全保障上も、日本以上の手ごわいライバルである中国に対抗する上で重要な意味を持たせることで日米同盟を維持してきた。
◇「吉田ドクトリン」通用せず、自立に向けた歴史的岐路に
おそらくトランプ・ワールドでは「吉田ドクトリン」は通用しない。日本は、経済でも安全保障でも、より自立性を高める必要があり、それは日本の生き残りのためには好機でもある。しかしそれは米国との対抗や決別ではない。依然として中国を警戒する米国との同盟関係を維持しながらも、関税賦課などで一方的な譲歩を強いられかねない安全保障と経済での過度な米国依存を減らしていくことである。
そのためには、日本にはこれまで以上の軍事力と、それを支える最先端の技術が必要となる。中国への対抗もあり、トランプ政権は日本に今以上の防衛費を負担することを要求するとみられるため、日本はそれを交渉条件にして日本経済を守り、新たな防衛予算は将来の経済成長の種となる軍民両用技術への研究開発に投資すべきだ。
今後、「トランプ・ワールド」が続けば、米国が中国とディールをして日本を無視するリスクも排除できないため、日本にとっては自国の軍事力を高め、それを新しい経済成長の糧にする以外に手がないはずだ。

これらの現実は安倍晋三元首相の時代から明らかであったが、トランプ2.0政権がそれを再認識させた。4月2日のトランプ氏の関税演説で「安倍首相はわかっていた」と発言しているが、安倍氏がわかっていたのは、その時点で米国を敵に回すのは得策ではないために、全力でトランプ氏との関係を構築して懐柔し、一方で将来のために日本の自立的な軍事力を整備しようとした、ことだったのだろう。
日本は危機を好機に変える歴史的な岐路に立っている。

渡部 恒雄(わたなべ・つねお) 笹川平和財団上席フェロー
1963年福島県生まれ。88年東北大学歯学部卒業。95年米国ニュースクール大学で政治学修士課程修了。同年、米戦略国際問題研究所(CSIS)に入所し2003年上級研究員。05年帰国し三井物産戦略研究所、09年東京財団を経て16年10月笹川平和財団。2024年4月より現職。外交・安全保障政策、日米関係、米国の政策分析に携わる。著書に『2025年米中逆転』(PHP研究所)、『2021年以後の世界秩序―国際情勢を読む20のアングル』(新潮新書)など。






のグラビア(国立公文書館デジタルアーカイブより)-500x500.jpg)

-500x500.jpg)