シリーズ「戦後80年 日本の変革」
あるべき日中関係を築くために──(下)
宮本 雄二(元駐中国大使、宮本アジア研究所代表)

3月22日には、東京で日中外相会議が行われたほか、日中両国の関係閣僚らが経済協力を議論する「ハイレベル経済対話」も約6年ぶりに開催。未来志向で共通課題の協力推進を確認するとともに、日本において早期の首脳会議実現に向けて調整を加速させることでも一致した。岩屋外相は戦略的互恵関係の推進などに向けた協力推進を呼びかける一方で、尖閣諸島を巡る東シナ海情勢や、中国軍の活発化への懸念を伝えた。王毅外相はトランプ米政権を念頭に「我々は多国間主義と自由貿易を堅持し、より公平で包括的な経済のグローバル化を推進する」と訴えた。
拡大する日中の協同分野──今こそ政治と外交の出番
◇激変する世界の中の日中関係
紆余曲折した日中関係は、2023年、岸田文雄首相と習近平主席との間で2008年の共同声明において打ち出した「戦略的互恵関係」の全面的推進を再確認し、ようやく元の軌道に戻ったように見受けられる。だが新たな諸条件の下で、「戦略的互恵関係」の中身を改めて検討し、そのような関係の構築が本当に可能なのかどうか、じっくりと考える必要がある。そのためには、日中が、果たして同じ目標に向かって協働できる分野があるのかどうかを精査する必要がある。実は、われわれの想定以上に、この分野は拡大している。
第1に、トランプ政権により動揺させられている現行国際秩序を維持するという共通の目標が、より明確な形をとって登場してきた。日本も、そして中国も、現行国際秩序のおかげで経済は発展し、今日の国際的地位を築いたことを考えると、ある意味では当然のことだ。だが、この話をすると、中国はその破壊者ではなかったのか、とびっくりされる方も多いと思う。確かに中国は、西側主導の現行国際秩序に反感を示した時期があるが、その後、それを修正している。中国のいう人類運命共同体とは、現行国際秩序が辿り着くべき姿を示しており、現行国際秩序を破棄して別のものに取り替えるということではない。

ここで生じる問題は、日中は、ともに国連憲章や自由貿易原則の遵守を掲げているが、解釈や適用において見解の違いがあり、しかもかなり大きいという点である。この調整は容易ではないが、同じ船に乗っていることだけは確かだ。
第2に、国際社会の重要な責任ある構成員として、地球温暖化や感染症などの地球的課題にともに取り組むべきは当然である。米国が離脱しただけに、その分、責任はさらに大きくなった。
第3に、東アジアにいかにして平和と安定の仕組みを作るかという共通の課題がある。なぜなら、日中の経済発展は、この地域の平和と安定という環境整備なしには不可能だからだ。しかし後述するように、中国の軍事力の増強と近隣諸国に対する行動が是正されない限り、このような話し合いが実を挙げることは難しい。ここは政治と外交の出番である。
第4に、経済関係は基本的に互恵の関係である。それぞれの経済発展のために相手国経済を最大限に活用するのは理の当然である。ましてや中国社会は急速な勢いで日本と同様の社会に変身している。少子高齢化、老人福祉、子供の教育問題など多くの共通の課題を抱えている。この分野は経済安全保障とは全く関係ない。
世界と東アジアのために、このような分野で協働して行くことこそが、新たな時代における日中戦略的互恵関係の求めるものである。この協働関係の増大が、日中関係の最大の難関となっている安全保障関係の安定化のための環境整備となり得る。さらに言えば、自分たちのためだけではなく、地域と世界のために貢献する具体的な姿と成果を示すことにより、両国社会をさらに近づけることができる。

3.世界と東アジアの平和と発展に貢献する日中関係へ
◇東アジアの安全保障をどうするべきか
現時点の日中間の最大の挑戦は、軍事安全保障面から来る。トランプ第2期政権はわれわれに、安全保障を米国に任せきりにするな、という重大な警告を明確に発した。米国が、唯一の超大国から大国の1つに転換するプロセスの始まりと見るべきであろう。米国の安全保障面でのコミットメントは低下すると言うことだ。日本は自国の防衛力の増強に迫られることになろう。中国は、この機会を捉えて、さらに軍拡を続け、この地域の覇権確立に邁進しても良いが、米国が直ちに白旗を掲げてグアム島まで後退することもない。米国は、中国に屈する気は全くない。従って当分の間は、米国の存在を当てにして対応することに根拠がないわけではない。
しかし、中期的、長期的にどうするのかについて、今すぐ、考える必要がある。それは、東アジアの国々が自分たちの地域の将来を自分で考えるプロセスの始まりでもある。
ここにおいて最大の挑戦は中国から来る。中国が軍事力の増強をスローダウンし、近隣諸国に対する行動を抑制できるかどうかが、最大の課題となる。中国の軍事力増強の最大の理由は台湾問題にある。台湾が中国の軍事侵攻を阻止できる戦争シナリオは1つといえども許さないという覚悟でやっている。そのためには台湾に対し圧倒的な軍事力を持つ必要があると考えている。次に、世界に拡大した経済権益の保護になる。
しかし中国がしっかりと考えるべきは、経済権益を軍事力で確保する列強の行動を、レーニンは「帝国主義」として厳しく指弾している点である。各国の正当な経済権益は、国際協調とルールに基づき、国際社会が担保すべきであって、各国の軍事力に委ねられるべきものではない。最後に米国の軍事力に追いつき追い越すという願望があるかも知れないが、これは止めておいた方が良い。追い越すのは難しいだろうし、中国にとっての負担が大きすぎ、資源の最適配分を著しく損なう。

こう考えてくると、台湾問題がカギとなる。台湾問題は内政問題であり、他国の関与不可、というのが中国の基本的立場だが、ここは主要関心国とともに、内々にもっと知恵を出し合ったらどうか。中国にとり、「1つの中国」の原則が担保され、台湾が独立しなければ、武力行使をする必要もなくなる。台湾の人たちの心を平和裏に掌握することで目標を達成するのが王道であり、武力行使は覇道だ。平和的に問題が解決されるまでの間、台湾が独立しないようにする方途が見つかれば、軍事力増強の最大の要因は消失する。ここに努力を集中するべきである。
東アジアの国々は、この地域に平和と安定をもたらす仕組みの構築についての話し合いを直ちに始めるべきである。その仕組みは、全ての参加国の安全を担保するものでなければならない。セカンド・トラックでも、1.5トラックでも良い。日米中の有識者の参加は、必要にして不可欠である。ドアは開かれており、欧州の有識者の参加はとても役に立つ。何と言っても彼らは経験豊富だ。インドが望めば最初から入ってもらっても良い。ロシアや北朝鮮を排除する必要はなく、状況を見て入れれば良い。危機管理から、信頼醸成措置、軍備管理・軍縮までを含む包括的な対応を検討する場となるであろう。これが、米国のコミットメントが低下していく中で、東アジアの平和と安定を確保する唯一の方途ではないだろうか。
◇日中の信頼関係の強化が急務
このような協働関係を強めることが、世界と東アジアの平和と発展に貢献する日中関係の構築につながる。そのためには必要最低限の信頼関係が不可欠となる。信頼関係が全くなければ、対話は意味をなさないし、協力関係も構築できない。日中の間には、幸いなことに、まだこの程度の信頼関係は存在する。対話を強化し、相互訪問を増大させ、人と人との接触を増やし、その上で、協力し合うことだ。そうすることにより信頼関係はさらに増大する。これは先ず政府レベルでやって欲しい。首脳同士で、相手が嫌がることはできる限りやらないようにし、相手がやってもらいたいと思っていることをできるだけやることに、合意して欲しい。具体的に何をやるか、やらないかは首脳に任せたら良い。こういうことの積み上げで、首脳同士、政府同士の信頼関係は強まる。


最近、中国のシャオミ(Xiaomi)の電気自動車の工場を視察した日本の友人は、その先進性に驚愕したと言っていた。AIや自動運転の分野でも中国の進歩は早い。中国は共産党の統治だが、市場は原始資本主義と言っても良いほどの競争社会である。党が勧める分野はすぐに過当競争となり、激しい競争を生き抜いた企業が、今度は世界を制する。日本企業が中国市場に進出し、学ぶ必要性は増大している。中国も、依然として日本から学ぶ分野は多い。日本の企業進出に対する地方政府の視線は熱い。中国も脱工業化社会を迎え、また少子高齢化社会を迎えている。日中の文化は、やはり近い。中国社会の抱える新たな問題に対する解を、かれらは成熟の度合いを強める日本社会に見出している。
このように、日中が交流を深め、お互いを理解し合い、協力し合う分野は増えている。直接交流を増やすと言うことだ。この意義は大きい。当局が情報を完全に管理する中国において、日本政府が直接、中国国民に日本の実情を伝えることは、今日のSNSの時代であっても、ほぼ難しい。ところが中国人観光客の増大が、私の想像を遙かに超えて、中国社会の対日理解度を急速に高め、直接交流の持つ影響力の大きさを実感させられた。様々な分野での直接交流を増大させ、国民同士の相互信頼を増大させる。そのことが日中関係の真の基礎固めとなるであろう。


宮本 雄二(みやもと・ゆうじ) 元駐中国大使、宮本アジア研究所代表
1946年、福岡県生まれ。京都大学法学部卒。69年、外務省に入省し、国際連合局軍縮課長、アジア局中国課長、米アトランタ総領事、軍備管理・科学担当審議官(大使)、駐ミャンマー大使、沖縄担当大使などを歴任し、2006~10年まで駐中国大使を務めた。現在は公益財団法人・日中友好会館会長、一般財団法人・日本アジア共同体文化協力機構(JACCCO)理事長も務める。近著に『2035年の中国』(新潮社)など著書多数。



-500x500.jpg)
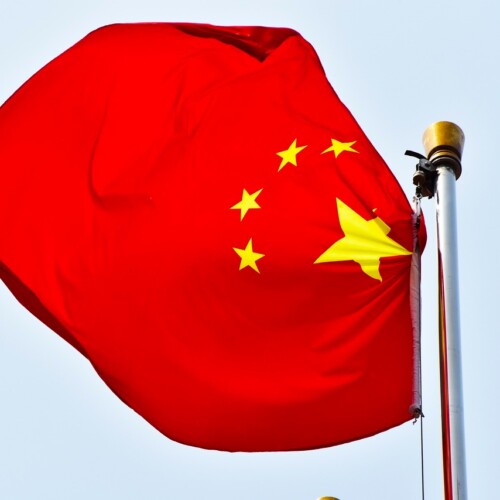



のグラビア(国立公文書館デジタルアーカイブより)-500x500.jpg)

