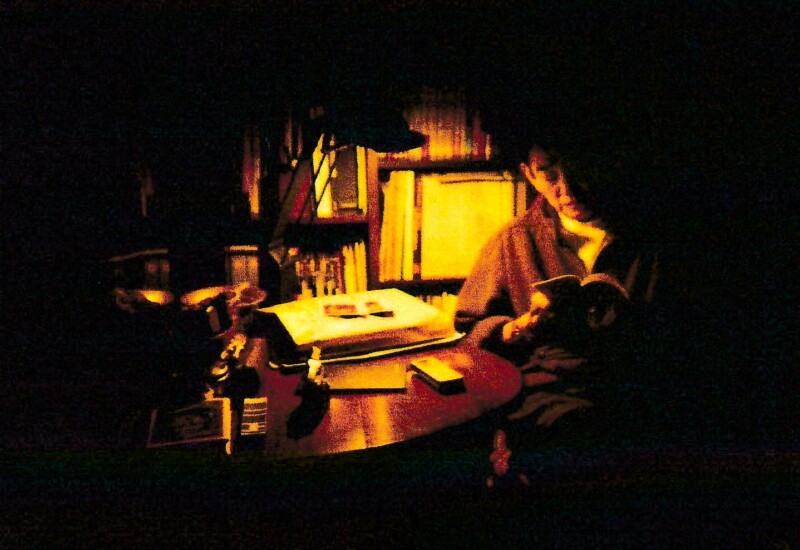石破政権の課題(全2回)
田中秀明(明治大学公共政策大学院教授)

石破首相は、アベノミクスを継承する方針を示しているが、それで日本経済はよくなるだろうか。
第1回 経済政策と地方創生
◇石破新首相への懸念と期待
2024年10月1日、石破茂氏が第102代首相に選出され、石破政権が発足した。5度目の挑戦で自由民主党の総裁になったからであり、念願を果たした。そして、彼は、首相就任後わずか8日後に衆議院を解散し、27日に衆院選投開票が行われることになった。戦後最短である。石破首相は執念でトップの指導者にたどりついたが、その前途は多難である。ここでは、特に彼が重視する経済政策と地方創生に絞って、石破政権の課題を議論する。
◇基盤の弱い首相
石破首相は、就任後早くも野党やメディアから批判に晒されている。総裁選における発言と首相就任後の発言に乖離があるからだ。その典型例が国会審議である。彼は、臨時国会で予算委員会を開いて野党と議論した上で解散すると言っていたが、首相就任後、それを翻し、党首討論にすり替えた。アジア版NATO、金融所得課税なども、同様だ。
国民から見るとがっかりであるが、これは至極当然である。石破首相は、自民党内での権力基盤が弱いからである。彼は、もともと党内では、一匹狼であり、主要派閥に属していなかった。自民党総裁選(決戦投票)では、高市早苗氏に対して比較考量で選ばれた。

政治資金問題で国民の批判が強いなか、早期解散・総選挙を選択した石破首相。国民の審判は10月27日に降る。
メディアによれば、森山裕幹事長など党内有力者から一刻も早い解散が要求され、それに石破首相が従わざるを得なかったそうである。今の自民党にとって最大の課題は、政治資金問題で国民の批判が強いなか、選挙に負けないことである。政策など二の次だ。
そして、これは議院内閣制の仕組みに関係する。首相は大統領のように国民から直接選ばれた指導者ではなく(だから大統領はときに独裁者にもなる)、与党議員の信任に基づいている。第二次世界大戦後に制定された新憲法下では、首相の権限は従来より強化されたものの、自民党55年体制では、首相より与党実力者の方が力を有していた。例えば、税制改正では、首相といえども、自民党税制調査会長の方針に逆らえなかった。
「弱い首相」では、迅速に意思決定できないことから、90年代以降政治行政改革が行われて、首相の権限は制度的に強化された。典型例が、小泉純一郎氏や安倍晋三氏である。しかし、彼らがリーダーシップを発揮できたのは、制度だけではなく、幾度となく選挙に勝ったからである。小泉氏は、党内基盤は弱かったものの、選挙の勝利により党内反対者を抑え、郵政改革などを行うことができた。安倍氏は、派閥による強い党内基盤と選挙での勝利で戦後最長の政権を維持できた。
従って、石破政権の今後の帰趨は、今回の選挙次第である。更に、来年夏には参院選もあり、この2つの選挙で勝たない限り、石破政権の権力基盤は固まらない。石破首相は、岸田文雄前首相と比べて、自ら実現したい政策を有しているが、仮に、公明党と併せて国会の両院で過半数を得たとしても、そうした政策の実現はそれほど簡単ではない。自民党は、関係業界から支援された、いわゆる族議員が多く、構造改革や利害がからむ政策には彼らが反対するからである。最近の典型例が、一般ドライバーが自家用車で旅客を運送するライドシェアである。
日本でも、24年4月から「日本版ライドシェア」が導入されたが、これは諸外国で実施されているものとは似て非なるものだ。タクシー業界が政治家を動員して反対したからである。党内に反対勢力がいる政策を実施するためには、官邸中枢が与党や官僚機構をコントロールする必要があるが、石破官邸にそうした能力を持ったスタッフがいるだろうか。安倍政権では、官邸官僚らがそれを担った。他方、予算の増額や減税などは、与党議員は石破首相を支持する。痛みを伴わないからだ。早速、石破首相は、2024年度補正予算は前年度を上回る13兆円規模にする旨を述べた。従来と同じ規模ありきだ。

諸外国で実施されているものとは似て非なる「日本版ライドシェア」。写真はイメージ
◇アベノミクスの継承で日本はよくなるか
石破首相は、10月4日の所信表明演説で、「デフレ脱却を最優先に実現するため、賃金引上げと投資がけん引する成長型経済を実現する」旨を述べた。これは、アベノミクスの継承であるが、それで日本経済はよくなるだろうか。
第2次安倍政権では、失業率は、2012年の4.3%から2020年の2.8%へ低下した。日経平均は、2012年12月(終値)の10,395円から2020年12月(終値)の27,444円に上昇した。企業収益は改善したが、肝心のGDPは期待外れだった。名目GDP600兆円を目標に掲げたが、2020年度で539兆円だった。2012~20年度(8年間)の年平均名目GDP成長率は0.95%、年平均実質GDP成長率は0.26%であった。異次元金融緩和を続けたが、消費者物価上昇率の目標2%は達成できなかった。世界競争力ランキング(世界経済フォーラムに基づく)で2020年までに3位以内を目標としたが、2019年では第6位だった。世界ビジネス環境ランキング(世界銀行に基づく)で、2020年までに先進国中3位以内を目標としたが、2020年で第18位だった。
他方、度重なる財政出動の結果、国の長期債務残高は、2012年度末の764兆から2020年度末の1,165兆円へと約1.5倍になった(財務省資料に基づく)。対GDP比では、153%から186%への増加である。借金が増えても、経済のパフォーマンスが改善すれば是認できるが、そうとは言えない。

写真は日本銀行。低金利は心地よいが、その継続は「永遠のゼロ成長」である。
アベノミクスの継承とは、金融緩和の継続である。石破首相は、10月2日、植田和男日銀総裁と面会したが、面会後、記者団に「個人的には現在、追加利上げをするような環境にあるとは考えていない」と発言した。これは 株式市場を踏まえた発言かもしれないが、そもそも、日本経済は今やデフレではない。2023年度の平均消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合指数)は2.8%だった。2024年度に入っても、毎月の物価上昇率(対前年同月比)は、3%前後で推移している。なぜ、相変わらずデフレ脱却を掲げるかといえば、財政出動やバラマキの口実が必要だからだ。
日本経済の潜在成長率(その国の経済の実力)は、1980年代の4%から2000年代以降の平均で0.5%程度に低下している。これは、金融政策では引き上げることはできない。技術革新や規制改革などの構造改革が必要であるが、それは痛みを伴う。しかし、それを回避してきたため、日本はゆでカエルになっている。低金利は心地よいが、その継続は「永遠のゼロ成長」だ。
◇「地方創生2.0」で地方は甦るか
自民党総裁選や所信表明演説などで、石破首相が特に強調したのが「地方創生」である。彼は、10年前に初代の地方創生担当大臣だったからだ。「地方創生こそ成長の主役」と位置付け、地方創生交付金を当初予算ベースで倍増することを目指すと述べた。しかし、予算を増やせば、地方の人口減少は止まり、成長が高まるだろうか。
地方創生は、安倍政権において、2014年11月に制定された「まち・ひと・しごと創生法」を基盤として進められ、10年が経過した。その最大の目的は、東京一極集中の是正である。毎年1兆円超の予算が投じられ、様々な施策が講じられたが、東京圏への人口流入は、コロナの影響で減ったことを除けば、この10年間で増加傾向にある(図1参照)。地方創生は、端的に言って、失敗だった。

失敗したのはなぜか。地方創生とは、各自治体が知恵を出して少子化対策や地域振興などに取り組むことを、国が交付金などで支援する枠組みである。地方分権が進められた現在では、国が自治体の事務事業を強制させることはできないので、こうした形を取っているが、事実上は、強制的だ。各自治体は人口ビジョンや中期計画を策定するが、都道府県のほとんどの計画は、出生率を2.00程度に回復することを目標に掲げる。これは、国が「人口1億人の維持」を目標にしており、自治体がこれに貢献するように計画を策定する必要があるからである。日本全体の出生率は、2023年に、過去最低の1.20になっており、これを2.00まで引き上げるのは、全く非現実的だ。仮に、ある自治体で出生率が増加しても、他が減少するだけであり、国は地方にゼロサム・ゲームを強要した。
2050年には、大都市圏などを除く地方の人口はほぼ半減する(国立社会保障・人口問題研究所の2023年推計に基づく)。この推計は、出生率1.36を前提としており、楽観的なので、人口はもっと減るだろう。出生率2.00を目指すような夢物語で計画を策定している限り、人口減少に真剣に取り組むとは思えない。人口の急激な減少下では、あらゆる面で「縮む」しかないのであるが、政治的にはそうした現実を見たくないのだ。

石破政権の目玉政策の一つが「地方創生」だが、予算を増やせば、地方の人口減少は止まり、成長が高まるだろうか。写真はイメージ
◇なぜ東京圏への流入超過を是正できないのか
地方創生が従来の施策と異なる点は、目標達成度を図るKPI(重要成果指標)を導入し、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回すとしていることである。評価できるが、その実態を見ると、機能しているとは言えない。第1期の地方創生は、130ものKPIがあり、しかも、「専門家による伴走コンサルティング支援実施件数」、「支援機関等におけるローカルベンチマークの活用割合」、「プロフェッショナル人材戦略拠点及び株式会社日本人材機構の相談件数」、「全ての小・中学校区に学校と地域が連携・協働する体制を構築」などなど、東京圏への一極集中是正とは直接関係ないものが多い。2018年に、政府は中間整理としてKPIの全体的な達成度を評価しているが、それによると、KPIの約8割は達成している。それほど高い達成率であるにもかかわらず、なぜ東京圏への流入超過を是正できないのか。
東京一極集中是正が妥当な政策か否かについては議論があるが、その原因を分析し、それを解決するような施策が講じられていない。また、これまでの10年間に山のように施策が講じられてきたが、その結果がどうなったのかについての分析もほとんどない(地方自治体も同様)。要するに、PDCAは回っていない。過去10年間のレビューなしに、「地方創生2.0」などと言っても、同じ失敗を繰り返すだけだろう。
◇石破政権に望むこと 徹底したレビューが必要
政府は、頻繁に新しい政策を掲げ、そのスローガンは勇ましいが、過去の政策のレビューは極めて乏しい。その代表例が、政府として最重要な政策文書である「骨太の方針」である。毎年、春頃から、府省や与党議員、業界は、自分たちの政策を骨太の方針に加えるために、奔走するが、6月に出来上がると、それで終わりだ。昨年の骨太の方針に書かれている政策が成功したのか、目標が達成出来なかった場合どうしてなのか、といった分析は全くない。それは、官僚たちには無謬性があり、失敗を認めたくないからだ。2001年に政策評価法が導入されたが、それは報告書の作成が目的となっている。
「地方創生2.0」を掲げるならば、まずは、過去10年間の徹底したレビューが必要だ。それを踏まえて対策を講じない限り、同じ失敗を繰り返す。自治体関係に聞くと、地方創生は国に提出する書類づくりに忙殺されたと不満をもらしている。それでも成果があれば許容できるが、東京一極集中は是正されていない。政権の人気取りで同じことを繰り返すならば、地方はますます疲弊するだろう。
田中 秀明 (たなか・ひであき)
1960年生まれ。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス修士(社会保障政策)、政策研究大学院大学博士(政策研究)。旧大蔵省などを経て現職。主な著作に『高等教育改革の政治経済学:なぜ日本の改革は成功しないのか』(共著、明石書店、2024年)、『「新しい国民皆保険」構想:制度改革・人的投資による経済再生戦略』(慶應義塾大学出版会、2023年)、『官僚たちの冬:霞が関復活の処方箋』(小学館、2019年)、『財政と民主主義:ポピュリズムは債務危機への道か』(共著、日本経済新聞出版、2017年)、『日本の財政:再建の道筋と予算制度』(中央公論新社、2013年)、『財政規律と予算制度改革:なぜ日本は財政再建に失敗しているか』(日本評論社、2011年)など多数。