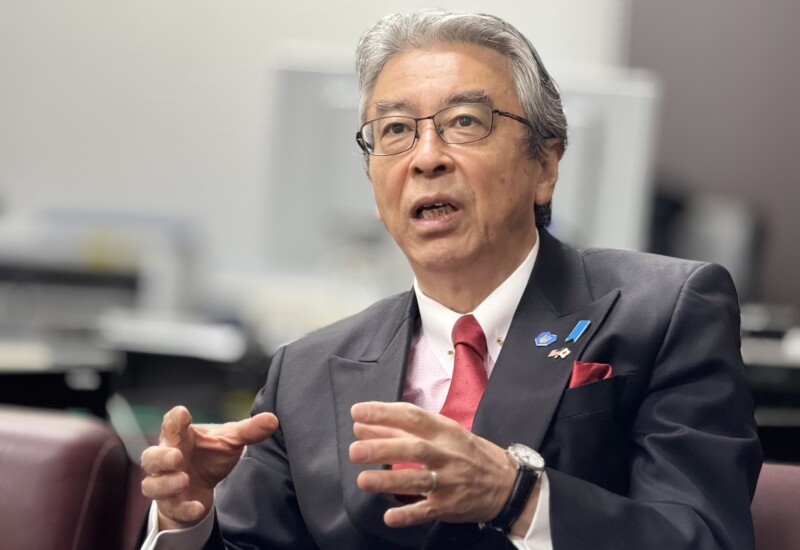難民と日本社会を考える(全2回)
橋本直子・国際基督教大学准教授に聞く

外国出身の人たちにどのように日本社会に溶け込んでもらうかが課題だ。写真は法務省旧本館と本省(背後)
第2回 社会に溶け込んでもらうには
◇「外国人慣れ」していない日本
日本は必ずしも排外主義的な社会とは言えない一方、もともと同質性の高い社会であることの裏返しとして、「外国人慣れ」していないことも確かです。
ただし、政府は労働力としての移民を受け入れる体制に舵を切っています。すでに移民受け入れの是非ではなく、外国出身の人たちにどのように日本社会に溶け込んでもらうかを考え実施せざるを得ないフェーズに来ています。また、世界第4位の経済大国として、国際社会の人道分野で果たすべき役割も大きいことは論を待ちません。
事実上の移民であるか、難民であるかを問わず、近年、在日外国人をめぐる議論は高まっています。その懸念の一つに犯罪率の上昇がありますが、外国人が増えたことで犯罪件数が増えている事実はありません。 その一方、体感治安が悪化しているという感覚を持っている人たちはいるようですが、それにはいわゆる「犯罪」とは別の理由があります。
新興の外国人居住地域の住民に聞いてみると、困りごとの多くは「外国人住民が生活ルールを守らない」というものです。ゴミの出し方、騒音、スピード違反などの運転マナーの悪さなどで、近年、クルド人コミュニティがクローズアップされている川口市などからも、こうした声を聞くことがあります。もちろん、運転マナーなどはともすれば命の危険にもかかわりますが、実はこうした外国人が起こす問題や困りごとは、川口で初めて起きたことではないのです。
例えば群馬や茨城、愛知、静岡など外国人が多く住む地域では、主に90年代からこうした問題が生活上の課題になってきました。そして、外国人コミュニティができて以来、10年単位でこうした課題に向き合って解消してきています。受け入れる側の日本の各自治体は、先行事例に学ぶことで軋轢を解消するヒントを得ることができます。
そしてもう一つ、難民受け入れにもつながる問題ですが、受け入れる際には「まず慣れている地域から始める」ことも重要になるのではないかと考えています。これまで外国人が一人もいなかったような地域で、いきなり大勢受け入れるとなれば、抵抗や摩擦が大きくなるのも無理はありません。これでは、元の住民も、新しくやってきた外国人も、双方が大変な苦労や不満を背負うことになりかねないのです。
確かに出身国や人種、宗教の区別なく日本で暮らしてもらうことが理想ではあります。とはいえ、これだけ同質性の高い日本社会に、見た目も生活様式も全く違う人たちがいきなり入ってくることになれば、当然ハレーションも生じてしまいます。
日本はこれまでにインドシナ難民やミャンマー難民を受け入れた実績があるように、アジア圏からの人々であれば比較的受け入れやすい傾向があるようです。アジア系ですから見た目もそれほど変わりませんし、仏教徒なども多い。「多様性の実現」を目指していきなり高い理想を掲げるよりも、まずはなるべく摩擦の少ないところ・人から受け入れを始めることも、長い目で見れば大事な要素になるのではないでしょうか。
◇日本語教育は必須
そして日本社会になじんでもらうためには、やはり外国人に対する日本語教育は必須です。昨年8月に法務大臣が、日本生まれで学齢期の子供がいる場合には親も在留を許可する、という一回限りの特別措置を発表しましたが、子供は学校で日本語や日本の生活ルールなどを学ぶことができる一方、親にはそうした教育の機会がほとんどありません。日本語教師やNGOなどが手弁当で教育の機会を作ろうと努力していますが、これは政府がより強力な支援策を打ち出すべきでしょう。

日本社会で欠かせない日本語教育。
言語はその社会に溶け込むための一番のツールです。言葉がわからなければルールも文化も理解できません。外国人犯罪の中には「日本では違法だと知らなかった」ために法を犯してしまったというケースもあります。先述の通り、外国人が増えたことで犯罪が増えているという統計はありませんが、凶悪犯罪ではない、軽犯罪や迷惑行為をより防ぐためにも、日本語教育は重要です。
外国人に日本語を教えることを「文化剝奪だ」「同化政策だ」と指摘する人もいますが、そうは思いません。働くにはもちろん、生活をするにも、その国の言語を身に着けることは絶対不可欠です。
男女問わず少なくとも高校までは望めばほぼ誰もが教育を受けることができ、98%という識字率を誇る日本の教育制度は、世界に誇るべきアセット(資産)です。日本に来た移民や難民が日本で教育を受けたのち、日本社会に貢献し、国内外で活躍することも大いにあり得るでしょう。
◇アフガニスタン難民への課題
新著『なぜ難民を受け入れるのか』(岩波新書)のあとがきにも書きましたが、この本の冊子版の印税はアフガニスタン難民一家の女児2名の教育資金として全額寄付することとしています。長年、難民に対する財政的支援を行ってきた日本であれば、こうした支援には抵抗が少ないはずです。
特に、アフガニスタンに関しては、大きな課題が浮き彫りとなりました。2021年8月、アメリカがアフガニスタンから撤退する際に、日本政府は邦人保護に出遅れたうえ、日本のために働いていた現地スタッフを置き去りにしてしまったのです。
現地スタッフは、タリバーンから外国勢力に協力したとみなされれば迫害や拷問の対象とされます。にもかかわらず、日本のために協力した人を保護するという意識や仕組みが、すっぽり抜けてしまっていたためにこうした事態になりました。これでは今後、日本に協力しようという現地協力員は得られません。
◇「日本社会の一員」になってもらうために
「せめて日本のために働いた人を、日本で受け入れられるようにしよう」という仕組みづくりは、普段は人道主義的な問題に関心を持たない、あるいは外国人の受け入れに対して抵抗を持つ保守派の人たちからも、同意を得られるのではないでしょうか。

日本社会にいかに溶け込んでゆくのか。
移民であれ、難民であれ、多くの人たちは日本にやってきて、社会の歯車の一つとして既に役割を果たしています。介護、建設などあらゆる場面で、日本社会は深刻な人手不足に陥っているのが現状です。
日本社会側が移民や難民を迎え入れるにあたって、彼らに「日本社会の一員」になってもらうための仕組みづくりを、少し前のめりでお節介に作っていく。こうした取り組みで、かなりの問題は予防・解消されるのではないかと考えます。
(取材・構成 梶原麻衣子)
橋本直子(はしもと・なおこ)
1975年、東京都生まれ。国際基督教大学准教授。オックスフォード大学強制移住学修士号、ロンドン大学国際人権法修士号、サセックス大学政治学博士号取得。専攻は国際難民法、強制移住学、庇護政策研究。国際組織論。在ニューヨーク国連日本政府代表部人権人道問題担当専門調査員、国際移住機関ジュネーヴ本部人身取引対策課プログラム・オフィサー、国連難民高等弁務官事務所北部スリランカ(ワウニヤ事務所)准法務官、外務省総合外交政策局人権人道課国際人権法・人道法調査員、国際移住機関駐日事務所プログラム・マネージャー、一橋大学大学院社会学研究科准教授などを歴任。現在、(法務省)難民審査参与員などを務める。著書に『難民を知るための基礎知識』(共著,明石書店)、『Migration Policies in Asia』(共編著、Sage)、『なぜ難民を受け入れるのか 人道と国益の交差点』(岩波新書)ほか。