外交裏舞台の人びと
鈴木 美勝(ジャーナリスト)

1969年1月に日米京都会議が開かれた国立京都国際会館
第7回 末次一郎と若泉敬(7)
首相・佐藤栄作の深謀遠慮(上)
1969年、総理大臣・佐藤栄作は自民党総裁3選後初の新年を迎えた。1月13日、首相官邸。「今年は沖縄問題を正面から取り上げて進める年です」――午後3時、離任の挨拶に訪れた駐日米国大使アレクシス・ジョンソンに対して、佐藤はこう切り出した。2年余にわたる日本での職務を終えたジョンソンは、20日に発足するニクソン米政権で国務次官に就任する。外交を所掌する国務省の中枢ポストに起用される知日派の訪問に、佐藤の表情も自ずとほころんだ。自身描く沖縄返還交渉を巡る日程を具体的に示した上で、11月訪米を念頭に「秋頃の適当な時期に自分が行くというタイミングを考えている」と言い切った。
「具体的な解決方法や中身の問題が決まっていない」として戸惑うジョンソンだったが、佐藤は言葉を継いだ。「しかし、スケジュールが決まらないと、逆に中身についても仲々決められない。スケジュールが決まれば、自分の決断のタイミングも決まってくる。いずれにしても、日米貿易経済閣僚会議と愛知・ロジャース会談で交渉をつめられるだけつめて、その上で残った点を自分が大統領との間で片づけるという段取りにしたい」〔註1〕。
◇「攻め」に転じた佐藤と裏舞台外交2人の“主役”
自身の訪米時期を言の葉に乗せてまで退路を断ち「攻めの対米外交」に転じたかに見える佐藤の受け答え。新大統領に就任するリチャード・ニクソンが、68年の大統領選予備選の際に触れた沖縄関連発言を強く意識していたからだろう。「強大な自由国家たる日本の利益は、強力な自由国家たる米国の太平洋における利益である。それ故、ひとたび日本が指導者の役割を果たすことを引き受けるならば、沖縄は必ず返還し得ると思う」(2月22日、ニューハンプシャー州ヒルズボロ)。また、ニクソンは本選挙投票日が迫った10月、朝日新聞の質問に対して67年11月の佐藤・ジョンソン合意に言及、安保上の責任分担拡大を条件にしつつも「67年の会議で作られた基本に立って前進するつもりである」と答えている。〔註2〕
13日の佐藤とジョンソンとの懇談は、2時間にも及んだ。佐藤の日記には「今後のスケジュールや沖縄問題につき懇談、大変うる処があった」とある。が、この時点で、後述する「核抜き・本土並み・72年返還」の実現に向けてどれほどの成算があったのか。まず、佐藤の問題意識は日米の世論にあった。「国内与論の造成が問題。米国内には米国の世論があり、両者の間の世論のギャップをうめる事がむつかしいが、同時に緊要の事である」〔註3〕。また、最難関となる「核」問題の扱い――後には繊維問題が絡んでくるのだが――に関して政官(首相官邸と外務省)にズレがあるのは明白だった。そこには、米国に「核の傘」を差しかけられている日本の安全保障にとって深刻なリスクが潜んでいる。沖縄の祖国復帰を公約に掲げてきた佐藤の大願成就には、このズレを<糊塗>することが不可欠だ。とすれば、外務省・国務省ルートの交渉ではこなし切れない、外交を裏で舞台回しする在野の日本人、国士/憂国の士が必要だった。
一人は、アメリカのオピニオンリーダーたちを巻き込み、戦争で失われた領土の回復のため「核抜き・本土並み・72年返還」に向けて国論統一を策する末次一郎だ。佐藤は末次の凄腕を認知しつつも、信頼感よりも警戒心の方が先に立ち、一方の末次の方も、佐藤との関係がしっくり行っていないことを自覚していた。が、二人の関係は木村俊夫(官房長官、後に官房副長官、外相)と竹下登(官房副長官、後に官房長官)という佐藤側近二人を介して安定的に維持されていた。
もう一人は、後に米最高権力の中枢で外交権を事実上一手に掌握した権謀術数のヘンリー・キッシンジャー(米大統領補佐官)と渡り合うことになる若泉敬であった。その若泉とは、佐藤はジョンソンとの懇談の10日後、首相官邸で会っている。そして、ニクソン大統領の就任式に足を運び、帰国した若泉から、持ち帰ったばかりのワシントン情報を直接インプットされた。〔註4〕
-300x206.jpg)
1967年11月の日米首脳会談の報道(16日付夕刊)
◇佐藤が敷いた対米シフト
67年11月、首相・佐藤は、米大統領リンドン・ジョンソンとの日米首脳共同声明(「両3年以内に復帰の目途をつける」)で沖縄返還への道を開き、期待に胸を膨らませた。ところが、その後、ベトナム反戦運動が米国内外で激化、ジョンソン(民主党、〔註5〕)は68年3月、大統領選への出馬を断念した。その結果、11月に勝利したのは共和党候補のリチャード・ニクソンだった。
米国の政権交代によって、67年の佐藤・ジョンソン共同声明が、本当にそのまま引き継がれるのか否か。沖縄返還を自身の政治的レガシーにしたい首相・佐藤の視線はその一点に注がれていた。「ニクソン勝利」を見極めた佐藤は人事構想を練り上げて、第2次改造内閣を発足させた。外相ポストに愛知揆一を据える一方、内閣の要となる官房長官に保利茂、それを補佐する同副長官には、敢えて官房長官から降格した佐藤側近の木村俊夫を起用する陣容を敷いた。実力者の保利と、小回りが利き末次や若泉とも昵懇の間柄である木村で首相官邸に最強の内閣官房――保利・木村ラインによる「大型官房制」(首相周辺)――を構築すると共に、沖縄問題にとかく慎重な外務省を総覧する外相に腹心の愛知を抜擢した。まさに“人事の佐藤”の真骨頂と言えた。対米外交の新布陣は、沖縄返還を本気で実現しようとする佐藤の決意を感じさせるシフトとなった。
そして、外交の後ろ盾に不可欠な国民世論を盛り上げるパワーを日米双方でテコ入れできる裏方の存在として、末次が必要だった。この稀代のオーガナイザーが裏舞台で縦横無尽に活動できる場は、沖縄返還に伴う施政権や教育制度の在り方を検討する首相の諮問機関「沖縄問題等懇談会」(通称・沖懇、座長・大濱信泉早稲田大学総長〔6〕)、加えてその一環として設置された大濱座長の私的な諮問グループ「沖縄基地問題研究会」(基地研)だった。この「基地研」は、末次が沖縄返還問題での最終合意に向けて、基地の態様に関する具体的な青写真づくりのための知的運動体としてオーガナイズしたものだった。
前回紹介したように2度にわたる訪米で「問題はワシントンではなく日本にあり」と結論づけた末次だが、特に、その組織的機能、位置づけに関して考えを巡らした。「沖懇」の専門委員会では単なる下請け作業になってしまう、「さりとてこれまでのような自由な私的グループという位置づけだけでは、研究、検討の結果を十分に生かせるとの保証が弱い」。このため、①大濱沖懇座長の私的な諮問グループとする②沖縄とのパイプを補強するため、すでに沖懇委員である久住忠男(軍事評論家)を座長役にする――という構想を大濱に提示、同意を得た。この構想には、木村も積極的に支持を与えた。木村については末次の評価も高い。首相を補佐し、佐藤・ジョンソン共同声明後の展望を「真剣に考える立場にあったが、よく問題の本質をつかんでいたし、この研究グループこそが決定的な役割をすることになる」と、末次は予感していた。
基地研のメンバーは久住のほか、林修三(元内閣法制局長官)、永井陽之助(東工大教授)、佐伯喜一(野村総合研究所所長)、衞藤瀋吉(東大教授)、中村菊雄(慶大教授)、高坂正堯(京大助教授)ら14人、もちろん中には若泉も入っており、末次も68年2月から「世話役」として加わっていた。
-300x187.jpg)
日米京都会議-(『追想・末次一郎』から転載)
◇末次主導――「日米京都会議」がつくった流れ
沖縄の祖国復帰への熱は一段と高まった。こうした中、沖縄基地問題研究会が存在感を示したのは、同研究会主催で行われた「沖縄およびアジアに関する京都会議」(通称・日米京都会議)だった。後に末次は、京都会議の意義について回想している。「(沖縄返還問題のような難題は)表からでは駄目。アメリカの政策がつくられる経過を調べると、アジア問題、日本問題の専門家あるいは戦略専門家、そういう学者たちが果たしている役割が非常に大きいから……そういうレベルで公式じゃない立場で率直に意見交換するのは意味があるのじゃないか、そういう所から京都会議は生まれたわけです」〔註7〕
69年1月28日、京都市内の「国立京都国際会館」――。午後2時、実行委員会事務総長の末次が開会を宣言。続いて実行委員長の大濱が挨拶に立った。「この会議は、日米両国の直面している最も緊急な沖縄問題及びアジアの平和と秩序を確保するために、両国はいかに協力すべきかなど、自由な立場で意見交換することが相互理解を深め、ひいてはそれぞれの国の政策決定にも寄与するであろう……」。会議は、武内龍次(前駐米大使)とエドウィン・ライシャワー(前駐日大使)を議長にして始まった。
議題は、①アジアの平和に対する日米の役割、②沖縄の地位――特に施政権返還と沖縄基地、③沖縄返還後の日米関係。討論に参加した米側メンバーは、ライシャワーが事前に作成した候補者リスト60余人の元軍人や安全保障・軍事問題の専門家・学者から厳選された9人、日本側は基地研メンバーを中心に22人、沖縄からは4人だった。〔註8〕
〔米側〕ライシャワー、マックスウェル・テーラー(元統合参謀本部議長)、ロバート・スカラピーノ(カリフォルニア大教授、アジア政治)、ジョセフ・イェーガー(防衛分析研究所)、トーマス・シェリング(ハーバード大教授)、ヘンリー・ローエン(ランド研究所会長)、アルバート・ウォルステッター(シカゴ大教授、核戦略研究家)、アーレイ・バーグ(元海軍作戦部長、ジョージタウン大戦略研究所長)、グレン・オールズ(ニューヨーク州立大教授)
〔日本側〕前述の基地研メンバーに加えて、武内、大来佐武郎(日本経済研究センター理事長)、猪木正道(京大教授)、蝋山道雄(国際文化会館調査室長)、武者小路公秀(上智大学教授)、三輪良雄(元防衛事務次官)、佐薙毅(元航空幕僚長)、中山定義(元海上幕僚長)、天野良英(元陸上幕僚長)ら。
〔沖縄特別代表〕安里源秀(祖国復帰研究会会長)、喜屋武真栄(沖縄教職員会会長、後に参院議員)、久場政彦(琉球大教授)、稲泉薫(琉球銀行調査部長)
激論となったテーマは、第2議題の「沖縄の地位」で予定時間をオーバー、沖縄代表の報告に対し元米軍首脳からの強い異論を含めて議論は白熱、「(日米)双方とも、軍人と学者との意見が分かれるという場面もあった」〔註9〕。1月31日、会議は4日目に入って総括討議が行われたが、最終報告案を巡っても激論になり、「一時は深刻な空気も流れるほどだった」が、「議長報告」という形で会議を総括して閉会した〔註10〕。
2月13日になると、久住、武内ら出席者代表が首相官邸の佐藤を訪ねて会議内容を説明、①沖縄返還後の米軍基地の態様については、事前協議の交換公文を含む安保条約を完全に適用、究極的に「本土並み」にすることに異論はなかった②沖縄に核を配備する必要はほとんどなくなっているとの日本側の主張に、米側の核専門家から反論はなかった③特に沖縄の核体系は他の新たな戦術体系で代替されている④アジアの局地戦では戦術核兵器は効用がない⑤核付返還は一種の核拡散であり、米国として必要なことは核の潜在権を保持することで、米軍としては緊急時に持ちこめれば良い⑥基地の自由使用問題も事前協議の弾力的な運用で十分カバーできる――などと伝えた。 (つづく)
<註>
〔1〕楠田實編著『佐藤政権・二七九七日』(上)
〔2〕ニクソン発言の背景には、高度経済成長期の日本が経済大国として世界的に認知されて来たことがあった。朝日新聞のインタビューに基づく沖縄返還問題に関するニクソンの基本的な立場は、「米外交政策の長期的な取り組み方は、沖縄を究極的に日本に返すことができる、ということでなければならない」「日本がアジアにおいて、相互依存、地域的協力の方向でリーダーシップをとり続けるのに見合って、沖縄返還が可能である」(朝日新聞10月22日付朝刊)というものだった。
〔3〕〔4〕『佐藤榮作日記 第3巻』。1969年6月以降、本格化する佐藤―若泉の裏舞台外交を巡る動きについては、2月配信(第9回「再び密使になった憂国の士」)で取り上げる。
〔5〕第36代米大統領。1961年1月に民主党ケネディ政権の副大統領に就任、63年11月、ケネディ大統領暗殺事件で大統領に昇格、政権を引き継いだ。外交政策ではケネディ政権からのベトナム戦争への軍事介入を拡大させ、国内に激しい反戦運動と世論の分裂をもたらした。
〔6〕1891年生まれ、沖縄県石垣島出身。早稲田大学卒、三井物産に入社。後に戦前戦中は早大で教鞭をとり、英国にも留学。戦後、早大総長に就任。初期の祖国復帰運動では、その「政治的偏向」に疑念を抱き、指導的地位に就くことを拒んだが、1961年に首相(当時、池田勇人)から直接就任要請を受けて南方同胞援護会会長に就任、沖縄祖国復帰、沖縄振興対策に尽力。佐藤政権でも沖縄問題での首相の相談役となった。大局的見地から柔軟な対応ができ、末次との相互信頼の絆は強かった。
〔7〕92年4月14日、琉球放送・具志堅勝也インタビュー
〔8〕〔9〕〔10〕末次一郎『「戦後」への挑戦』
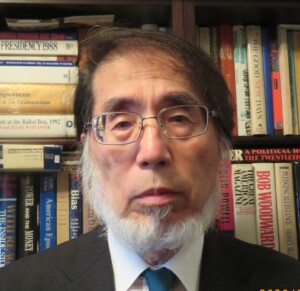
鈴木 美勝(すずき・よしかつ)
ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(以上、ちくま新書・電子書籍)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。




-500x457.jpg)



-500x500.jpg)

