日本の財政破綻と国民生活(全2回)
第1回 私たちの生活はどうなるか
浅井隆(経済ジャーナリスト)

◇破綻国家の国民を襲う悲劇
私が20年以上かけて世界中の破綻国家を取材した結果、各国で一般庶民の生活にどんな影響があったのか、共通項をまとめて2回に分けて話します。財務省や日銀の人に聞いても、国家破綻後の国民の生活が本当にどうなるかはわかっていないし、教えてくれません。私は元々新聞社のカメラマンで現場主義を信条としています。庶民の視点でどんな問題が起きるか具体的に知りたいと考え、破綻後の国家を回って現地取材しました。
結論から言うと、いずれの破綻国家でも、国家の借金を国民が持っている財産で相殺せざるを得なくなり、国民は多くの財産を失っていました。実は日本でも明治維新や敗戦後に同じことが起きていたのです。
国家であっても借金は必ず返済しなければなりません。財政破綻もしくは国家破産とは国の信用が崩壊することで、自動的に金融危機に陥ります。通貨と国債の価値が大幅に下落するからです。日本の場合は日銀が発行する円と財務省が発行する国債の価値が下がります。
◇準ハイパーインフレになる ⇒年10~100%
円の価値が下がる、つまり円安になると日本は輸入大国ですからインフレになります。今年は162円台まで円安が進みました。ハイパーインフレの序曲はもう既に始まっています。
国債の価値が暴落すると、それを保有する銀行など金融機関が大損するだけでなく、いまは日銀が大量に保有していますから、日銀の資産が大きく減損します。財務省も高い金利をつけないと国債が発行できなくなり、ただでさえ借金だらけの政府と日銀はますます身動きが取れなくなります。
国債が暴落すると同時に、金利が上昇します。借金がある人は金利負担が重くなり、社債発行にも高い金利をつけなければならない企業も大きな影響を受けます。国民生活はかなりの混乱状態に陥るでしょう。
国家というのは徴税権で国民から税金を召し上げて成立しています。本来は税収の範囲内で予算を組むべきですが、税金で賄えないほど予算を増やし続けて、とんでもない額の借金をしている異常な状況です。
国家が財源の裏づけとなる財産のない中でお札を刷ると、ハイパーインフレになります。日本が財政破綻した場合、1000%を超えるインフレというのは現実的ではないと思いますが、それでも年10%から100%ぐらいのインフレにはなるでしょう。実際にトルコではいいときで10%、そうでないときは100%のインフレが10年間続きました。いま3%程度のインフレで国民生活は大変だと騒いでいるのに、これが10%になれば大混乱に陥ることは明らかです。賃金の上昇はインフレに絶対に追いつきませんから。
◇実際に訪れた破綻国家たち
私が最初に訪れた破産国家はベトナムでした。いまは違いますが30年ほど前まで国家財政は破綻状態で、アメリカとの戦争の後、中国とも戦争をしてしまったために、政府はくり返し預金封鎖を実施して、国民の財産を取りあげたのです。
当時のベトナムでは「銀行にお金を預ける人はいない」と聞いて驚きました。財政が破綻して国民の資産を何度も奪ったので、誰も銀行を信用しないというのです。国民は銀行に預けずに、通貨のドンもしくは米ドルを麻袋に入れてどこかに隠す、あるいは金(ゴールド)を隠し持っていました。
これで興味がわき、経済危機でIMFに救済された韓国(1997年)を訪れ、さらにソ連崩壊後に破綻状態に陥ったロシアへ3回取材のために行きました。ロシアでは金(ゴールド)が大混乱時に全く使えなかったことに驚かされました。ニセ物が大量に出回ったために誰も金のことを信用しなくなったのです。また預金封鎖が行われた1998年には、銀行の貸金庫の中まで取りあげられたというのです。
ロシアではインフレが年金生活者を直撃し、多数の高齢者が破産して自殺に追い込まれたそうです。品の良いおばあちゃんがスーパーの片隅で物乞いをして「年金生活者でお金がないんです」というので、同情した皆が小銭をあげていたそうです。後になって、最近あのおばあちゃんを見かけないねと話すと、首を吊っていたというケースがたくさんあり、弱者は生きていけないという嘆きを何度も聞きました。
さらにハイパーインフレのトルコ、リーマン・ショック後のギリシャとアイスランド、100兆ジンバブエドルを発行してもインフレを抑えられなかったアフリカのジンバブエも見にいきました。その後も経済が破綻したアルゼンチンとベネズエラを訪れています。
◇強度な資本規制 ⇒預金封鎖、引き出し制限へ移行、海外への送金禁止
政府の借金が返せなくなると、国民の財産と最後は相殺するしかなくなるわけですが、日本でも80年前に徳政令がある日突然断行されています。戦後の昭和21年に実行されたのが預金封鎖でした。いま日本は当時よりもひどい借金を抱えています。敗戦直前の昭和19年でもGDP比204%だったのに、今は250%超ですから、きっかけ次第で同じような預金封鎖があっても不思議ではない状況なのです。
私が一番恐れているシナリオは、南海トラフ巨大地震で大阪湾や名古屋湾に大津波が押し寄せてきたら一発でそうなるかもしれないということです。
預金封鎖は資本規制の一種で、皆さんは財産を動かせなくなります。例えば通帳上では預金が2000万円あっても下ろせません。引き出し制限がかかり、海外送金も絶対にできなくなります。海外に移して逃げようとしても無理です。
預金封鎖をする理由は、国民が預金を引き出せないようにして、その預金と国の借金を相殺するためです。新円に切り替えて、旧円は何月何日までに銀行に入れないと紙切れになると政府が宣言します。そうやって強制的に現金を銀行に入金させて全財産を把握しようというわけです。
いまも心配な人は円や米ドルの現金を自宅でタンス預金にしていますが、持っている旧円は銀行に入れないと紙くずになるので、仕方なく預けることになります。こうして政府は、国民の財産をすべて把握します。不動産は通常でも簡単に把握できますが、タンス預金も預けさせることで預金とあわせた全財産が把握できます。そこで例えば5億の財産を持っていれば60%の財産税を課税して、政府の借金と相殺するのです。
昭和21年の預金封鎖はその後引き出し制限へと変わり、2年半も続きました。その間、預金から下ろせる金額には制限があり、最近破綻した国家もみなそうでしたが、上限は週5万円、月20万が相場です。それが認められる生活費というわけです。
経済危機のギリシャも預金引き出し金額に上限を設定しました。しかしギリシャ国民が一番困ったのはATMでした。銀行窓口は閉まっているのでATMしかありません。ところが普段ならATMにすぐ補充される現金が破綻時にはすぐに補充されないのです。炎天下で並んだ100人のうち、最初の20人分の現金しかATMにはなく、それでその日の営業は終了です。そうなると庶民は午前3時からATMに並ぶしかなくなります。
◇かなりの円安 ⇒200円~ やがて1000円
日本は今年、1ドル160円の円安水準で大騒ぎしました。相場は一度円高に戻っても、来年か再来年には200円を突破し、財政破綻すれば1000円以上の円安になるでしょう。売り惜しみが始まり、値上げが止まらなくなります。するとインフレと円安のダブルパンチで、預金は預けているだけで価値がどんどん目減りしていきます。こうして大不況になるのです。
◇大不況がくる
昭和21年に預金封鎖を実施した後、敗戦から5年間はひどい不況でした。私は以前、松下幸之助の側近だった人から、松下電器が倒産寸前に追い込まれたと聞いています。どん底だった昭和25年正月には「うちの会社も年末までもたへんかもしれんな」と幸之助さんが側近に漏らしたそうです。
この年の6月に朝鮮戦争が始まり、特需で冷え込んだ経済が一挙に回復しますが、それまではトヨタでさえ潰れそうな大不況でした。インフレがひどくなると金利が激しく変動するので、モノが流通しなくなり、製造業はやっていけません。朝鮮戦争がなければトヨタもパナソニック(松下電器)もソニーも潰れていて、戦後復興はかなり遅れたと思います。
私がトルコでインタビューしたブリヂストンの現地法人の社長から、恐ろしい話を聞きました。トルコでは年100%のインフレが続いていましたが、その後3年間ほどやや安定した時期があったそうです。アメリカの資本が入ってトルコリラもやや持ち直し、金利も下がって多くの人が安心した時期があったのです。すると政党間の争いが急に激化して、それを見た大金持ちが現預金を再び海外に移したとの噂が広まって、国民も浮き足立ち、気づけば銀行が封鎖されていたそうです。
その間にリラが1週間で一気に70%も暴落しました。もしその暴落がずっと続いたとすると、1か月が4週ですので835%、1年間は52週なので1.7%を52乗すると年間9千6百億%という信じがたい数字になります。そんな異常な通貨の暴落とインフレがずっと続くことはないでしょうが、人々はパニックに陥り、経済活動が停止することは想像がつくでしょう。
つまり金利が今いくらで、これからどのように変動するか、誰もわからない状況になります。破綻した国では金利が随時変動していくので政府発表もできなくなります。
インフレ率100%のとき、銀行の貸出金利は150%ぐらいになり、一時トルコ経済が安定した3年ほどの時期は40~50%ぐらいだったそうです。それでも日本人には想像もできない金利です。3週間後に営業を再開した銀行では、窓口で金利を掲示しました。お金を借りている人はその金利で返済しなければならないので、一般人も企業経営者も心配で、金利を確認しようと押し寄せたところ、なんと1万5千%と書いてあり、全員が泣き狂ったそうです。貸出金利が1万5千%ということは元本を1年後に150倍にして返せということですから、借りた全員が破産します。
その掲示された金利の額も刻々と書き換えられていったそうです。その現地法人の日本人社長は、「浅井さん、恐慌なんて楽なものです。国家破産というのは恐慌の千倍もひどいことになります。明日どうなるか誰もわからない。私の工場も数か月間閉鎖になり、従業員は全員解雇しました。明日このタイヤの原料がいくらになるのか、いくらで売るのか、為替がどう変わるか誰にもわからないし、給料をいくら払っていいかもわからないので経理処理も一切できません。仕入れも一切できない。これが国家破産の本当の恐ろしさですよ」とおっしゃったとき、日本の戦後のどさくさがどういうものだったか、少しわかった気がしました。
◇治安が悪化する
国家破産状況がずっと続いているアルゼンチンでも、現地に長く住む経営者に話を聞きました。一番ひどいパニックの状況がすぎて、だいぶ落ち着いた時期でも、治安がとても悪いと言っていました。
日本なら絶対に破れないような頑丈な鍵をドアに3つもつけているのに、特殊工具を使って武装した男性が5人も押し込んでくる。強盗に入られたらおしまいで、脅されて全財産を奪われるけれども、それでも警察を呼んではいけない。警察に通報すると、捜索と称して、警察官が家の中のめぼしいものをみんな持っていき、証拠物件と言って返さない。みんなポケットに入れてしまうわけです。
一番ひどい例は、破産した国家では公務員に給与が出なかったり遅配となったりで、しかもハイパーインフレで給与の額面の価値もどんどん目減りするわけです。なんと軍の特殊部隊がお金に困って、訓練と称して金持ちの家に押し込んで、強盗していったそうです。十数年前のアルゼンチンの話です。
日本では今回、円が3年ぐらいかけて100円から160円に安くなっただけで大騒ぎになりました。1週間で70%安くなれば、治安が悪化するのは当たり前です。インフレと通貨安で食べていけない人がたくさん出てくる、しかも銀行からお金をおろすこともできなくなれば、元気な人間は強盗になるしかないわけです。
ロシアで怖かったのが、食べられなくなった一般人の白タクです。客を拾って乗せると、5分後に客か運転手のどちらかが強盗になるそうです。後ろの人がナイフを出して運転手に「カネを出せ」と脅すか、タクシーの運転手が後ろにピストルを向けて「有り金を全部おいて降りろ」という事件が日常茶飯事だったというのです。
また日本の自衛隊では考えにくいですが、当時ロシア軍も給料が出ないため、武器を闇市場に売りました。自動小銃が15万円で、弾丸も込みで20万円あれば買えたそうです。マフィアがそれで武装して、カネを返せない人々を公開処刑にしていたと聞きました。私は本当かなと思いましたが、「公開処刑はよく見ましたよ」という証言を多くのロシア人から聞きました。
日本の敗戦直後には公開処刑はなかったかもしれませんが、治安は実際に相当ひどかったはずです。少なくとも私たちが見るドラマで描かれるような生易しいものではなかったでしょう。
次回は年金・社会保障の大幅カットについて話します。
<第2回 年金・社会保障はどうなる>に続く
浅井 隆 (あさい・たかし)
経済ジャーナリスト。1954年生まれ。早稲田大学政治経済学部中退後、毎日新聞社に入社。1994年に独立。1996年、新しい形態の21世紀型情報商社「第二海援隊」を設立。主な著書に『大不況サバイバル読本』(徳間書店)『ドルの正しい持ち方』(第二海援隊)など多数



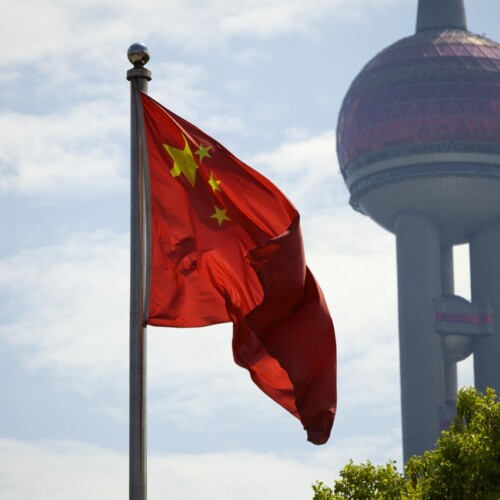





や議員会館など永田町の風景-500x311.jpg)
