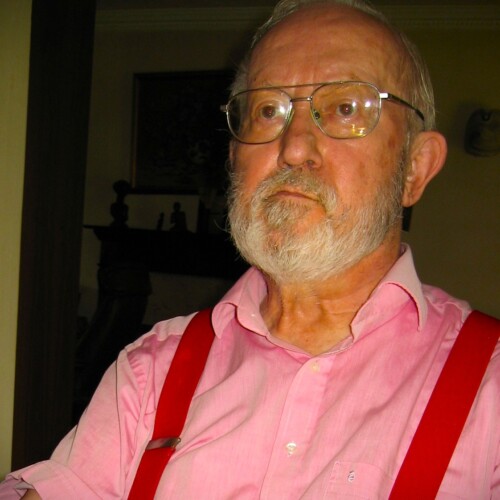「グローバル・アイ」
第7回 西川 恵

カナダと米国 正反対の国造り
カナダのトルドー首相が今年1月6日に自由党党首の辞任を表明し、同20日にトランプ氏が第47代米大統領に就任した。対照的な2人の首脳の去就だ。
トルドー氏は政権をとった2015年から、リベラルで進歩的な、理念色の強い政策を展開してきた。最初の組閣から閣僚を男女同数(各15人)にし、現在まで堅持している。社会問題になっていた子供の貧困にも積極的に取り組み、手厚い給付を行うようになった。先住民に対する過去の政策を謝罪して和解を進め、2021年から毎年9月30日を「真実と和解の日」として祝日にした。嗜好用大麻を合法化し、22年には米国での銃犯罪を教訓に、徹底して厳しい銃規制を導入した。

カナダの国会議事堂(センターブロック)
経済政策でもグローバリズムに信を置き、移民の受け入れもそれまでの年間20万〜30万人から50万人台に増やし、イスラム教徒にも寛容な姿勢をとってきた。ただ移民の増加は住宅価格の高騰や失業率の増加、治安の悪化など社会に緊張を生み、今回の党首辞任に繋がった。
言うまでもなくトランプ氏の政治的立場は正反対だ。反グローバリズム、一国中心主義、移民の制限と不法移民の強制退去、多文化主義への否定的態度……。リベラルなトルドー氏に対しては大統領就任前から敵愾心にも似た態度を示し、国境警備の厳格化を求め、関税の大幅引き上げも言明し、「カナダが米国の51番目の州になればどちらも必要なくなる」と皮肉った。
ただトルドー、トランプ両氏の対照は、二人の政治的立場の違いを超えて、カナダと米国の国造りの本質的な違いを露わにした。以前、カナダ各地を取材し、各界の識者にインタビューしたことがあるが、ある歴史学者の説明にストンと胸に落ちるものがあった。
カナダに最初に欧州から渡ったのは16世紀のフランス人で、大西洋に注ぐセントローレンス川流域に入植した。彼らは先住民にフランス絶対王政の栄華とカトリック文化の素晴らしさを伝え、毛皮貿易に従事した。その後、英国人の入植が続き英仏が衝突。その結果、カナダは英国の支配下に入った。
一方、腐敗した欧州に絶望した英国の清教徒の分離派が17世紀、神の言葉に基づく新世界を築こうとメイフラワー号で渡ったのが今の米国である。彼ら「ピルグリム・ファーザーズ(巡礼始祖)」は米国建国の先達となった。
1783年、英国からの独立戦争に勝利した米国は、カナダ諸州にも独立を呼びかけた。しかしカナダは英王室との関係維持を決めた。その後、何度か米国による支配・併合の危機があったが、跳ね返してきた。英国の自治領を経て、完全な主権国家となったのは1926年である。

風にはためくカナダ、米国の国旗
この歴史家は「カナダは欧州との結びつきを強めることに、米国は欧州と断絶することに国造りの理念を求めた。方向は正反対だ」と指摘した。米国と国境を接しながら、競争や効率一辺倒だけではない寛容の精神がカナダ社会に根付いているのは、その底流に長年の欧州との繋がりで養われた精神があるからだと合点がいった。「カナダは多民族が集まって造られた国。特定の民族が造ったのではない」との認識の下、民族融和と多文化主義は国是となっていて、この点ではリベラルな自由党、右寄りの保守党に違いはない。
10年以上前の保守党政権の時だが、来日した民族問題担当の大臣にインタビューした際、「寛容な社会を維持するためには、ちょっとした社会の緊張も見逃さず、すぐ手を打つことが大切だ」と語ったのが印象深かった。ある私立学校で生徒にキッパ(ユダヤ教徒の帽子)をかぶるのを禁じて騒ぎになった時、政府が間に入って撤回させたという。
カナダでは今春に総選挙が行われ、野党の保守党が政権を握るのはほぼ確実だ。受け入れる移民の数は減るだろうが、それでも30万人台は維持される見込みだ。労働力を維持するためにはこの程度の受け入れは必要なのだ。
これまで外目には米国とカナダは相似形の兄弟のような関係と捉えられていたが、両国の首脳の対照は歴史に根差した国柄の違いをクローズアップした。反グローバリズム、ナショナリズムの強まり、理念の行き過ぎに対する反動という昨今の政治潮流を体現したトランプ政権を隣国にもつカナダは決して居心地はよくないだろう。両国関係の緊張は免れないと思われる。
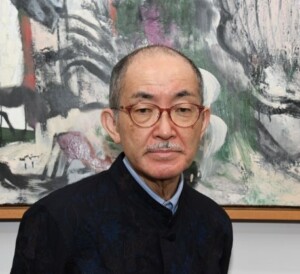
西川 恵(にしかわ・めぐみ) 毎日新聞客員編集委員
1947年生まれ。テヘラン、パリ、ローマの各支局長、外信部長、専門編集委員を歴任。フランス国家功労勲章シュヴァリエ受章。日本交通文化協会常任理事。著書に『エリゼ宮の食卓』(新潮社、サントリー学芸賞)、『知られざる皇室外交』(角川書店)、『国際政治のゼロ年代』(毎日新聞社)など。





-500x489.jpg)


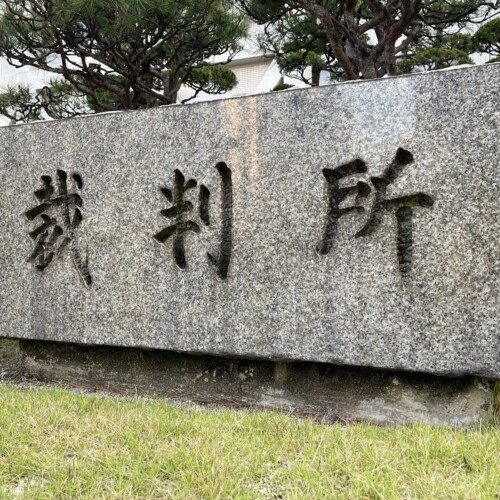
と会食する若泉敬(伊藤隆著『佐々淳行・「テロ」と戦った男」』ビジネス社刊より)-500x500.jpg)