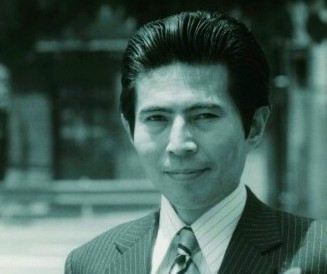一水四見 多角的に世界を見る
小倉孝保

パレスチナ国旗
小倉孝保(毎日新聞論説委員)
第1回 パレスチナの国家承認
ナチスによるホロコースト(ユダヤ人大虐殺)を生き延びた、ハンガリー生まれのユダヤ系米作家、エリ・ビーゼル氏はパレスチナ問題についてこう述べている。
<イスラエル国家とパレスチナ国家が並び、平和に暮らす姿を見たい>
イスラエル寄りの姿勢でたびたび批判を浴びたこのノーベル文学賞作家でさえ、平和のためにはパレスチナ国家の建設が必要だと考えていた。
ビーゼル氏が87年の生涯を閉じて今月で8年になる。世界では今、パレスチナを国家として承認する動きが加速している。
パレスチナ解放機構(PLO)の故アラファト議長が独立を宣言したのは1988年だ。中国やロシアのほか、欧州でも当時ソ連圏にあったブルガリア、ハンガリー、ポーランド、ルーマニアなどが承認に動き、昨年末時点で139カ国が外交関係を持っていた。
そして今年4月から6月にかけ、カリブ海のバハマ、トリニダード・ドバゴ、ジャマイカ、バルバドスの4カ国が順次承認した。
さらにスペイン、アイルランド、ノルウェーの欧州3カ国が5月28日に承認し、パレスチナと外交関係を持つ国は146となった。世界のほぼ4分の3である。
昨年はメキシコ1カ国だけだったのに、今年前半だけで7カ国が承認に動いた。背景には、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区での軍事行動がある。
イスラム組織ハマスによる襲撃を受けて始まった報復作戦は、女性や子どもを含む市民に大きな犠牲を出した。国連を初めとする国際社会は、繰り返し停戦を求めているが、イスラエルのネタニヤフ首相は応じない。そんな中、各国はパレスチナを承認して外交関係を結ぶことで、イスラエルに圧力を掛けようとしている。
アイルランドのハリス首相はネタニヤフ氏に対し、「世界の声に耳を傾け、ガザでの人道的大惨事を止めるよう求める」と強調し、スペインのサンチェス首相は地域の平和のためには、2国家が共存するしか解決策はないと主張した。
こうした動きに距離を置いているのが主要7カ国(G7)である。いずれもパレスチナを国家承認していない。イスラエルの最大の後ろ盾である米国は「2国家共存」による和平の必要性を認めながら、パレスチナの第三者による承認や国際機関加盟には反対の立場だ。その理由について、「永続的平和を実現する唯一の方法は当事者間の直接交渉である」と説明している。
イスラエルが「共存」を求めているなら、その主張も理解できる。ただ、ネタニヤフ氏は「共存」反対を公言したこともあり、当事者間の交渉に無関心だ。この状況を考えると、米国の主張はイスラエルを擁護するための口実でしかない。
ただ、G7内にも変化の兆しはある。米欧の市民はイスラエルに対し抗議の意思を示し、その不満はイスラエルを支援する各国政府にも向いている。
マクロン仏大統領は2月、「パレスチナ国家の承認はタブーではない」と踏み込んだ。英国労働党は総選挙での公約に、「新たな和平交渉に資するべく、パレスチナを国家として承認する」との文言を盛り込んでいる。
国連総会では5月10日、パレスチナの国連加盟を求める決議案が採決され、143カ国の圧倒的多数で可決した。しかし、正式加盟には安全保障理事会での決議が必要で、米国が拒否権を行使している。
日本やフランスは総会決議に賛成した。国連加盟は国家にしか認められていないため、国家承認の用意があることを示唆したとも言える。
焦点は、G7内でどこが最初にパレスチナを承認するかに移っている。日本は欧米と違い、ホロコーストやイスラエル建国に直接関与していない分、外交の幅は広い。
和平を希求する意思を示すだけでなく、グローバルサウスと呼ばれる新興・途上国へのアピールという意味からも、英仏に遅れることなく、パレスチナを国家承認すべきだと思う。
小倉孝保(おぐら・たかやす)
1964年生まれ。毎日新聞カイロ、ニューヨーク、ロンドン特派員、外信部長などを経て現職。小学館ノンフィクション大賞などの受賞歴がある








-500x500.jpg)
と会食する若泉敬(伊藤隆著『佐々淳行・「テロ」と戦った男」』ビジネス社刊より)-500x500.jpg)