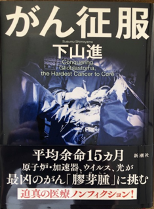メディア・報道の現在 下山進さんに聞く(全2回)
第2回 メディア業界のビッグバン

地ダネ主義を貫く北國新聞の一面
◇生き残りのヒント
――下山さんは1999年に「勝負の分かれ目」でコンピュータ導入による新聞と通信の大変革とそれを支えた人間たちのドラマを、そして2019年の「2050年のメディア」でインターネットのポータルサイト、ヤフーと大手全国紙のニュースの配信争奪をそれぞれ長編のノンフィクションとして描いています。その大きな潮流を克明に捉えてきた下山さんは、この「インターネットによる地殻変動」で、既存のマスコミ、メディアにも金融ビッグバン並みの淘汰の時代が始まっていると言います。
では大変革の中でも生き残れるメディアはどのようなものか。下山さんが「持続可能なメディア」のためのヒントとして紹介してくれたのは、小さくとも将来を築き得る、二つの日本国内の地方メディアの活動でした。
◇一面地ダネ主義
下山 生き残るメディアの例として、ニューヨーク・タイムズや英エコノミストの例をあげると、「下山さん、うちはニューヨーク・タイムズではないし、英エコノミストでもない」と尻込みしてしまう日本のメディアの役員が多かったので、日本の中で、では、持続可能にやっているメディアはどこなのか、を探してみつけたのがこれから紹介する二社です。
一つは石川の県紙、北國新聞です。
北國新聞というと、新聞業界の人たちは、「下山さん、脱北という言葉を知っていますか?」とか「記者に部数拡張のノルマが課せられているだけですよ」と、眉をしかめる。しかし、その人たちによく聞いてみると実際の北國新聞の紙面は読んでいないのです。
北國新聞の部数は震災前で31万部強、人口がほぼ同じ大分県の県紙大分合同新聞が16万部弱の部数だから、いかに北國新聞が「持続可能なメディア」を考える意味で重要なメディアかがわかると思います。
2013年まで紙の新聞の部数を伸ばし続け35万部強、以降はゆるやかに部数を減らしているが、震災前の時点でピーク時から9パーセントしか減らしていませんでした。
同じABC部数でみても、朝日新聞は、ピーク時が2000年の830万部、それがいちばん新しい2024年上半期の数字では約340万部ですから、6割減。地方紙やブロック紙でも約3割の部数を失っている。
「部数拡張のノルマだけで北國新聞が部数を維持できているわけはない」と考え、北國新聞の紙の紙面を2カ月講読しました。
今、テレビの人のみならず、新聞の中の人も、中身を読まずに判断をする人が多くなっていますが、これは、本当におかしいと思っています。左でも右でも、ちゃんと読んで判断をする、それがこの仕事の基本です。
北國新聞の特徴のひとつは、新聞の看板となる一面の記事の扱い方にあります。
私は多くの地方紙も見ていますが、いつも不満に思っていたのが、なぜ共同通信の全国ダネや、国際ダネを歌舞伎の十八番のように一面に持ってくるのか、ということでした。これでは全国紙やNHKと変わらないし、共同の記事はそれぞれの県の読者を意識して書かれたものではないのです。
その一面の記事において、「北國新聞は共同の記事を使うことがほとんどない」ことに気づきました。「一面は徹底的に地ダネでいく。地元石川県は文化と歴史の地だから、お茶や美術の話もバンバン一面に」という姿勢がはっきりしている。共同電が流すような国際ニュースや中央の情報はNHKやNHK NEWS WEBで見ることができる。それを踏まえ「北國新聞でしかできないことに特化していこう」という選択はとても合理的な判断です。
そういうと、うちだって地域の記事を載せている、という地方紙はあるでしょう。しかし、そこに掲載されている記事は、ネットで代替できてしまう、どこで何があった、という記事です。北國新聞で感心をしたのは、地域面に掲載されている記事も、たんなる発表ものをフォローしているのではなく、記者独自の視点のものを大きくとりあげる傾向があったことです。
たとえば2023年3月に掲載された学校のうさぎの飼育数を調べた地域面の記事。うさぎの飼育数が5年で半減したのはなぜか、ということを追っているのですが、これは、教員の働き方改革による労働時間削減との関係を調べて記述している優れた記事でした。
◇孤立を恐れず
――地域への密着と独自の情報コンテンツが、メディア存続の鍵になる。これはテレビなど映像の分野でも共通すると、下山さんが紹介してくれたのが、山陰の鳥取県西部の米子市、境港市、大山町など2市5町1村をカバー範囲とする中海(ちゅうかい)テレビ放送というケーブルテレビ局です。

米子にある中海テレビ放送の調整室 撮影 下山進
下山 中海テレビ放送は、ジャーナリスト志望だった地元の高橋孝之さんや、果物の卸会社を営んでいた秦野一憲さんらが地元の人々や会社が100万円ずつ170口出資して1989年から放送が始まりました。
中海テレビ放送は、開局当初から、独自のニュース専門チャンネル「中海テレビニュース」をもち、鳥取県西部のニュースを流していますが、民放のローカル局や新聞の報道のしかたとはまったく違います。
新聞やNHKの場合、県庁なり警察なりに記者を常駐させ、官僚や警察官のもっている情報をとって、先に書く「前うち」と呼ばれるやりたかたがずっと主流でした。
これは、紙しかなかった時代には、競争力という意味でそれなりの意味があったのでしょうが、いまやヤフーなどのプラットフォームであっという間に追いつかれてしまうニュースです。つまりA社が書いても、B社が書いても、読者にとってはかわりない。
また、この記者クラブ文化というのがやっかいなもので、ようは、横並びの中でのいかに当局の者にとりいるかという競争です。
北國新聞が他社から嫌われているのは、編集局には、編集局以外の人間をいれない、知事への抗議など記者クラブがやろうとしても、参加しない、他社の人間と飲み会をしない、など独自路線でつるもうとしないからとも言えます。
中海テレビ放送の報道部は、記者クラブに記者を常駐させてはいません。
報道部はわずか13名の陣容ですが、世論調査会社の調査によれば、鳥取西部では地元紙を抜き、NHKと並ぶ信頼度をもったニュースチャンネルとなっています。
なぜなのでしょうか?
中海テレビニュースをつくった高橋さんが開局以来、記者に口を酸っぱくして言ってきたことのひとつに、「地元の問題のシーズ(種)をみつけてその解決を提示せよ」ということがありました。

中海テレビ放送は、取材もカメラも原稿書きも一人でこなすビデオジャーナリスト方式。写真の上西真里那記者(現営業部)は、キャスターとして出演もしていた。撮影・下山進
◇国道118号線の死亡事故から
99年に入社したばかりの上田和泉記者(現 報道制作部)が取材した2002年の国道181号線の死亡事故はその典型です。上田記者はその死亡事故の箇所は、前にも死亡事故があったことに思いあたり調べてみると過去5年の間に9件10人の死亡事故が同じ箇所で起こっていることをつきとめます。
その箇所は5年前に拡幅工事が行われていました。地元の人は以前の感覚でそこをわたるのですが、わたりきれずに車に跳ねられていたのです。
それを報道すると住民の間で、鳥取県と警察署に横断歩道と信号をつけてほしいという運動がおこる。それをまた報道する。そして、行政が動いて、実際に横断歩道と信号がつきます。
その渡り初め式まで取材して報道をし、上田記者は「これが課題解決型報道なんだ」と気がつきます。
――社名にもある中海(なかうみ)は、米子と島根県松江市に広がる淡水と海水が混ざる汽水湖で、その浄化のための番組も上田記者がやったんですよね?。
下山 1945年の敗戦直後は海水浴ができた中海も、干拓事業と生活汚水の流入で下水の匂いのするような汚染湖に変貌していました。番組の記者兼リポーター兼キャスターになった上田和泉さんは、2001年からこの中海の汚染問題にとりくみます。
2002年2月、出演者が集まった会議で一つの目標が決まります。それは「10年で泳げる中海にする」でした。
一カ月に一回放送するこの番組「中海物語」で、中海での浄化ボランティアも増え続け、2004年には鳥取・島根両県知事が参加した中海・宍道湖一斉清掃も実現しました。

中海オープンウォータースイム2022 米子市広報から
目標の泳げる中海は、2011年6月の「オープンウォータースイム全国大会」の開催で達成されました。大会は以後毎年開催されています。
中海テレビ放送開局30年になる2019年には「中海物語」の20年の軌跡を1時間番組にまとめます。そしてこの番組はギャラクシー賞の報道活動部門大賞を受賞しています。
◇独自報道が信頼につながる
そしてこうした独自の報道をすることの意味は、地元の人々が「中海テレビの言うことならば間違いがない」という信頼につながっていったことです。そのことが、経営に大きく貢献したのです。
中海テレビ放送は、開局以来2023年度3月期決算までずっと増収を続けてきました。その秘密は、ケーブルテレビの契約料以外に、インターネットのプロバイダー料、2016年の電力自由化以降はじめたChukai電力の料金などの売上が大きく寄与したことでした。
電力自由化までは、米子の住民は中国電力と契約するしかありませんでしたが、そこで払ったお金は広島におちていきます。そこで、地産地消の再生エネルギーをとりいれたChukai電力をおこしたのですが、米子の人々は、地元のための報道をしてきた中海テレビならば信頼できると、契約をしていったということになります。
課金システムに顧客情報をもつ。これがケーブル会社の強みです。それに信頼が加わり、派生する事業を始めたときにスムースに大きくすることができたということになります。
創業時の社長はこんなメモを残しています。
「私は、地域の持続的存続条件は、地域が経済的に自立することだと信じています。そのために我々が何ができるのか」。
これこそが、中海テレビ放送しかできないことを現していると思います。
──まとめるとどういうことになるのでしょうか?
メディアが持続可能になるための条件は以下のふたつです。
1.技術革新に対応しているか?
2.横並びではなく、そこでしかできないことに注力をしているか?
たとえば有料電子版をやったとしても、そこで展開されている中身が、他で読めるような記者クラブ取材のものがメインでは、人はお金を払ってその有料版をとってはくれないでしょう。
この他でやらないことをやる、というのが今の日本のメディアのシステムの中では非常に難しいのです。
記者クラブ以外の世界に目を向けましょう。
出版社やネットのメディアやプラットフォーマーそれらで自由になされている議論に耳を傾け、自分たちにしかできないことを考えてみる。組織がそれができないというのなら、個人でそれを考えて組織を出てみる。
その中で、自分たちにしかできないことをみつけたメディアや個人から、この負のスパイラルから脱していくことができると思います。
(聞き手 長谷川 篤)

持続可能なメディアを語る下山進さん
下山進(しもやま・すすむ)
1993年コロンビア大学ジャーナリズム・スクール国際報道上級課程修了。文藝春秋で長くノンフィクションの編集者を務めた。元上智大新聞学科非常勤講師、慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授。現聖心女子大学現代教養学部非常勤講師。著書に『アメリカ・ジャーナリズム』(丸善、1995年)、『勝負の分かれ目』(KADOKAWA、2002年)、『2050年のメディア』(文藝春秋、2019年)『アルツハイマー征服』(KADOKAWA、2021年)、『2050年のジャーナリスト』(毎日新聞出版、2021年)。最新刊の『がん征服』(新潮社、2024年)でも、「がん」に関して専門家の言い分をそのまま報じるだけの横並び報道のリスクがまた指摘されています。
(下山進さんの最新刊、「がん征服」新潮社)