外交裏舞台の人びと
鈴木美勝(ジャーナリスト)

地球儀を模した若泉敬の墓所からの眺望=福井県鯖江市で鈴木美勝撮影
第4回 末次一郎と若泉敬(4)
◇核の時代・トインビーとの対話 若泉「第三の道」の模索
沖縄返還に伴う核密約を一身に背負った若泉は1996(平成8)年7月、二つの遺書を残して自裁した。その一つには、次のようにあった。通夜、告別式、葬儀などの儀式は行ってはならず、法名不要、祭壇を設置してはならぬ。すべての弔問者の自宅への立ち入りを拒絶し、門外に記帳所を設けて記帳のみ【註1】。香典、供花、供物はすべて辞退すること。ただし弔問者には、遺言執行者の礼状と「感謝寸言」に添えて、『未来を生きる──トインビーとの対話』(文庫版)を渡すこと──と。同著は、若泉が70(昭和45)年6月、英国の歴史哲学者アーノルド・トインビー(1889─1975)をロンドンの自宅に訪ね、1週間にわたって行われた質疑応答の記録。「人間精神の危機が叫ばれ、人間の存在そのものが問われようとしている」(若泉)時代に、人類が直面する基本的な諸問題について、世界的な文明史家の考えを聞き、その思想を体系的にまとめたものだ。
-225x300.jpg)
若泉敬は桜を愛した=山岸豊治氏撮影
時あたかも、日本は奇跡的復興を可能にした高度経済成長期にあって太平楽に酔いしれ、東西冷戦下の米国は自由主義陣営の盟主として沖縄を拠点にベトナム戦争を遂行、ソ連の軍事的威嚇に直面する中国は戦略的自律性を志向して初の原爆実験を実施していた。そして3年後には、その数千倍の威力を有する水爆実験にまで踏み切った。トインビーいわく、70年の世界は16、17世紀のプロテスタント対カトリックの宗教戦争当時に似た「不寛容、敵意、不安、暴力の時代」に戻ってしまった。そして、現代文明の本質を喝破した──現代は、科学と技術が激的に進歩する一方で、倫理・道徳は退歩し、「社会的無秩序」が増大している。人類は、核兵器を使う「狂気の自殺行動」に走るのか、「より小さな悪」として「世界的独裁制」に屈服するのか──。こうした危機的状況にあって若泉ら次世代の人びとが「中間の道」(第三の道)を見い出すよう期待すると。言わば悪魔の択一を迫られる<大情況>の中で行われたトインビーへの問いかけ、そこには、核の時代における日本の安全保障の在り方を模索する若泉の苦悩も色濃く映し出された。
◇1964年の衝撃・中国初の核実験
第二次世界大戦の敗北後初めて、日本の安全保障にとって最も深刻に受け止めなければならない危機──少なくとも若泉の目にはそう映った──が到来した。その国際的事件は、「軽武装経済重視」によって復興を遂げた日本の再生を世界に誇示した1964東京五輪開会式(10月10日)からわずか6日後に起きた。中国における初の核実験である──その結果、中国は世界で米ソ英仏に次ぐ5番目、アジアで初の核保有国になった。
中国は早くから、「覇権主義の核威嚇と核脅威に対抗するため」「独立自主、自力更生、国内立脚」(首相・周恩来)の方針の基に原子力技術の取得を計画していた。その直接のきっかけとなったのは、中ソ関係の悪化だった。
『周恩来伝 一九四九~一九七六 下』によると、中国が核実験の期日としてフォーカスしたのは、好天の日が4日間ある10月、検討の結果、中旬の16日が選ばれた。同著は、米ソ両超大国の核に対抗するために行った初の核実験時の<歓喜>の様子を伝えている。
10月16日早朝、一面に晴れ渡り、雲一つ無い青空が広がった中国西部ロプノール地区(現・新疆ウイグル自治区)──実験基地は緊張と厳粛な雰囲気に包まれていた。その日、予定の時刻に向けてカウントダウンが始まり、午後、ついに「零」が告げられると、「起爆」命令が下った。瞬時にロプノール大砂漠の深部から赤い強烈な閃光が走る。次の瞬間、第二の太陽のごとき巨大な火の玉が空高く舞い上がった。天空と大地が真っ赤に染まる。キノコ雲が上空に向けてもくもくと伸び上がって行く。しばらくして、天地を揺るがすような大音響が一帯を制した。と同時に、実験に携わった人々から大歓声が沸き起こった。「すべての人々は感動を分かち合い、熱い涙を流し、互いに祝福し合った」。午後3時4分、現場を指揮した張愛萍(副総参謀長、国務院国防工業事務室副主任)は青空に高々と立ち上るキノコ雲を眺めながら核実験の成功を確信、周恩来に電話で報告した。
深夜11時、初の核実験に成功したことを伝える新華社の「プレスコミュニケ」と、核兵器に対する中国政府の立場を明らかにした「中華人民共和国政府声明」が発表された。
奇しくも、ほぼ同時刻に相前後して、モスクワから驚くべき一報が北京に届いた。中国側が核の脅威を常々感じていたソ連に政変が起こり、ソ連共産党第一書記のフルシチョフ首相が突如、解任されたのだ。『周恩来伝』には感情の昂ぶりを抑えきれないような筆致で書き綴られている。
<中国の核実験が一挙に成功した日は、まさにフルシチョフ失脚の日(引用者註──実際の発表は10月15日)となった。歴史の絶妙な風刺というべきか。世界のマスコミがこぞって、中国の原爆が爆発し、フルシチョフが失脚したと報じたのも不思議ではない>
中国の核実験実施を、時間の問題と見ていた日本政府の情報機関・内閣調査室は、かねて事前情報の収集に努めていたが、核実験の一報が伝えられるや、今後、日本がとるべき方針について、調査・研究・分析を本格的に着手。12月には最初の報告書「中共の核実験と日本の安全保障」を作成した。その起草を担ったのが、報告書のまとめ役の元幹部・志垣民郎の友人で、助言者だった若泉敬だった。【註2】
中国は翌65年5月14日、早くも2回目の核実験を実施した。若泉が東京大学五月祭で「『日本の安全保障』──中共の核武装とその影響」と題して講演したのは、その直後のことだった。若泉は若い世代に対して、核の時代における中国の動向に警鐘を鳴らした。
独自に築いた人的ネットワークを通じて収集した国内外のインテリジェンスを基に、若泉は講演の中で、中国核実験・核武装の軍事的・政治的意義を的確に分析している。【註3】
そして、副首相兼外相・陳毅が1963年に日本人記者団に語った言葉を紹介した。
<「我々はどんな犠牲を払っても核武装する(略)中国人民は実のあるスープがすすれなくても、ズボンがはけなくても核武装だけはやってみせる。何故なら、この核時代に於いて中国のような大国がその威信を保つ為には核の裏づけが無くては駄目だし、同時に国防を全うすることは出来ない」>
中国の核武装に関する若泉の基本的な認識は、実戦に使うためではなく、抑止が目的で、外交戦、心理戦の後ろ盾として活用するためというものだった。が、短期的にはともかく、長期的に見れば「非常に深刻な事態」であり、日本はどう対処すべきなのか──若泉は学生に問いかけた。
今後の選択肢として理論的に考えられるのは、次の三択──①日本独自の核武装②非武装・非同盟③現状肯定(米国の核の傘に入り、そろばん片手に「狡猾なナショナリズム」をもっての対米依存)──だが、国際政治のリアリズムからして②は論外。③については、このままで良いのかと疑問を呈した。実質的ジレンマの中で若泉が当面の選択肢として挙げたのは、中共に対して、日本の国力、少なくとも科学技術水準の優位性・能力を明確に示すことだ。①については、「安易なセンチメンタリズムは安全保障の問題から排除せねばならない」としつつも、被爆国日本は「信念として核武装はしない」。このため、「平和目的」の原子力開発と人工衛星打ち上げを推進し、核武装しようと思えばいつでも可能だという毅然とした態度を、中共に明確に示すべきだと主張した。
これは、2年後に提唱する「核軍縮平和外交」の原型をなす考え方と言える。が、この時点での若泉は、要路の政治指導者に提起するだけの明確な献策を持ち合わせていなかった。
◇1967年──沖縄返還交渉の密使への助走
核拡散が現実の様相を帯びてきた国際情勢の中にあって、若泉が、戦後一貫して末次一郎が追求してきた沖縄返還運動の重要性を強く意識しつつ、核問題に深く通底する現実政治に本格的に関与するようになったのは、1967(昭和42)年だった。
中国による核開発の決意と併せて米ソの「核独占」を許さないとのアジア人からの意思表示に対して、二大超大国はすぐさま反応。核実験の翌65年8月に米国、同9月にソ連が相次いで、核の不拡散を目的とした条約(NPT)の草案を国連・18カ国軍縮委員会に提出した。
若泉は、『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』でその時の心境を綴っている。
<日本としても早晩それに対する基本的態度を決定しなければならない。(略)条約案には日本にとってもいくつかの重要な問題点があったにもかかわらず、世論の関心は概して薄いように見受けられる>
若泉は、NPT条約案について、米ソ核超大国をはじめとする既存の核兵器保有国の現状を肯定しつつ、その他の国の核武装を阻止するという基本的不平等を内包しているとの問題点を指摘、まず核保有国の核軍縮への努力義務が不可欠だが、併せて問題になるのは、中国とフランスの核保有国がこの条約に反対している点だと強調した。
こうした状況を受けて、1967年になると、若泉は核の時代における安全保障の在り方について、具体的な外交構想を発信すると共に、本格的に政治の要路に働きかける。「理論」と「実践」をいかに結びつけて政策—否、「国策」とするか―行動する国際政治学者・若泉が、以前にも増して強く意識し始める、自身に課した<使命感>となった。以下、若泉は精力的に学者としての活動をこなす一方で、<裏舞台外交>を活発化させていく。

若泉が出席した毎日新聞1967年元日付特集紙面「日本の外交に国民の総意を」
1月=毎日新聞元日付朝刊の新年企画・大型座談会「日本の外交に国民の総意を」で、永井陽之助(東工大教授)、石川忠雄(慶応大教授)らと外交安保リアリズム論争を展開
2月=「核軍縮平和外交の提唱」(中央公論3月号)/ニューデリーでの国際会議「アジアの平和と安全保障」に出席
3月=佐藤栄作(首相)と「核の話」で懇談(13日)
6月=カナダでの国際会議「核兵器拡散をいかに防止するか」に出席(下旬)するなど、7月にかけて欧米を歴訪
※中国、初の水爆実験実施。核実験としては6度目(6月17日)
7月=佐藤首相と昼食を共にしながら「沖縄など」に関して懇談(26日)
9月=末次一郎と懇談(2日)、戦後一貫して沖縄返還運動をしている経験に基づき様々な知見を得るため、以後、頻繁に会って意見交換するようになる/「下田会議」(日米関係民間会議)に出席/福田赳夫(自民党幹事長)から沖縄問題で正式に協力を要請され、応諾(29日)
※三木武夫(外相)、日米閣僚会議(バージニア州ウィリアムズバーグ、13日~15日)出席に際してラスク(国務長官)、マクナマラ(国防長官)と個別に会談
10月=沖縄の復帰問題研究会の招きで高坂正堯(京大助教授)と共に沖縄訪問(18日~20日)/ハルペリン(国防次官補代理)、ロストウ(大統領特別補佐官)らと沖縄返還問題で協議するため極秘に渡米(下旬)
11月=帰国後、福田に報告(5日)/首相特使として渡米することが決定(8日)/訪米した佐藤の宿泊先ブレアハウスで、ロストウとの極秘の事前協議の結果を報告(13日)/帰国した佐藤と面会(21日)
※佐藤・ジョンソン日米首脳会談──「両三年以内」に沖縄の「施政権返還」の時期について合意する趣旨の日米共同声明(15日)
12月=佐藤の最側近・楠田實(首席秘書官)に極秘裏に呼ばれ(26日)、以後も直接会って、外交安保の諸課題で相談を受ける
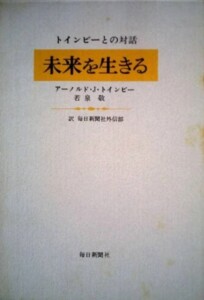
毎日新聞社刊『トインビーとの対話 未来を生きる』(左)
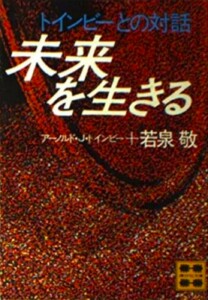
弔問者に配布された講談社文庫『未来を生きる トインビーとの対話』
◇トインビーとの邂逅
1967年は、若泉にとって、核を巡る問題に加えて沖縄返還交渉に本格的に関与するようになった年であるが、忘れてはならないのは、この年を機に時空間の中に形をもつ現象(形而下の世界)を超越し、その背後にある真の本質、根本原理、存在そのものを探求する形而上の諸問題(理性的思惟による思索や超経験的な世界である宗教、神・霊魂など)に強い関心を向けるようになったことだ。そのきっかけとなったのが、20世紀を代表する歴史哲学者トインビーとの邂逅だった。
京都産業大学に職を得て2年余が経過した67年夏、若泉はトインビーを日本に招聘するため、初代総長の荒木俊馬と共に渡英、3カ月後の11月9日、夫妻の訪日を実現させた。日本滞在中、トインビーは京都で二度にわたって講演(16日、18日)。その後、若泉の案内で伊勢神宮に参拝した。関西での日程が終わると、トインビーは首相官邸に佐藤を表敬訪問(30日)、若泉はこれに同道した。前述したように、8月以降の若泉は欧米歴訪、訪沖を含めて殺人的なスケジュールをこなしていたが、来日した夫妻に付き添って誠心誠意きめ細かな心配りに努め、この偉大な歴史哲学者の心をつかんだ。心底、絶大なる信用を勝ち得たのだった。二人の心理的距離は人種、世代差を越えて縮まり、その信頼関係の絆は強固なものとなった。
若泉の遺書に従って弔問客に配布された文庫版『未来を生きる』【註4】の基となった対話は、トインビー来日から2年7カ月後に行われたが、その時にできた信頼が礎になった。
この「対話」は若泉が切望した。政治、経済、社会、安全保障がグローバル規模で揺れ動く危機の中にあって、1960年代後半、大学紛争が全世界に吹き荒れた。新世代の叛乱と受け止めた若泉は、ただならぬ異変を感じ取った。なぜ若い世代は既存の価値観に疑念を抱くようになったのか──その切迫した問いが、トインビーとの「対話」に彼を駆り立てた。ある者たちは現実から逃避し、またある者たちは過激な反体制運動へ走る。単なる世代間断絶と言うより、現代文明に対する強烈な批判、人類史における本質的な問題提起が含まれているのではないか。若泉は、若い世代の人たちと討議を重ねて掬い上げたテーマと設問を整理し、用意周到な準備を行った。
広範多岐にわたる質問はあらかじめ、ロンドンに住むトインビーに送られ、実際には「対話」と言うよりも、若泉が質問するインタビューのような形式で行われた。

毎日新聞に長期連載された若泉による「トインビーとの対話」の第1回紙面(1970年8月24日付朝刊)
「対話」は1970年6月10日から16日までの1週間、毎日3時間ずつ、トインビー邸の応接間で行われた。40歳の若泉の問い一つひとつに、81歳のトインビーは誠実に答えた。いわく、これは<過去から現在に至る人間の問題について、生涯、好奇心を燃やし続けて来た一人のイギリス人が、日本の若い世代のもつ問題を取り上げた一人の日本人に答えようとした試み>だが、同様の質問が世界中で提起されている今日、<日本の若い世代は、世界の若い世代のスポークスマン>なのだ。
<われわれ人類は、いかにして未来を生きるか>──否、<いかにして生き残ることができるか>という命題、そして<宇宙における人間の位置>は……。すべては人生の目的と意義は何かを問うことでもあった。<政治および経済の問題は、究極まで探究するならば、倫理的かつ精神的諸問題>なのだ。「対話」のテーマは八つ──「今日の生きがい」「生と死」「愛と性」「学問と教育」「現代の課題」「未来の展望」「世界国家への道」「若い世代への期待」、質問は65項目に及んだ。核拡散が進行する現代においても、<われわれは、底流にある本質的な問題に直面せざるをえない>と指摘している。
◇トインビーの遺言
世界文明の考察を生業とする偉大な歴史哲学者の一言ひと言は、国際政治学者に<新しい世界に至る道への燭光>をもたらした。この「対話」の時間は、沖縄返還交渉で極度に緊張を強いられてきた密使・若泉にとって、なお続く<裏舞台外交>の狭間に生じた夢のような1週間であったようだ。
若泉に形而上の諸課題に関して思索を深めるきっかけをつくってくれたトインビーは5年後の1975年10月、秋色に染まったロンドンで不帰の人となった。
トインビーは、「対話」の「死を迎える心」の中で吐露している。<私の友人のおよそ半数が第一次世界大戦で殺された>1915年~16年以来、今日に至るまで<戦いに死んだこの友人たちのことが絶えず念頭を離れず、それ以後、私の人生は、毎年が“余生”なのだ。(略)したがって、他の人々に価値があるだろうと考えるものを、私独自の仕事を通じて生み出し続けることにより、この余生を意義あるものにしなければならないというさし迫った使命感>を持ち続けてきた。あとは<私が死ななければならない>という<自然の計画>に殉ずるのみ。<この世で果てしなく生き続ける必要がないことをうれしく思います>と結んでいた。
また、トインビーは、「世を去るにあたって」「自己をふるいおとして」と題した二編の詩を創作して、若い世代に贈った。
<わたしは人間がますます力強く、ますます無力に、ますます荒々しく、ますます錯乱してゆくのを見てきた。(略)/わたしの死んだ後に何がおこるか気がかりだ。(略)/まもなくわたしは立ち去るだろう。だが後代への関心は残るだろう。(略)/なぜならそれは未来の全世代を包括するからだ。>「世を去るにあたって」
<落日は枝が裸になる前に急いでとりどりの色を木々の上にもえあがらせる。(略)/あすは、やがて憩う大地の色をまとっているだろう。(略)/そしてわたしの肉体もやがて木の葉の道をたどるだろう。つまり、生国の大地へもどるのだ。わたしもまた、かえるだろうが、大地ではない。なぜといってわたしはわたしの肉体ではない。わたしは時空のなかにはいない。(略)/それはもはや「わたし」ではないのだから。知識の代償は分離である。わたしが未知なるものと再び合体した時わたしにはそれがわからないだろう。未知なるものとは過去であり、現在であり、未来にほかならないかからだ。>「自己をふるいおとして」
若泉は、核の時代において日本民族が生き残る「第三の道」を懸命に模索した。が、挫折、自身は「沖縄核密約」によって「背信行為」を犯したという良心の呵責にさいなまれ、自ら命を絶った。遺言に基づいて、弔問者一人ひとりに手渡された『未来を生きる』は、その生き方に敬意を表してやまないトインビーに自身を一体化しようとした境地の表われであろう。(敬称略)
<注記>
【1】鰐渕信一氏によると、実際は若泉邸横の駐車場にテントを張り、受け付けで御弔問の御礼状と『未来を生きる』を渡したが、記帳所は設置されなかった。
【2】「NHKスペシャル」取材班『“核”を求めた日本──被爆国の知られざる真実』
【3】「土曜会会報」第71号昭和40(1965)年6月20日
【4】この「対話」は、70年8月24日付~12月20日付まで計97回にわたって毎日新聞朝刊紙上に連載され、その後、毎日新聞社が『トインビーとの対話 未来を生きる』を刊行(71年4月)。弔問者に配布された講談社文庫版は『未来を生きる トインビーとの対話』として77年5月に出版された。
<参考文献> 金冲及主編『周恩来伝 一九四九~一九七六 下』、『未来を生きる トインビーとの対話』、安藤正士『現代中国年表 1941─2008』、『佐藤栄作日記』、『楠田實日記』
鈴木 美勝(すずき・よしかつ)
ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(以上、ちくま新書・電子書籍)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。
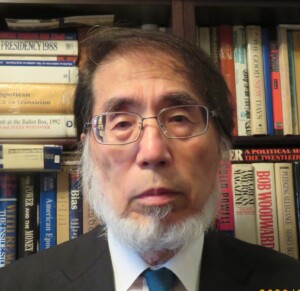





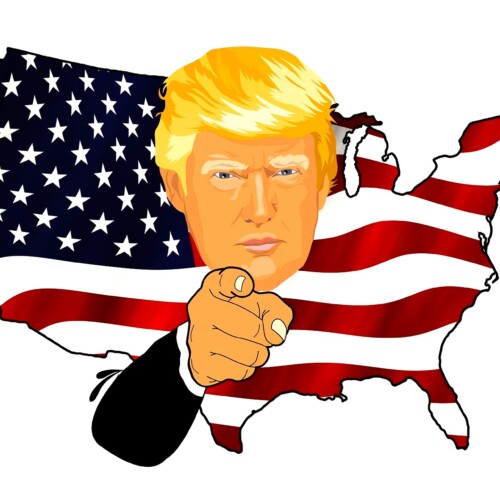



-500x500.jpg)
