「高倉健と戦後日本社会」
~ 温もりと美しさ、愛おしさのものさし
小田貴月 高倉プロモーション代表
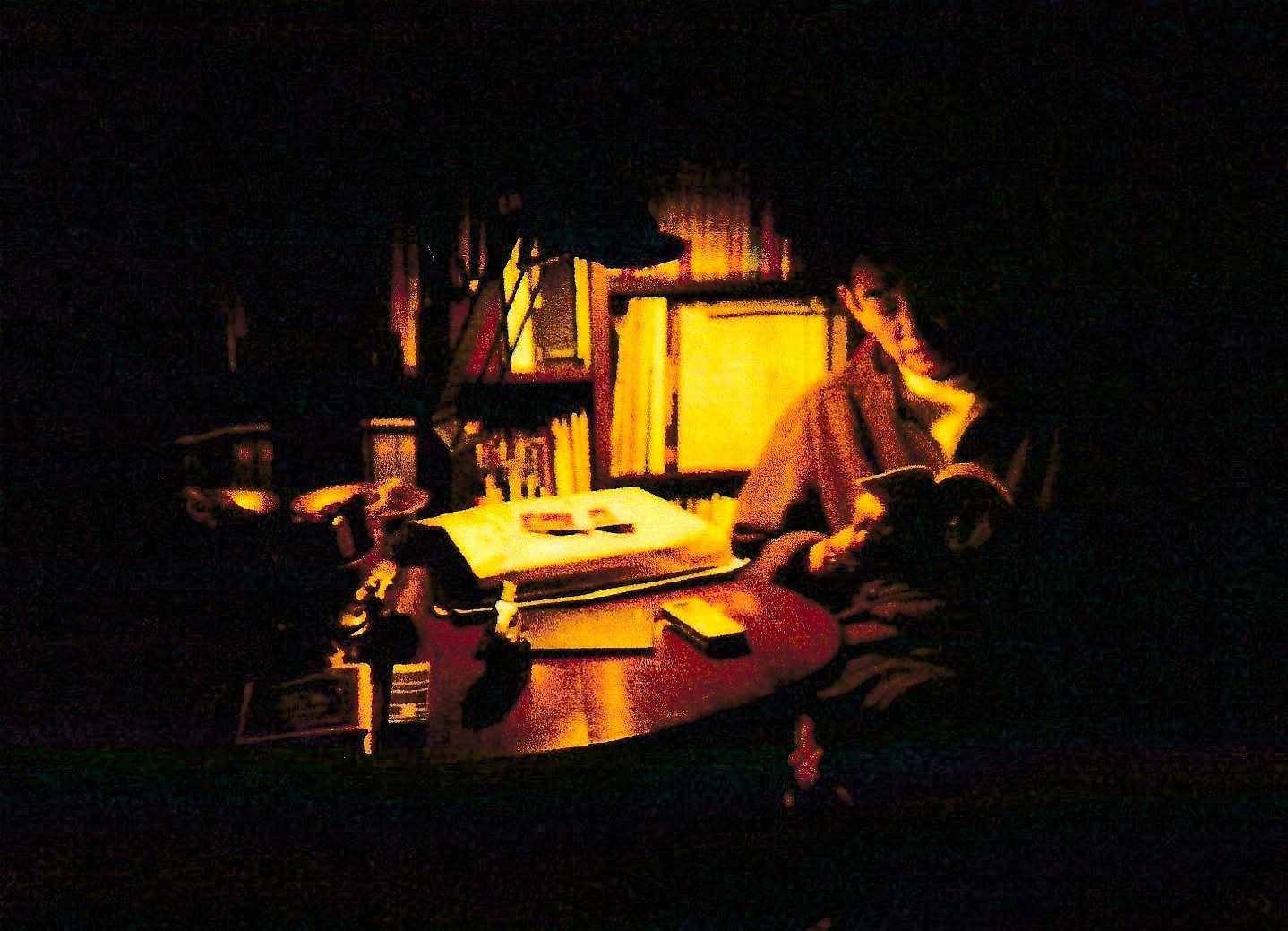
©Takakura Promotion
昭和から平成にかけて生涯で205本の映画に出演した日本映画界の大スター、高倉健が逝って11月10日で満10年を迎えた。『昭和残侠伝』『網走番外地』各シリーズなどの任侠・ヤクザもの路線で一世を風靡。その後も『幸福の黄色いハンカチ』をはじめ、『八甲田山』『君よ憤怒の河を渉れ』『駅 STATION』『海峡』『居酒屋兆治』『南極物語』『ブラック・レイン』『鉄道員(ぽっぽや)』───など人々の記憶に残る名画に出演し、戦後の日本社会・文化に大きな影響を与えた人生であった。17年間にわたって「人間・高倉健」の真の姿を間近で見てきたパートナーで、高倉プロモーション代表取締役の小田貴月さんに寄稿してもらった。
高倉プロモーション 小田貴月
「これに、何か刺繍してくれない?」と高倉。
「何か好きなモティーフがありますか」
「そうだね……、蜂がいいな? 色を注すだけでも、シンプルでいいけどね」
高倉が、新しく買ってきたジャケットや、ロケ先に持っていく布製の小物入れやハンカチに、こだわりのひと手間として望んだのが小さめの刺繍でした。わたくしが出会う前は、アップリケやオリジナルワッペンを、知り合いの縫製士の方に縫い付けていただていたようです。お気に入りのジャケットに施した小さな刺繍を見つけたカフェのスタッフの方から、「高倉様、これは何のマークですか?」って訊かれて、「秘密!って答えたけど、結構みんな目ざといんだね」と、帰宅した高倉が開口一番話してくれたことがありました。お仕着せではなく、身に着けるものひとつにも、自分なりのこだわりや温もりのひと工夫を美しいと感じる人。
それが高倉健という人でした。
-300x225.jpg)
孤高の映画俳優に17年間寄り添ったパートナーが綴った知られざる姿と信念。
晩年、高倉が新聞社から寄稿のご依頼を受けたことがありました。若い世代への提言です。
高倉は、幼き頃、お母様から何度も言い聞かされて育ったふるさとの言葉、“辛抱ばい”をテーマに、心穏やかではいられなかった辛い局面をどんな風に乗り越えたかというエピソードに加え、「戦後の日本は、金をかけたものが心のこもっているものだとみんながどこかでおもいはじめた時から、何かが曲がってきはじめたと思うんですよね」と綴りました。
戦中、戦後を、多感な少年時代に体験した高倉の原体験に基づいた視点です。
昭和6(1931)年2月16日生まれ、本名小田剛一は、福岡県中間市で生まれました。(幼少期、たけいち、たけちゃんと呼ばれていたようですが、自らのパスポートには、GOICHI ODAの自著があるため、剛一の読み方はごういちとさせていただきます)。父は炭鉱の労務管理を取り仕切る仕事、母は学校でお花などを教える職についていて、4人兄妹の次男として育てられました。
小学2年生のとき、肺浸潤(肺結核の初期症状)を患います。肺浸潤は、当時伝染病とされていて、親戚の家の敷地にあった離れでの隔離生活を余儀なくされました。
「お母さんは、とにかく滋養のあるものっていうんで、毎日ウナギを買ってきて自分で捌いて僕に食べさせてくれた。ウナギの血はワインに混ぜて飲まされて、身を炙った煙を吸い込みなさいって。毎日だよ、毎日。大変だったと思うよ。だから、僕は兄妹4人のなかで、自分ばかり面倒かけてお母さんを独り占めしたっていう優越感みたいなものと、他の兄妹への申し訳なさっていうか、心苦しい複雑な想いがあったね」
お母様の看病の甲斐あって、1年の留年を経て、復学。
そして、ほどなく戦争が始まりました。
「食べるものも、着るものも、豊かとは言えない生活だったけど、お母さんは、毎朝卵だけは、4人兄妹それぞれに、どんな風に食べたいか聞いてくれてた。飼っていた鶏の卵を、毎朝取りに行くのが僕の役目。雌鶏が産み落として、お腹の下で温めている卵を『ポーッ、ポッポッポッ』って鶏の鳴きまねしながら、そっと近づいて、安心した隙に卵をすって手を伸ばして獲ってくる。産みたての卵って触ったことある? 温かくて、殻が軟らかいんだ」という少年の日の陽だまりのようなエピソードや、「僕は、病気(肺浸潤)とか、疎開とかで転校生だった。僕は、ランドセルに革靴。転校先の子どもたちは、背嚢っていう布袋にズック。持ち物や見た目からして、全然、違うってだけで、待ち伏せされてよくいじめられた。気心が知れてくると、ここは内緒だぞとかって、それぞれ縄張りがあるらしくて秘密の場所に案内してくれて、これは食べられる。これはだめだとか、木の実の種類なんかいろいろ教えてもらった」
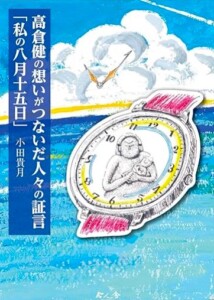
『高倉健の想いがつないだ人々の証言「私の八月十五日」』(今人舎刊)
そして迎えた14歳、昭和20(1945)年8月15日。
「その日、いつもの学徒動員の作業は休みで、近所の池で同級生数人と遊んでいた時、寺の住職の息子がラジオ放送があるらしいといって呼びに来て、寺に駆け付けた。雑音だらけの玉音放送が流れてきて、大人たちが泣いていて。『戦争に負けたらしいばい!』と同級生が言って、終戦を知った。あっ、これからは学校で殴られなくてすむって思って、ほっとした」と話してくれました。
通っていた学校では、戦時中、教練という名のもと、退役軍人から闘いのための体力作りや手旗信号を習うなか、上手くできない生徒がいると、全体責任といって、生徒は一列に並ばされて毎日のように殴られることに、世の中の不条理を感じないわけにはいかなかったと。
「終戦って聞いて、同級生と一緒に、生徒たちを毎日殴ってた教官の家に行ってみた。そしたら、藻抜けの殻。きっと終戦の日のこと、知ってたんだなって感じた。通学で使っていた折尾って駅にはMPがずらっと並んでた。カッコイイ。なんだ、こんな国と戦ってたのかって」
終戦を経て、急激な価値観の変化を味わい、何より、流布されている世の常識を鵜呑みにしないことを身に着けたといいます。
高校生になり、始めたパイロット船のデッキを洗うアルバイト。その際、故郷洞海湾を行き交う大型の外国船を眺めながら、「幸せは海の向こうにある」というある種の確信を得て、貿易に携わる仕事への夢を膨らませます。必須となる英語力を高めようと、高校ではECCを創設し、生の英語に触れようと映画館で洋画を観ることに。初めて観たのが『哀愁 Waterloo Bridge』(1940年)でした。
監督はマーヴィン・ルロイ、主演はロバート・テイラーとヴィヴィアン・リー。第一次世界大戦下のロンドン。空襲警報鳴り響く “ウォータールー橋” で出会い、惹かれ合った英国将校とバレエの踊り子の悲恋を描いた作品。「対訳本を買って、映画を何度も観ているうちに台詞もほぼ暗記してね。戦時下での身分の違う二人の恋愛話、高校生でどこまで理解できてたかどうか、はっきり思い出せないけど、この映画ほど繰り返し観たのはなかったね」と、話してくれました。

貿易に携わる仕事への夢を膨らませて大学へ。写真は明大通り
東京の大学、商学部に入学。
「行儀見習いだっていわれて、親父から相撲部に入れられた。四股踏むんじゃなくて、マネージャーね。もう、先輩からこき使われて、言いなり。勉強どころじゃない。大学は、留年せずになんとか卒業できたんだけど、あとで聞いたら英語の成績が良かったんで、かろうじて(卒業を認められた)だったらしい。でも、そのあとの就職がね……。選べる立場じゃないのに、幾つか就職先を紹介されたのに、偉そうに、ベルトコンベア式に組み込まれたくないなんて思って面接にさえ行かなかった。一旦(福岡県)家に戻って、親父の仕事を手伝うことにした。その頃は、親父は炭坑の仕事じゃなくて、線路に敷く砕石(バラスト)を作る会社を興してて……。仕事は、毎日、単調な作業の繰り返し。これ(この仕事)は、違う。自分の一生の仕事じゃないって思えて、耐えられなくなった。1年後くらいだったか、親父の会社の売上金を内緒で持ち出してもう一度上京した。友達のところに居候させてもらいながら、何か具体的にあてがあったわけじゃないけど、自分の力を試せるような就職先がないかって。持って来てた金が、そろそろ底をついてきた頃に紹介されたのが、芸能事務所のマネージャー見習いの話。面接に指定された喫茶店に行ったら、『君、俳優にならないかって』。その喫茶店に偶然居合わせてた、東映の重役から声をかけられた」
こうして、芸能の素養など一切なかった青年が、その容姿を見染められ、東映第二期ニューフェイスとして映画界にスカウトされたのです。昭和30(1955)年のことでした。
その後、養成所での訓練そこそこに『電光空手打ち』で主演デビューするも、苦節9年。代役だった任侠映画、そして『網走番外地』が大ヒット、作品がシリーズ化され “健さん” として愛されるようになりました。その間、結婚、自宅が全焼しホテル暮らしを経て、離婚。転機は、東映を退社した昭和51(1976)年、45歳のとき。
「会社を辞めたら、もうこの仕事では食っていけないかもしれないな。そしたら、何ができるかなって悩んだ。その時は、(離婚して)独り暮らし。東映での最後の映画『神戸国際ギャング』で顎を切ったり歯を折ったり、怪我の治療に専念してたら、徳間(徳間書店・徳間康快)さんに『けんちゃん、けんちゃん、休んでちゃダメだ。どんどん仕事しないと』って発破かけられた。『今度、これをやりたいから(脚)本読んどいて』って渡されたのが、『君よ憤怒の河を渉れ』。『新幹線大爆破』を一緒にやらせていただいてた佐藤純彌監督だから受けることにした。検事の役。それまでの塀の中の役から、今度は外に出た感じ。次は、『八甲田山』と『(幸福の)黄色いハンカチ』のオファーがあって。運が良かったんだ。この2本が、第1回の日本アカデミー賞の主演男優賞(受賞)の対象作品になって。今でも、結局、運だけだったと思ってるよ。それと、大事だったのは、動ける体を維持できてたことかな」
で開催中の「没後10年展-高倉健に、なる。」ポスター-212x300.jpg)
11月28日まで開催中の「没後10年展-高倉健に、なる。」ポスター。出演作のタイトルで横顔を彩っている
独立したのは、純粋に自分で出演作を選びたかったから。固定のマネージャーを置かず、すべての判断は自分で行い、一作ごとに興行的成績のすべてを引き受ける主演という立場から、軸足がぶれることはありませんでした。
高倉が、仕事をする上で、常に心を寄せていた一文のひとつが、昭和58(1983)年に公開された『南極物語』の南極ロケの際、厳しい荷物の重量制限のなかで持ち込みが許されたたった1冊の本、『男としての人生:山本周五郎のヒーローたち』(グラフ社・木村久邇典著)に記されています。
赤線が引かれたページには、
「身についた能の、高い低いはしようがねえ、けれども、低かろうと、高かろうと、精いっぱい力いっぱい、ごまかしのない、嘘いつわりのない仕事をする、おらあ、それだけを守り本尊にしてやって来た」
『ちゃん』(山本周五郎作)より
と書かれていました。
2014(平成26)年11月10日、高倉健は、58年の映画俳優としての人生で205本の作品を残し旅立っていきました。享年83。
2024(令和6)年11月、高倉健は没後10年を迎えました。
現在、読売新聞ビル3階よみうりギャラリー(東京・大手町)において、11月28日(木)まで、没後10年展「高倉健に、なる。」が開催されています。
タイトルの「高倉健に、なる。」には、諸行無常の人生においてもなお、嘘いつわりなく精進を重ねた高倉の思いの強さを込めました。
高倉は、芸事の素養なく、養成所での訓練期間を満了せずデビューに至った自分の初心を常に振り返り、現場主義を貫きました。どんな仕事であっても、常に全力で立ち向かう姿は、高倉とともに仕事をしていただいた方々の目に焼き付いていると伺いました。
「生き方が映る」
晩年のテレビのインタヴューで語った言葉が、自身の生業に対する矜持。
映画は、庶民の暮らしに寄り添う娯楽。役柄のフィルターであり、生きる悲しみの表現者たる俳優は、地に足のついた生活を貫きながら出番を待つ仕事。
で開催中の「没後10年展-高倉健に、なる。」大型パネルより-169x300.jpg)
『鉄道員ぽっぽや』=よみうりギャラリー(東京・大手町の読売新聞ビル3階)で開催中の「没後10年展 高倉健に、なる。」大型パネルより
亡くなる1年前の2013(平成25)年秋、映画俳優として初めて文化勲章受章者となりました。
映画俳優という職業の地位を、自分が少しでも引き上げることができれば、自分を育ててくれたファン、そして日本映画界への恩返しになるはず。
次回作『風に吹かれて』出演への熱い思いを抱きながら、静かに旅立っていきました。
我が往く道は精進にして、忍びて終わり悔いなし
(大乗仏典『大無量寿経』「我行精進 忍終不悔」より。高倉は、天台宗僧侶・酒井雄哉大阿闍梨からこの言葉を授かり、『南極物語』への出演を後押しされたのです。)
合掌
<追記>
高倉健 没後10年企画『高倉健の愛した食卓』文藝春秋より10月8日発売。
「今日のご飯は何?」……俳優という職業を、生涯を通じて全力で駆け抜けた高倉健。俳優人生を支えた日々の家庭料理を再現。少年時代の食の思い出や映画撮影にまつわるエピソードと共に、幸せな食卓の情景を綴る(帯文より)。
小田貴月(おだ・たか)
1964年、東京都生まれ。女優を経て、海外のホテルを紹介する番組のディレクター、プロデューサーに。96年、香港で高倉健さんと出会う。2013年、高倉さんの養女に。現在、高倉プロモーション代表取締役。主な著書に『高倉健、その愛。』『高倉健の美学』『高倉健の想いがつないだ人々の証言「私の八月十五日」』『高倉健、最後の季節。』『金のホテル銀のホテル DO NOT DISTURB』『スウィートルーム』。

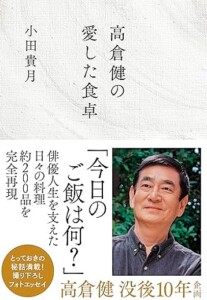




-500x388.jpg)





