全ては中国の都合次第──
日中関係の奇妙な構造は打破できるか
中澤 克二(日本経済新聞 編集委員・論説委員)
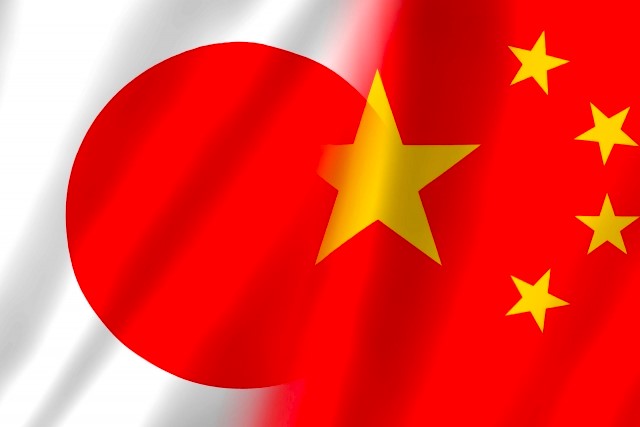
対中関係…日本側主導で大きく動いた例はない
日本にとって中国との関係安定は言うまでもなく極めて重要である。12月25日に初訪中した岩屋毅外相が北京で李強首相、王毅・共産党政治局員兼外相とそれぞれ会談し、戦略的互恵関係に基づく協力促進や閣僚級の「日中ハイレベル経済対話」を開催する方針で一致した。ただ、経済と安全保障の両面で今後、中国とどう向き合っていくのか。それは広い意味で日本の将来、死活をも左右する。
ところが21世紀に入ってからの浮き沈みをみると、ほぼ全てを左右しているのが、中国指導部が政治的に決める対日姿勢だ。中国の政権が日本にどのような態度をとるのかによって全てがすぐに変わってしまう。残念ながら、日本側が主導権をとって対中関係を大きく動かした例はない。
◇日中間の民間交流の効果には限界
日本の民間組織の対中交流も同じである。中国共産党が全てを決める中国の体制下では、厳密な意味での民間は存在しない。指示に従って「民間」も動く。だからこそ、長く対中関係に携わる人々が、様々なイベントで十年一日の「日中友好」を唱えてみても、大状況は変わりようがない。そこに多くの関係者がむなしさを覚えるのである。
この問題を考えるために、まず、中国共産党総書記で国家主席の習近平氏が、その地位に就いた前後からの歴史を振り返りたい。2010年、中国は経済規模で日本を抜き、世界第2位の経済大国になる。当時の中国の雰囲気は活気にあふれ、これから経済、軍事など幅広い分野で世界をリードする大国になるのだという自信に満ちあふれていた。
少し誇張して表現するなら、自分たちは名実ともに大国への道を歩んでおり、経済的に立ち行かなくなった日本の言い分などまともに聞く必要などない、という感覚である。そんな上昇気流の中で新たなトップとして登場してくるのが、 「中華民族の偉大な復興」を掲げる習氏だ。

写真は万里の長城
そして12年9月、沖縄県の尖閣諸島を巡って中国側がいう「大事件」が起きる。日本政府による尖閣諸島の国有化だ。民主党政権下の日本政府が、対中関係の安定化のため、よかれと思って踏み切った措置ともいえる。
だが、中国は逆にこの日本の措置を利用し、日本に「領土問題」で大攻勢をかける。中国各地で官製色がにじむ激しい反日デモが起き、日本企業の店舗打ち壊し、工場焼き打ちにまでつながった。
間もなく習氏は中国共産党と国家のトップになる。日本は民主党政権から自公連立政権に交代し、首相に就いたのは安倍晋三氏だった。日本側では政権交代が起きたのに、習氏の中国は安倍政権を無視し続けた。ようやく習氏が、安倍氏との首脳会談に応じたのは14年11月のことである。安倍政権の成立後、2年近くが過ぎていた。
この「習・安倍会談」は北京で開いたアジア太平洋経済協力会議(APEC)の場を利用したものにすぎない。ホストである中国が、隣国日本のトップと会ってきちんとしたあいさつもしないのではメンツが立たない。そういう中国側の事情があった。
◇2年もかかった「安倍・習」会談とは一変
それから10年が過ぎた今、また同じようなことが起きようとしている。日本との関係を長い間、軽視し、様々な措置で日本に圧力をかけてきた中国が、急速な変化を見せている。
最近の対日圧力の象徴は、23年夏から科学的根拠なしに踏み切った日本産水産物の全面禁輸だ。日本人向け短期ビザ免除措置も長く中断した。

写真は北京の天安門
習体制下での国家安全法制強化を背景にしたビジネスパースン、学術研究者を含む日本人の拘束は極めて深刻な問題だ。かつて中国で活動する日本企業で構成する「中国日本商会」の副会長を務めたアステラス製薬の社員は北京で拘束された後、すでに起訴されている。
日本人学校に通う児童殺傷事件などの真相解明と情報公開は、なお進まない。事件発生には、「日本人学校はスパイ養成機関である」という誤ったSNS情報の拡散と、当局による放置も関係していたとみられている。
これらは全て中国側が厳しい対日姿勢を示す手段として利用している面もあった。中国の国内政治が関係し、一方的に採られた対日措置ともいえる。日本側としては、ただ中国に善処を求めるしかなかった。
ここにきて短期滞在ビザ免除など一部、前向きな動きが出てきた。とはいえ今回も中国側の都合にすぎない。米国では中国に厳しいトランプ政権が25年1月に発足する。明らかになってきた国務長官や貿易・経済政策の担当者らの顔ぶれをみれば、中国は警戒せざるをえない。
中国の経済は長く低迷している。住宅・不動産不況の影響で地方財政は極めて厳しく、消費も振るわない。習氏が対外姿勢を修正せざるをえないのは当然だ。対外的に強く出る「戦狼外交」の雰囲気も少し薄れてきた。
11月15日、ペルーAPECという国際会議の場を利用して35分間にわたる日中首脳会談が実現した。石破茂首相は就任後、初めて会う習氏とほぼ目を合わせず、笑顔も見せない。一方の習氏は、驚くほど柔和な表情を見せた。今から10年前、習氏が当時の首相、安倍氏との初の首脳会談で見せた仏頂面とは大違いだ。
石破自民党は10月衆院選で負けた。だが、対中外交だけを考えれば、石破首相個人は幸運ともいえる。安倍時代の初期は、習氏に会うだけで2年もかかったのだから。今回は首相就任1カ月余りであっさり日中首脳会談が実現した。だが、それはやはり中国側の都合に過ぎない。
防衛政策に長く携わってきた石破氏は、台湾海峡の安定という日本の安全保障にも絡む問題に詳しい。その石破氏は、自民党総裁就任の直前だった8月、あえて台湾を訪問。習氏が名指しで批判している民主進歩党の頼清徳総統、蔡英文前総統らに会っている。
「石破さんの訪台には、総裁選出馬表明前に、反対勢力から張られた『親中派』というありがたくないイメージを払拭する狙いがあった」。日台関係筋はそう指摘する。そして石破氏は訪台中に記者らの前で総裁選出馬を明かした。訪台の効果だったかは不明だが、総裁選決戦投票で、対中強硬派とされる高市早苗氏に勝利した。

自民党総裁選決選投票で、「対中強硬派」とされる高市早苗氏を破った石破茂氏は、「日中の井戸を掘った」田中角栄元首相の事務所出身だ(自民党ユーチューブチャンネルより)
中国側は自民党議員の動きを注視しており、8月の石破氏らの訪台に強く反発していた。しかし、それでも習氏は、首相就任後の石破氏との正式会談に早々と応じた。経緯をつぶさに観察すると極めて興味ぶかい。
中国が経済的に自信があり、勢いに乗っている時には日本の政府や経済界、企業を重視することはない。日本側から勝手にやって来るからである。そして、中国にとって最も重要な対米関係が良好で、先が見通せる場合、中国は日本に対して極めて強く出たり、無視・パッシングしたりする。今、この状況は大きく変わった。
◇中国はグローバルサウス重視で米国けん制
中国の急激な変化は対日本だけではない。習氏はペルーAPECに続いてブラジル・リオデジャネイロで開催した20カ国・地域首脳会議(G20サミット)では、スターマー英首相と会談した。関係が冷え込んでいた中英首脳の会談は6年ぶり。18年に当時のメイ首相が訪中して以来である。
「ニーハオ」。習氏はスターマー氏との冒頭の握手の際、自ら挨拶している。やけに愛想がよい。そして、今回、南米訪問中に会談した計16カ国のトップの多くにも習氏が先に「こんにちは」に当たる挨拶を口にする場面が目立った。
今回で計11回目となるG20参加で習氏は、グローバルサウス重視の姿勢も鮮明にしている。トランプ氏が再び米大統領に戻ってくれば、対中経済政策は厳しくなる。既に表明ずみなのは、中国からのほぼ全ての輸入品に対する10%の追加関税だ。今後も様々な対中圧力が予想される。
中国としては、トランプ対策として成長するグローバルサウスに活路を見いだそうとしている。これと中国国内の需要を組み合わせる「2つの循環」(双循環)を狙っているのだ。一方で日本、韓国といった周辺国、そして英国、欧州連合(EU)各国との距離も見直し始めた。これらは一種の保険でもある。
◇ハイレベル交流探れ
全ては中国の都合による対外的な態度の変化。習氏の対日姿勢の変化もこの文脈の中にある。それでも石破氏は、集権に成功した強いトップである習氏との直接会談で「戦略的互恵関係」を再確認できた。これは重要である。今後は様々なレベルのハイレベル交流を探るべきだ。25年に日本で開催する日中韓3カ国の首脳会談もその一つだ。この枠組みでは、中国からの出席は李強首相になる。
一方、気をつけなければならないのは安全保障面だ。尖閣諸島、東シナ海での対日圧力は続いている。中国とロシア両軍の艦船、航空機が連携して日本周辺で活動するのは常態化している。安保上の対日姿勢は簡単には変わらない。今後も慎重に見極めなければならないのは、習氏をトップとする中国が何を最も重視するのかだ。現時点では、米トランプ政権の出方と、それが中国経済に与える影響だろう。それらは習体制下の中国の内政をも大きく左右する。

25年は米中関係を主とする国際情勢が大きく動く年になる。日本としても中国の内政、外交、安保政策を十分、分析したうえで、中国に対して主導的に動く必要がある。待っているだけでは道は拓けない。それが「全ては中国側の都合次第」という日中関係の奇妙な構造を打破するきっかけになる。
中澤 克二(なかざわ・かつじ) 日本経済新聞編集委員兼論説委員、元中国総局長
仙台市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。1987年日本経済新聞社入社。政治部などを経て98年から3年間、北京駐在。首相官邸キャップ、政治部次長、震災特別取材班総括デスクなどを歴任。2012~15年中国総局長。2014年度「反腐敗」など一連の中国報道によりボーン・上田記念国際記者賞受賞。主な著書に『習近平の権力闘争』、『中国共産党──闇の中の決戦』『習近平帝国の暗号 2035』、近著に『極権・習近平──中国全盛30年の終わり』 (いずれも日本経済新聞出版)。

.jpg)








