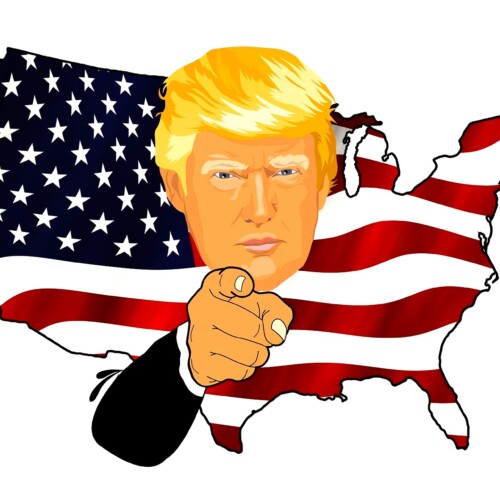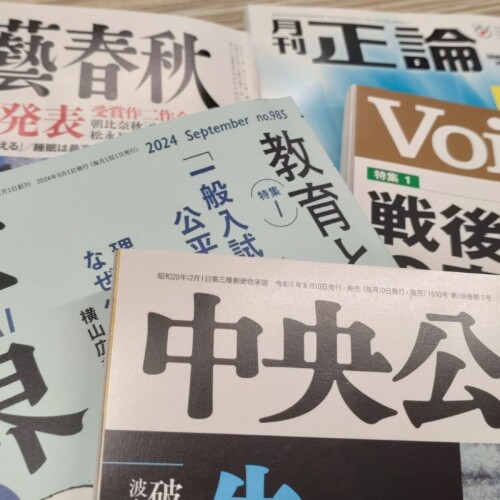コラム 論壇透かし読み
鈴木英生

戦争の時代から始まった「昭和」も100年を迎えた。写真は靖国神社
第6回 「昭和100年」と女性と社会党
12月発売の『中央公論』と『文藝春秋』2025年1月号は、共に「昭和100年」を冠した特集をしている。昭和は1926年12月25日から89年1月7日まで続いた。そう、仮に2回の改元がなければ、来年で昭和100年になるのだ。
『文藝春秋』は、昭和の著名人100人についてゆかりの人物が語る200ページの大特集を組んだ。副題は「高度成長とバブル編」なので、今後、続編もある?
人選は、政治家が佐藤栄作、中曽根康弘、竹下登……。財界人は中内功、佐治敬三、土光敏夫……。文化人は司馬遼太郎、梅原猛、井上ひさし……。この辺はわかりやすい。読売新聞の渡辺恒雄や創価学会の池田大作がいないのは、やや不思議。
ロック歌手の忌野清志郎や漫画家の矢口高雄、さらに、詩人・作家の森崎和江あたりも入るのは編集部のこだわりか。女性は森崎のほか、松田聖子、向田邦子ら計15人。将来、同誌が平成や令和の100人を選ぶならば、何人の女性が入るだろうか。
『中央公論』では、政治学者の御厨貴、エッセイストの酒井順子、社会学者・作家の古市憲寿が、座談会で昭和を象徴する3人をそれぞれ挙げている。御厨が、政治家の近衛文麿、池田勇人と共に作家・僧侶の瀬戸内寂聴を選んだのが興味深い。<常に生き生き><最後まで恋愛><手練れだから、政治家の男を転がすなんてわけない(笑)>。酒井が選んだうちの1人、作家の林芙美子は、<地方から出てきてのし上が>るバイタリティーが真骨頂だ。
瀬戸内ら同様に昭和を生き抜いてきた女性、ノンフィクション作家の澤地久枝は、『世界』で同業の後輩、梯久美子と対談した。
澤地は30年生まれ、梯は61年生まれと親子ほどの年齢差だ。それでも、二人の両親の来歴は、共に近代の庶民体験を映して似通う。澤地の母は、小学校高等科に進学したいと親に懇願したが、女中奉公に出された。4歳で孤児になった父は大工として働き51歳で死んだ。梯の父は農家の五男坊で元陸軍少年飛行兵、母も貧しい農家の出で戦後に中卒の紡績女工だった。
そして、澤地も梯も大学を出て、ものを書く仕事に就いた。澤地の母の人生にとって、澤地の早稲田大卒業式に呼ばれたのは大きな出来事だったという。澤地の世代はもちろん、梯の時代でさえ女性の4年制大学進学率は今よりもずっと低い。とはいえ、無数の澤地や梯たちが高等教育を受けて、活躍できるようになったのが昭和戦後期だった。
その『世界』の特集は「1995 始まりと終わり」。そういえば、『中央公論』でも御厨が、昭和が終わった89年よりも95年の<戦後50年のほうが大きな節目になっている>と語っていた。
昭和が終わった後、バブル崩壊や非自民連立政権の誕生などが続き、95年に阪神大震災や地下鉄サリン事件が起きた。戦後50年の「村山談話」、「慰安婦」問題のアジア女性基金設立もこの年。沖縄では米兵少女暴行事件が起き、今に至る反基地運動が盛り上がりをみせた。
つまり、ある面では戦前から継続し、高度経済成長を経て成熟した社会構造が大きく揺らぎ、あるいは揺らがされ始めたのが95年までの数年間だった。同年までを、英国の歴史学者、エリック・ホブズボームの「長い19世紀」に倣い、「長い昭和時代」とでも呼びたくなる。
『世界』の特集は、特に政治学者、宮城大蔵の「村山政権という問い」が面白かった。冷戦期、55年体制の最大の争点は、言うまでもなく憲法・安保問題だった。社会党は、村山政権(94年発足)で自民党と連立して自衛隊も日米安保条約も丸のみし、結果として存在意義を失った。
だが、この時期の社会党には、「戦後平和主義」を冷戦後の国際環境に適応させ、発展的に変容させる機会があり得たというのが、宮城の主張だ。
90年代初頭、自公両党と民社党は日本の国連PKO参加に向けて三党合意を結んだ。元々は社会党を含む四党合意を目指し、「自衛隊と別組織での参加」など同党の主張も大幅に採り入れていた。が、ボタンの掛け違いで協議は決裂。92年のPKO法案に社会党は牛歩戦術で抵抗した。そのわずか2年後には180度の路線転換だ。有権者にそっぽを向かれるのも無理はない。
社会党を含む四党合意が成立していれば、同党は<自らが提唱した形でのPKOの運用に関わる>ことになり、従来の平和路線の発展形態としてPKOを位置づけられたのではないか。その先で徐々に安全保障政策を進化できれば、自滅は避けられたかもしれない。もし、<社会党、あるいは社会党的なるもの>が生き延びたら、今、特に外交面で強調される自由や民主主義の価値などについても、また違った幅のある議論があり得た。そう宮城は考える。
現代日本は、昭和期と比して、ジェンダーなど特定の分野はよほど「リベラル」だ。ただし、『文藝春秋』が選んだ昭和の100人に、我が国初の女性の主要政党党首、土井たか子はいない。それほどまでに、昭和の記憶は遠ざかりつつあるのかとも思った。(文中敬称略)
鈴木英生(すずき・ひでお) 毎日新聞専門記者
1975年生まれ。毎日新聞青森・仙台両支局などを経て現職。学芸部で長く論壇を担当し、「中島岳志的アジア対談」など連載を元に書籍複数。
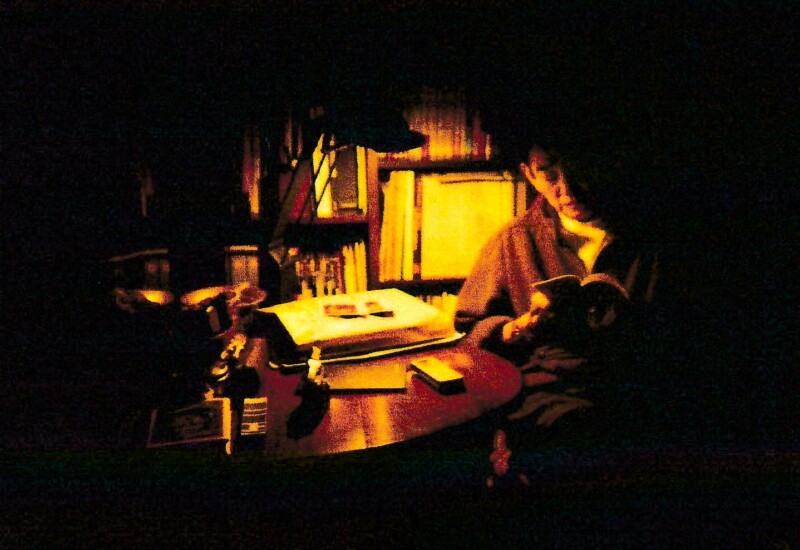



-500x500.jpg)