コラム マネー侃々諤々
関 和馬

日本の金融経済、人々の暮らしはどうなるのか──。夕闇が迫る日本銀行本館前で=浅井 隆撮影
第8回 日銀の「タカ派」ぶりは性急だ
◇日本経済の実態は「スタグフレーション」では?
つい先日、国会で日銀の植田和男総裁と石破茂首相の齟齬が話題となった。それは両者の日本経済に対する認識で、植田総裁は「現在はデフレでなくインフレの状態にあるという認識に変わりはない」と答弁。これに対し、石破首相は「日本経済はデフレの状況にはない。しかしながらデフレは脱却できていない。今を『インフレ』と決めつけることはしない」とあやふやな説明をした。
これを報じたネットニュースのコメント欄では「どちらも正しくない。日本経済はスタグフレーション(不況下のインフレ)だ」という意見が支持を集めていたが、私もそう思う。もし街角で「今の日本は景気が良いか」と聞いたら、大多数の人は首をかしげるのではないか。
現在の日本経済は、実質賃金は下落か良くて横ばい、国内消費も全く見劣りしている。金利上昇によって企業の倒産も増え始めた。また、個人の債務を巡る状況も深刻化している。政府の統計によると、家計債務は2023年に平均655万円(2人以上世帯)と、所得を初めて上回った。株価こそ好調だが、景気が良いと感じている人はどう考えても少ないように思う。もちろん、私だけが不景気を実感しているというのであれば良いのだが(涙)。
それゆえ、最近の日銀のタカ派ぶりには驚きを隠せない。ちなみに、金融における「タカ派」は政策が引き締め(利上げ)寄り、「ハト派」は緩和(利下げ)寄りという意味で使われる。ここ最近は植田総裁だけでなく、他の審議委員からもタカ派な発言が相次いでおり、マーケットでは国債が売られ円が買われている。
ただし、前提として、中長期的な金融政策の正常化は不可欠だ。一国の中央銀行が政府の発行する国債の大部分を買うという、これまでの日本の姿はまさしく異常であり、決して持続可能ではない。一方で、低金利に慣れきった我が国が性急に正常化を目指せば、実体経済が腰折れするどころかショック(危機)に陥る恐れもある。
現在の日本の政策金利は0.5%。これは17年ぶりの水準で、さらに0.75%への利上げが実施されればそれは30年ぶりの出来事となる。金利の観点では、まさに「失われた30年(デフレ)からの脱却」を象徴するイベントになりそうだ。
日銀を含め先進国の中央銀行は、中立金利(景気を冷やしも熱しもしない金利に期待インフレ率を加えたもの)を基準に政策金利を決めると言われている。ただし、この中立金利は現実の世界で測定することはできない。予想するしかないのだが、現時点の日本の中立金利は「1.2-2.8%」(推計値)だと考えられている。そのため、理論上はそれくらいまでの利上げは起こり得るということだ。
しかし、日本は悪いインフレ(スタグフレーション)によって中立金利が上昇しているのではないかという疑念がどうにも拭えない。これはあくまでも個人の感想だが、現在の経済は1%以上の政策金利に耐えられないように思う。半面、利上げには預金の利息を増やすことで景気にプラスの作用をもたらすことが考えられる。もっと言うと、利上げによる円高が昨今の物価上昇を良い意味で冷ますかもしれない。
それでも私は日銀がこのままタカ派な姿勢を続けていけば景気は腰折れし、最悪の場合は株価や国債が暴落することで日本経済が窮地に陥る可能性も低くないと思っている。あまりに急いで正常化へ旋回すれば、そこに待つのは石破首相が標榜する「楽しい日本」ではなく、「苦しい日本」ではないか。

関 和馬(せき・かずま) 経済アナリスト
第二海援隊戦略経済研究所研究員。米中関係とグローバル・マクロを研究中。

-1.jpg)




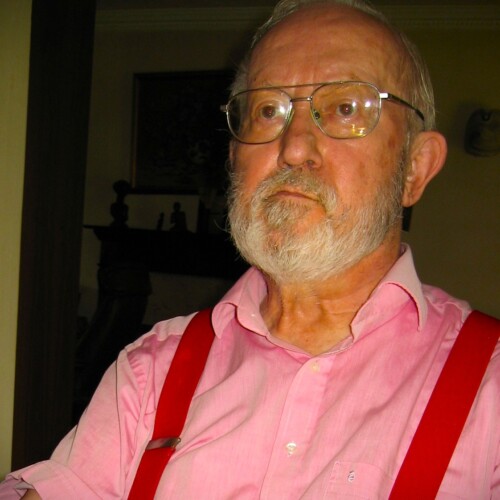

-500x500.jpg)

