コラム マネー侃々諤々
関 和馬

第9回 働かないニッポン、どこへ向かう
人手不足があちらこちらで叫ばれる昨今、都心部ではサービス業を中心に外国人の就労が当たり前となっている。なにもこれは日本だけの問題ではなく、先進国の多くで人手不足が常態化しつつある。競争力や社会インフラを維持していくためにも働き手の確保は喫緊かつ長期的な課題だ。
とは言え、ここ日本では少し気になる傾向がある。それは日本人の年間労働時間が減り続けているということだ。
OECD(経済協力開発機構)によれば、2023年の日本人の平均年間労働時間は1611時間。これをカレンダー通りに働く就労者に当てはめると、2023年の平日の数は247であったので、1日の労働時間は6.52時間。ちなみに1980年代の日本人は年間で2100時間ほど働いていたので明らかに減少傾向を辿っていると言えよう。
誤解のないように言えば、G7でも過去数十年は一様に年間労働時間が減少してきた。ここで私が真に取り上げたいのは、日本人の稼ぎがそこまで増えていないのにもかかわらず、労働時間が減っているということである。
当たり前の話だが、長く働けば良いというものではない。たとえば、G7では英国(1524時間)、フランス(1500時間)、ドイツ(1343時間)はいずれも日本より働いている時間が短い(いずれもOECDより、2023年)。一方で2023年の日本の1人あたり労働生産性は92,663ドル(877万円/購買力平価換算)と、上記3カ国よりも低く、OECD加盟38カ国中でも32位だ(当然G7では最下位)。

慢性的な人手不足に悩む日本の労働環境
日本にはこれといった資源がなく、高度経済成長期の頃から豊富かつ勤勉な「人材」こそが強みのはずだ。ハイテク化などで効率を上げる努力はもちろんだが、短期間で労働生産性を高めることができないのであれば、投入時間を増やすことも一案のはずである。
もちろん、ブラック企業のような会社が長時間労働を強いることは大きな問題だ。過労死などはもってのほかである。ただし、一方で仕事に没頭したいという人や無理のない範囲で残業代を稼ぎたいという人も少なからずいる。
◇国際競争力に勝つためには……
日本人の労働時間が減っている主な原因には、ホワイトカラーやパートタイム労働者の増加、サービス残業、もともと無償で働く人が多いこと、さらには祝日の増加などが指摘されている。
これらをもって「日本人が勤勉さを失った」なとど言うつもりは毛頭ないが、1人あたりGDP(国内総生産)が日本より上の米国(1799時間)、イタリア(1734時間)、カナダ(1685時間)、韓国(1872時間)の方が長く働いているという事実に日本はもっと奮起してもよいのではないか。
個人的には、先進国のなかで断トツに多い祝日の数が気になる。その分、有給休暇が取得しにくいといった面は課題としてあるものの、本来、国民に消費を促すための祝日であっても使うお金がなければ意味はない。海の向こう側、たとえばギリシャでは職種によっては「週6日」勤務制を導入しようとしている。韓国のサムスン電子も役員に限り6日制を導入している。
人手不足が慢性化するこの時代、もはや国民の総力戦で挑まなければ過酷な国際競争には勝てそうにない。働くことが「楽しい日本」を目指すことも、大切ではないか。

関 和馬(せき・かずま) 経済アナリスト
第二海援隊戦略経済研究所研究員。米中関係とグローバル・マクロを研究中。







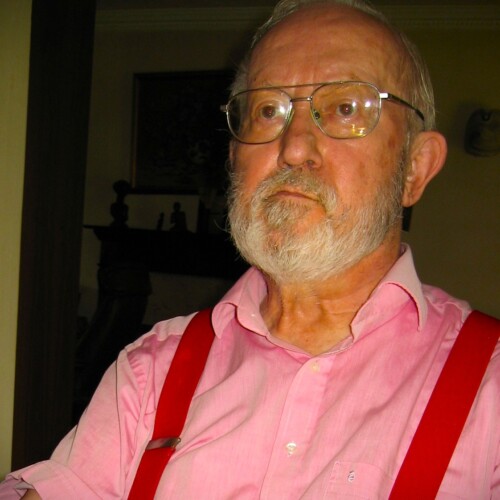
-500x457.jpg)

