一水四見 多角的に世界を見る
小倉孝保

旧ソ連と英国の「二重スパイ」だった故オレグ・ゴルジエフスキー氏=2014年6月、小倉孝保撮影
第10回 伝説の「二重スパイ」は何を言い遺したか
東西冷戦時代、秘密情報機関は互いに敵対国にスパイを潜入させた。周到な準備が必要で、一歩間違えばスパイの命が危険にさらされる。そのため、「二重スパイ」を送り込む作戦は宇宙開発にも例えられた。旧ソ連国家保安委員会(KGB)のスパイでありながら、英秘密情報部(MI6)の協力者となった「二重スパイ」、オレグ・ゴルジエフスキー氏が亡命先の英国で86年の生涯を閉じ、3月21日に発表された。
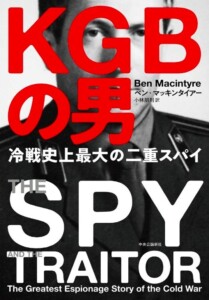
ゴルジエフスキー氏本人インタビューやMI6関係者証言をはじめ、激烈な諜報活動の実態を克明にたどった英国発の世界的ベストセラー(中央公論新社刊)
英ソ(露)のスパイ合戦史においても特筆すべき人物で、スパイを扱った著作の多い英国のノンフィクション作家、ベン・マッキンタイアー氏はこう書いている。「ごくたまに、スパイが歴史に大きな影響を与えることがある。オレグ・ゴルジエフスキー氏はその一人だ」
私は2014年6月、ロンドン郊外の自宅でゴルジエフスキー氏をインタビューをしている。元FSB(露連邦保安庁)中佐、アレクサンドル・リトビネンコ氏がロンドンで放射性物質「ポロニウム」によって殺されてから8年が経過していた。リトビネンコ氏の妻、マリーナさんは当時、暗殺の真相を知ろうと法廷闘争を繰り広げていた。私はその活動を追う過程で、ゴルジエフスキー氏の存在に興味を持った。
FSBはKGBの後継機関である。リトビネンコ氏は共にソ連・ロシアの秘密情報部出身で、MI6に協力した者としてゴルジエフスキー氏を慕った。私が訪ねると、薄暗い書斎に通された。元KGBロンドン支局長は温和な顔に白いあごひげをたくわえていた。薄赤色の半袖シャツに吊りベルト姿である。「以前、日本の秘密情報機関の方がここを訪ねてきましたよ。日本人の客はそれ以来です」。日本の秘密情報部員はロシアと北朝鮮の軍事協力関係に興味を持っていた。「ロシアについて、とても詳しいので驚きました」と感想を語った。
リトビネンコ氏からは、「親友」と呼ばれていた。「彼には実直な印象を持っていました。ただ、あんなにおしゃべりなエージェント(秘密情報部員)は初めてです。簡単な質問をすると、本題に入るまでに時間がかかる。むしろ警察官のような正義感を持っており、エージェントにはなりきれなかったと思う」。生活面での相談にも乗った。「MI6は将来、家族の面倒をみてくれるだろうかと心配していました。年金の話もしましたよ」
ゴルジエフスキー氏の最大の功績は、核戦争を回避させたことだとされている。1981年に米大統領に就任したレーガン氏はそれまでの「デタント(雪解け)」政策を転換し、ソ連を敵視する。ソ連政府は米国が核攻撃を計画していると判断し、世界中のKGB職員に兆候をつかむよう命じた。この動きを西側に伝えたのがゴルジエフスキー氏だった。この極秘情報を受け、米政権は攻撃の意図はないとのメッセージをクレムリンに送る。被害妄想に駆られたソ連政府による核兵器の先制攻撃は避けられた。
英政府は2007年、「英国の安全保障に貢献した」として聖マイケル・聖ジョージ勲章(CMG)を授与した。映画『007』の主人公、ジェームズ・ボンドも受けた勲章である。ゴルジエフスキー氏は60年代前半にKGBに入った。ソ連軍がプラハ市民を弾圧したのを知り、祖国に愛想を尽かしMI6に協力した。85年にその活動がソ連側に察知され、英特殊部隊によって救出された。本人不在のまま死刑判決が言い渡されている。
英語による約2時間以上のインタビューで、二重スパイになった理由を「民主的な社会を実現するには、邪悪な独裁国家を潰す必要があった」と説明した。欧米諸国はかつて、経済・エネルギーの観点から、プーチン政権と良好な関係を築こうとした。ゴルジエフスキー氏はそれを強く批判した。「文明国は野蛮な国と対抗しなければなりません」
露軍がウクライナに侵攻して3年が過ぎた。米国のトランプ政権は露政府の主張に一定の理解を示す一方、国際法には関心が低い。第二次世界大戦が終わって80年になる今、国際秩序はまさに音を立てて崩れようとしている。「二重スパイ」の言葉は人類に対する「遺言」のようだ。なお、ゴルジエフスキー氏の発言内容は、拙著『プーチンに勝った主婦 マリーナ・リトビネンコの闘いの記録』(集英社新書)で詳報している。
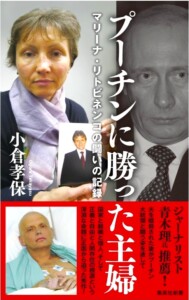
筆者の最新刊『プーチンに勝った主婦 マリーナ・リトビネンコの闘いの記録』(集英社刊)

小倉 孝保(おぐら・たかやす) 毎日新聞論説委員
1964年生まれ。毎日新聞カイロ、ニューヨーク、ロンドン特派員、外信部長などを経て現職。小学館ノンフィクション大賞などの受賞歴がある。




-500x500.jpg)

-500x500.jpg)
は株価上昇の象徴。-500x500.jpg)


