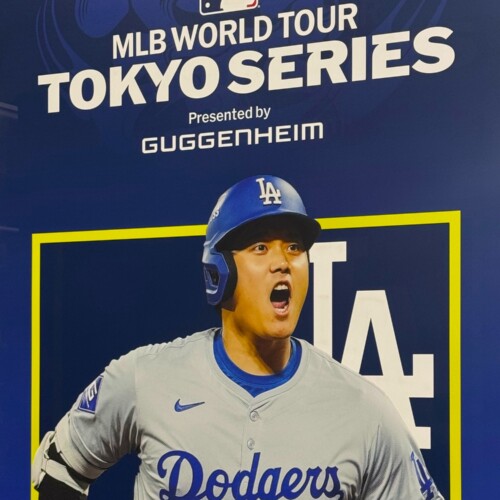日本政治の転換点─多党化に即した統治構造へ
牧原 出(東京大学教授)

参院選の結果、自民・公明の与党は昨秋の衆院選に続いて過半数割れとなった
参院選で自公の安定基盤崩壊──
内閣と官邸機能の強化は過去のものに
◇国会運営は野党ペースへ
7月20日投開票の参議院選挙は、日本政治が転換点にさしかかったことを明らかにした。昨年10月の衆議院総選挙での自公の過半数割れに続いて、参議院でも自公過半数割れとなったからである。もはや自公が国会における安定的な政治基盤のもと、与党として政策を展開する時代は過ぎ去った。

自公の敗北を伝える参院選翌日の朝刊各紙(7月21日付)=中澤雄大撮影
さらには、3年後の参議院選挙では自公の改選議席数は今回よりはるかに多い75議席であり、よほど大勝しなければ過半数に達することはできない。したがって、今後6年を超えて自公合わせて過半数議席に満たない状況が続くとみてよいだろう。自公が政権にいたとしても、国会運営は野党のペースで進まざるを得ない。自公が独自性を発揮する余地は乏しく、政権が立ち枯れする可能性が高くなった。今後数年かけて、自公から自公以外の政党による政権へと移行することも念頭に政治を見る必要が出てきたのである。
◇少数与党・自民の後継総裁に問われる課題
自民党内では、石破茂首相の責任を問う声が噴き出している。大敗の責任を総裁が取るべきだと言うのであれば、党そのもののあり方も見直すべきであろう。自民党が未だ直面したことのない「いつ野党となるか判らない少数与党」のもとでの党組織とは何かが問われる。

自民党本部
すでに石破総裁が辞任した場合、後継総裁をどう選ぶか、また後継総裁がどのように政権を組織できるか、そのために総裁選挙に際して候補者には何が必要か、が問われている。いずれも少数与党としての総裁選挙とは何かという問いをめぐる課題なのである。
そもそも事の発端は安倍派の裏金という政治資金疑惑だった。そこから自民党への不信感が広がり、昨年の衆議院総選挙、今回の参議院選挙と敗北し、政治資金規正法改革はまだ道半ばである。少数与党による多様な連立の可能性の模索が続く中、こうした改革はさらに進むだろう。
◇政治資金問題の解決はこれから
1990年代を振り返ってみたい。リクルート事件(88~89年)に端を発した政治改革の流れの中で、すでに自民党は参議院選挙(89年7月実施)で過半数を失っており、党の分裂と多党化を経て、93年の総選挙で敗北し、野党に転落する。その後選挙制度改革と政治資金制度改革を経た政治改革関連法が成立し、規制緩和、地方分権改革、省庁再編、司法制度改革といった統治構造改革が次々と着手された。
こうした過程が今後再び始まるだろうか。少なくともいくつか手を打たなければならない改革はある。その先に、改革の方式は別として、積み残し得ない改革課題が出てくることはやはり想定しなければならない。
まず、自公政権が少数となった現在、2026年1月1日から始まる改正政治資金規正法の施行を前に、とりわけ第三者機関の制度設計など法運用の細部を詰める必要があるし、野党が多数の国会でそれをなおざりにはできないだろう。

首相官邸
また年内に解決に至らない課題があったとしても、国民の厳しい視線が将来再度この問題を政治課題に押し上げることも十分考えられる。そもそも裏金問題は、少子高齢化に伴う負担増により、国民が政治家に対して厳しい視線を注ぐようになったから生じた。この負担増は今後の政治の基調である以上、政治資金問題に端を発した政党のあり方は常に改革課題となるであろう。
◇さらなる少子高齢化への準備が必要
その先に必要なのは、さらなる少子高齢化の時代への準備である。当面、国民は負担軽減を求めているが、今や次第に明らかになりつつあるのは、生活保護世帯もあれば、備蓄米の放出を強く歓迎する生活苦が深刻な層もあり、当面生活に余裕はあるが老後への準備に不安を感じる層もあるなど、それぞれの不安は異なることだ。そうした異なる不安をそれぞれに和らげるメッセージが求められる。本格的な少子高齢化が到来すれば、さらなる負担増は避けられない。こうした状況に即して、今ある制度も手直しが必要になるだろう。
たとえば国と地方の関係では90年代の国から地方への事務移譲による地方分権改革とは異なり、事務量の増大と職員不足に悩む市町村から事務を軽減し、大規模の市や都道府県への事務の吸収が改革課題となる。総務省における「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会」は、6月の報告書で、定型的な事務を小規模市町村から都道府県や近隣の地方自治体に移譲する方向性を打ち出した。そうした方向の改革は今後何らかの形でさらに試みられるであろう。
◇官邸の再設計と各省の政策能力を高める仕組み
また官邸を中心とする体制は、第2次以降の安倍晋三政権で従来と比べて格段に戦略的な意思決定を果たすことができた。だが、新型コロナウイルス感染症の拡大の中、安倍晋三・菅義偉・岸田文雄各政権では、適切な対応どころか、多面的検討に乏しい官邸の決断が地方自治体や専門家との対立を生み、混乱が続いた。
しかも、私たちの研究グループが政策シンクタンクPHP総研『官邸の作り方』で論じたように、首相に就任する数カ月前からスケジュール作成、官邸の人員配置、政策策定の順序について準備する必要がある。そうでないと、首相就任後、官邸が戦略的に政策を打ち出し、安定的な政権基盤を創出することはほぼ不可能である。実際に、安倍政権後の菅・岸田・石破各政権は、官邸を設計する余裕のないまま、政権を発足させ、状況に翻弄され続けた。

霞が関の官庁街
そうした事前の周到な準備を伴う官邸の設計と併せて、各省人事を統制しすぎて政策面で萎縮させないことも不可欠である。事実、少数与党下での与野党交渉の際に、各省から実現可能な政策決定の選択肢が示されないと、厳しい交渉の上に成立した合意を実行することがかなわず、白紙に戻ることになりかねない。
ここでは、強い要求を与党に突きつける野党の側で、どこまで政策の実現可能性を認識するかが問われる。
また交渉を通じて政策の実現に自負するところがありながらも、その結果に責任を負うことも重要である。このような過程においては、各省は官邸の意向にのみ服するのではなく、与野党間の専門知あるアンパイアにならなければならない。その意味での能動性が欠かせないのである。
少数与党下での官邸と各省の改革は、当面は与野党間交渉を円滑に進めるための態勢作りとなるだろう。だが、2001年の省庁再編から20年以上が経ち、今や制度への再点検が必要な時期にさしかかっている。90年代では、衆議院総選挙(96年10月実施)で過半数に近い239議席を確保した第2次橋本龍太郎内閣が、六大改革として多岐にわたる改革に着手し、その一環として省庁再編も進めた。内閣と省庁の点検作業が本格的に始まる時は、与党がより安定した基盤を得た時となるだろう。
◇政党支持はSNS次第で変化する可能性大
90年代は93年8月の自民党の野党転落から、3年後には第2次橋本内閣が発足した。現在の多党化した政党配置のままでは、自公政権のような強固な信頼関係の上での連立の枠組みが広がることは考えにくく、そうした段階が来るとは言えない。

参院選東京選挙区・参政党新人候補の演説に集まった有権者ら=JR御茶ノ水駅前で7月17日、中澤雄大撮影
だが、今回の参議院選挙で議席を増やした国民民主党、参政党がSNS戦略で票を伸ばしたとすれば、SNS次第でその支持も大きく変化する可能性が高い。こうした党を含めて政党間の離合集散が始まることも十分あり得る。それは政党間の結集もあれば、さらなる多党化でもあり得るだろう。政党のあり方次第で改革がどのように進むかどうかが決まってくる。裏金問題の発覚以降、衆参の選挙を経て、ようやく多党化という新しい政治構造を生み出した。それはいずれ自らにふさわしい統治構造を要求するだろう。
◇多党化とデジタル化に即した統治の仕組みに
ただし、90年代と決定的に異なるのは、当時はインターネットがほとんど改革で用いられず、デジタル化を前提としない改革だったことである。意思決定が加速し、改革があったとしても、滞りなくシームレスに新しい制度が運用される必要がある。AIが意思決定に活用されることもあるだろう。
そうなると、改革があったとしても、デジタル化に即して進まざるを得ないことになる。多様な政党が参画したからと言って、改革が頓挫するとは言えない。また多角的な検討も可能になるだろう。つまりは、官邸に意思決定を無理に一元化するのではなく、各省がイニシアティヴをとり、与党の枠組みが広がる中で、それに即した統治構造、いわば「アジャイル」〔註1〕な統治構造ヘと向かうことが、今後の課題となるのではないだろうか。
この改革の方向性は日銀や公正取引委員会、さらには司法権などの独立機関にも当てはまる。司法権を除けば、多くの独立機関の幹部は国会同意人事であり、少数与党が人事を専権することができない。野党が同意する範囲でのみ独立機関の幹部人事が可能になる。場合によっては、与党の意思にそぐわない人物が野党の強い要求で幹部となることがあり得る。その結果、独立機関は政権からより独立性を強めることになるだろう。
◇90年代の構想を越え、分散的かつ統合可能な制度に
国と地方の間は、市町村へ権限と事務を下ろすのではなく、国や都道府県に事務が吸い上げられる改革が進むと指摘したが、それは集権を意味しない。自治体にとっては、すでに執行の最大限近い業務を抱えている。そこからイニシアティヴが生まれるには、抱えた事務量を整理削減する必要がある。また、人口減のもとで自治体数を減らす改革も考えられる。その時は、地方に大きな権力核が析出し、国との間で協力関係にも対抗関係にも立つことになる。
官邸一元化ではなく各省の自立化、独立機関の一層の独立性の確保、国と対抗する地方自治体の登場といった改革は、内閣強化とは一見逆行する。だが、国と官邸に権力をさらに集中させる改革は、二大政党制による圧倒的な与党形成に適合的ではあっても、多党化には適合的ではない。

国会議事堂
こうしていくつかの制度に即して改革の方向性を構想していくと、90年代に構想された地方分権化、内閣と官邸機能の強化が過去のものとなりつつあることが明らかとなる。それはすでに達成されており、今後はそうした仕組みを前提としつつも、デジタル化の流れを援用し、分散的でありながら、統合可能な制度を作り上げることとなるであろう。
[註釈]
註1=アジャイルとは、変化に迅速かつ柔軟に対応しながら価値を生み出す考え方や手法を指す。
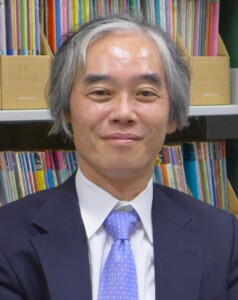
牧原 出(まきはら・いづる) 東京大学先端科学技術研究センター教授
1967年生まれ。東大法学部卒。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス客員研究員、東北大学大学院教授などを経て2013年より現職。専門は行政学、日本政治史。著書に『内閣政治と「大蔵省支配」』(中央公論新社)、『崩れる政治を立て直す』(講談社)、『田中耕太郎』(中央公論新社)など。




-500x500.jpg)