コラム 論壇透かし読み 鈴木英生
第3回 「エモい記事」論争

鈴木英生(毎日新聞専門記者)
「エモい記事」論争なるものが、先月末ごろから再び論壇誌や論壇系サイトを賑わせている。元々の発端は、朝日新聞のサイトに西田亮介・日本大教授が寄せた論考(3月29日)だった。
西田氏のいう「エモい記事」とは、たとえば「わが町のちょっとイイ話」「地元で愛された店が閉店する」「日々の記者の独白やエッセー」といったたぐいの新聞記事のこと。<データや根拠を前面に出さず、何かを明確に批判するのでも賛同するわけでもなく、「読む意味」が曖昧で、記者目線のエピソードや物語(ナラティブ)を重視した記事>(『Voice』10月号でのジャーナリスト、武田徹氏との対談)と定義している。
昔から新聞の社会面や夕刊などには、こうした「箸休め」的な記事やコラムがつきものだ。西田氏も「エモい記事」を全否定はしない。が、特に近年、夕刊の1面などで増えすぎているのではないかとみる。
インターネットで個人が直接世界へ発信できる時代に、素人でも書けそうな記事を多数載せる意味はあるのか。ネットに押されて部数が低迷するなか、限られた紙面とマンパワーはもっと深いニュースの分析などに割くべきでは? 西田氏は、新聞が自らの役割を再確認してほしいという思いで問いかけた。
なのに、西田氏の主張は「エモい記事不要論」だと当の朝日新聞の記者らに誤読され、同紙のサイト上に反論が並んだ。これに対する西田氏の批判や、西田氏に触発された新聞の役割や将来についての議論が、特にこの1ヵ月、目白押しだ。上記の『Voice』対談、ノンフィクションライターの石戸諭氏の論考(「プレジデントオンライン」8月31日)、西田氏と大澤聡近畿大准教授の対談(『プレジデント』9月13日号)、批評家、東浩紀氏のコラム(『AERA』9月16日号)……。
その多くが強調するのは、<「全国紙」のビジネスモデルは終わりに近づいている>(石戸氏)といった危機感である。昨年、1世帯あたりの新聞発行部数はついに0・49部と過半数割れした。2000年代初頭に1000万部超を誇った読売新聞は約595万部。朝日新聞(約343万部)、毎日新聞(約154万部)は当時の半分以下(24年上半期、日本ABC協会)だ。
各紙は地方支局や通信部の統廃合、一部地域の夕刊廃止に続き、一部の県で配達停止にまで踏み切りつつある。ネットのニュースサイトに力を入れる社も多いが、有料会員数は紙の新聞部数に遠く及ばない。
この状況下で、新聞はどうやって新たな読者を獲得すべきか? 武田氏は、「エモい記事」が増えたのは従来型の客観中立な記事では若い層に響かないと新聞社が考える故だと分析した。ネット上では、自分の信条を正直に発した「真正性」のある言説が力を持つ。せめて、その語り口くらいはまねて読者を引きつけようと、「エモい記事」が増えたのではないかと。
ただ、ネット上の「真正性」のある言説は、往々にして極度に主観的だったり、事実に基づかなかったりする。かつ、より扇情的で過激なものほど読者にウケる。つまり、PVやCVを稼げる。そして、極端な言葉で社会の分断を加速させてしまう。
石戸氏は、2010年代、ネットニュースメディアに在籍した。当時、ネットのみで配信するニュースメディアは複数生まれていたが、そのいくつもが立ちゆかなくなった。結局、前述のような「真正性」競争の波に飲み込まれた面もある。しかも、そうなってすら収益化は難しかった。
また、石戸氏は、一から粘り強く取材して記事を書ける人材の育成やスキルアップを大規模にできる組織は、今のところ新聞社しかないと強調する。ネットメディアは、こうした能力を育てる余力やノウハウが乏しい。
それ以上に、ネットだけで記事を書いていても、取材力を磨くインセンティブが働きにくい。ネットでは、特に根拠薄弱でも「真正性」が強い、特定の思想信条や政治的傾向を持つ層の感情に働きかける原稿ほど、「よい記事」とされかねないのだから。
結局、各氏の認識は、信頼性が相対的に高い情報を全国で取材・発信したり、大量の人材を育成できたりするニュースメディアは、今のところ全国紙(とNHKなど)だけだという点とその必要性について、おおむね一致する。
そのうえで、今後ますます紙の新聞を縮小してネット版へ移行するにしても、既存のネットメディアと同じ競争をしては、新聞の特性が失われる。そもそも、経営が成り立たない。
では、どうすべきか。実は、ネットメディアではPV数などと収益を直結させすぎない努力が始まっている。動画プラットフォームのABEMAの場合、単体では赤字だが、競輪と競馬の「投票券」のオンライン販売で売り上げを伸ばしている(『プレジデント』での西田氏の発言)。新聞も同様に、コンテンツを経営と切り離して考え、記事と別に何らかの「ドル箱」を持つべきだと。
さらに西田氏は、新聞を<もはや民業で現状を維持するのは難しいのではないか>とまで踏み込んでいる。報道の「ナショナルミニマム」(国家の保障する最低水準)を議論する必要性に言及し、補助金制度の導入も提案した。つまり、報道の質や多様性の維持は公共的な課題であり、いわば電気や水道、道路などと同様のインフラとして考えるべきなのだ。
最後に、「エモい」エピソードをひとつ。四半世紀前に私が毎日新聞社へ入社した頃、本州最北端にある青森県下北半島の某村(人口約3000人)で、毎日新聞の購読者は5人と聞いた。当時からその程度のシェアだった。
それでも、販売店員は最寄りのむつ市から毎朝、村に5部を配達する。極端に厳しく長い冬の日々も。その新聞を受けとった5人(5世帯)の読者は、何気なく目にした私の記事から、興味がなかった問題に強い関心を持ったり、日常にない視野が広がったりするかもしれない。ここに新聞記者という仕事の意義と責任があると思っていた。
かつて新聞の現場にいくらも転がっていただろうこんなナラティブを、どう再興するか。つまりは、読みたいものしか読まれないネット空間でも<紙の新聞がもっていた豊かさをどう維持するか>(東氏)。「エモい記事」論争の先で見いだされるべきは、その展望だと信じたい。
鈴木英生(すずき・ひでお)
1975年生まれ。毎日新聞青森・仙台両支局などを経て現職。学芸部で長く論壇を担当し、「中島岳志的アジア対談」など連載を元に書籍複数。




-500x500.jpg)

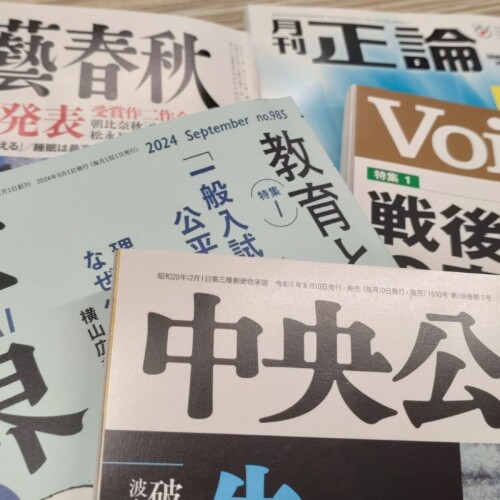
-500x500.jpg)
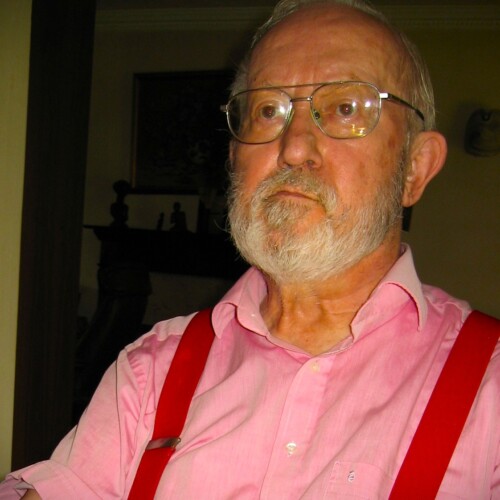

-500x457.jpg)
