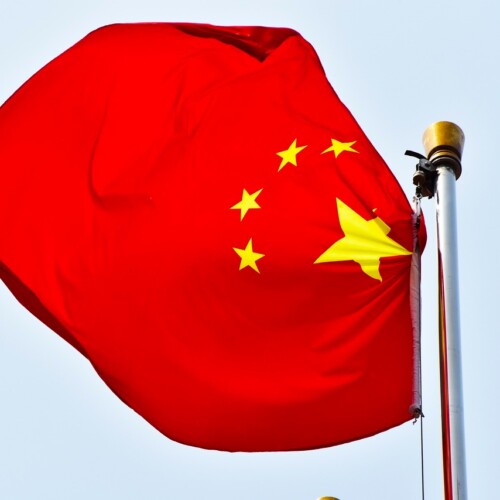シリーズ「戦後80年 日本の変革」
歴史に学ぶこれからの外交と政治
井上 寿一 (学習院大学教授)
のグラビア(国立公文書館デジタルアーカイブより).jpg)
内閣情報部発行の『写真週報』創刊号(昭和13〔1938〕年2月16日号)のグラビア(国立公文書館デジタルアーカイブより)
多国間協調主導する国内体制確立を
◇“新たなヤルタ会談”? 急迫告げる国際情勢
ウクライナ和平に関連して、「ヤルタ2.0」あるいは「新たなヤルタ」との表現が頻出するようになった。これらの表現が1945年の米英ソ首脳会談=ヤルタ会談を想起させるように、「戦後80年」はメディアの周年イベントとしてではなく、喫緊の課題として80年前の歴史をとおして考えることを促す。国際情勢が急迫を告げる一方で、日本国内では石破茂首相の商品券配布問題が政治問題化している。「政治とカネ」の問題に対する有権者・国民の視線はきびしい。内閣支持率が急落する。少数与党内閣のゆくえは危うい。首相は「戦後80年談話」を出す検討もしていたとのことである。しかし7月の参議院選を経て、8月15日前後の首相が誰になっているか、予断を許さない状況である。以上を踏まえて、「戦後80年」の年にこれからの日本は世界のなかでどのような方向に進むべきか、歴史をさかのぼって考える。
◇1930年代、対外関係修復の試み
米国のソ連の協調関係は、ヤルタ会談よりも前から始まっていた。
1933年11月に米ソは国交を樹立する。イギリスはソ連と断交したままだった。国交樹立による米ソの接近の外交戦略上の意図には対日抑止があった。1931年の満州事変によって、ソ連を仮想敵国とする日本が対ソ戦の戦略的拠点・軍事資源の供給地として満州を確保したからである。

対する日本は、1933年5月の日中停戦協定の成立によって満洲事変に大きな区切りをつけ、対米・対ソの外交関係の修復に向かう。この年のロンドン世界経済会議では日本はアメリカと共同歩調をとる。同年にはソ連の所有する北満州鉄道を満州国(実質的には日本)に売却する交渉が始まる。日本はアメリカよりもさきにソ連を承認し、イギリスとは異なり、国交を維持し続けていた。
対米・対ソ関係はそれ以上には修復しなかった。翌1934年になると、今度はイギリスとの間で不可侵協定を結ぼうとする。この年から翌年にかけて、中国をめぐる日英協調が模索される。
◇現代にも通じる「三つの選択肢」
対外関係の修復の試みは、国内における政党勢力の復権を促す。1932年の五・一五事件によって政党内閣は崩壊した。代わりに非政党内閣が続く。どのような政党内閣の復活の可能性があったのか。第一は衆議院で第一党の立憲政友会の単独内閣である。第二は第二党の立憲民政党が社会大衆党や非政党勢力とも連携しながら、政権復帰をめざす選択である。第三は立憲政友会と立憲民政党が「大同団結」して、大連立を組むことである。
これら三つの選択肢は今日に似る。第三の選択は、石破首相が言いかけて自ら否定した。それでは第一の選択と同様に、少数内閣であっても第一党は自民党なのだから、このまま参議院選に臨むのか。それとも第二の選択と類似して、日本維新の会や国民民主党との連携を強めるのか。
1936年2月20日の衆議院総選挙では国民は第二の選択を求めたようだった。立憲民政党を第一党に返り咲かせ、社会大衆党を躍進させたからである。今年の国民の選択はどうか。第一あるいは第二に類似した選択のどちらであれ、政党間の対抗と提携関係の再編は不可避のようである。
◇状況は急変したが、軍事リアリズムを欠いた
歴史の方はどう動いたのか。政党内閣が復活する前に状況は急変する。1937年7月7日の日中間の偶発的な軍事衝突(盧溝橋事件)が戦争に拡大していく。8月21日には中ソ不可侵条約が成立する。アメリカも日本の九カ国条約(中国の門戸開放・領土保全を定めた条約)違反を問う姿勢に転じる。
そうであっても、日中戦争をめぐって、米ソが共同歩調をとるようになったのではなかった。ソ連の対中接近は限定的だった。アメリカも中国を道義的に支持したものの、日中に対して中立的な立場を崩すことはなかった。
問題は日本だった。日本は軍事リアリズムが欠けていた。仮想敵国=ソ連に備えるのであれば、徒に中国と事を構えてはならなかった。それなのに戦争目的も不明確なままに、戦線を拡大し続けた。
-208x300.jpg)
近衛文麿首相(『写真週報』昭和13〔1938〕年2月16日号、国立公文書館デジタルアーカイブより)
◇戦争終結を妨げた強硬な国内世論
近衛文麿内閣は主観的には戦争の早期終結を模索する。可能性があったのは、トラウトマン駐華ドイツ大使の和平仲介工作だった。しかし日本の国内状況がこの和平工作の妨げとなった。戦勝気分に沸く国内では領土の割譲や賠償金を求める声が強かった。強硬な国内世論を背景に、日本側は和平条件を加重する。これでは和平は実現しなかった。
日中戦争の負荷に耐えながら、日本の戦時外交は1940年11月に日独伊三国同盟を結び、翌年4月には日ソ中立条約の締結に至る。外交ポジションを改善した日本は、対米交渉を軌道に乗せる。ところが6月22日に独ソ戦が始まる。対ソ戦にも忙殺されることになったドイツと日伊の三国同盟は、対米圧力を弱める。攻勢に転じたアメリカは、日本との交渉において非妥協的となる。
◇緒戦の勝利に幻惑され戦争終結構想を欠いていた
対する日本は、アメリカの経済制裁によって身動きが取れなくなる前に、真珠湾の奇襲攻撃に出る。しかし緒戦の勝利に幻惑された日本は、軍事リアリズムを失っていく。奇襲攻撃に成功したのならば、なぜ真珠湾を占領しなかったのか。真珠湾を占領すれば、それを和平の取引材料として交渉できたはずだった。和平が成立すれば、予防戦争としての対米戦争は成功である。アメリカが再び参戦するのはむずかしかった。
それだけではない。なぜ不要不急のミッドウェー海戦を仕かけて敗北したのか。決戦の「天王山」はつぎつぎと移動した。陸海軍の戦略の統一はできなかった。戦争終結の具体的な構想を欠く戦争では勝ち目はなかった。
.jpeg)
真珠湾攻撃(『写真週報』昭和17〔1942〕年1月7日号、国立公文書館デジタルアーカイブより)
1945年になると、戦況は一段ときびしくなる。戦争終結を求めて、日本はソ連に接近する。欧州戦線では米ソは連合国として戦っていた。しかしアジア太平洋戦線では違った。日ソ中立条約は有効だった。駐ソ大使の経験を持つ元首相の広田弘毅とマリク駐日ソ連大使との間で断続的に会談がおこなわれる。
ところが2月のヤルタ会談で密約が結ばれていた。ドイツの降伏後、数カ月でソ連が対日参戦することになっていた。この密約のとおり、8月8日、ソ連は日本に宣戦布告する。前後して広島と長崎に原爆が投下される。日本は8月14日にポツダム宣言を受諾する。こうして80年前に戦争は終わった。
◇「リベラルな国際秩序」支える共同歩調を
以上の歴史は何を示唆するのか。
今もこれからもアメリカは国際秩序に限定的にしか関与しないならば、それは1930年代のアメリカに似る。当時のアメリカは国際連盟未加盟国だった。そのアメリカと国際連盟からの脱退を通告した日本は、ロンドン世界経済会議で共同歩調をとった。このことが間接的に示すように、自国中心主義あるいは孤立主義のトランプ大統領のアメリカであっても、日本は国連などの多国間協調の場で共同歩調をとるべきだろう。
しかし冷戦時代のような対米依存の同盟関係を続けることはリスクがともなう。リスクヘッジの外交戦略上の意図も含めて、日英不可侵協定を模索したように、今や“準同盟国”となったイギリスとの提携を強化することで、リベラルな国際秩序を支えなくてはならない。提携すべきはイギリスだけではない。地理的な近接性ではなく、国家の機能の近接性に基づく提携、すなわち機能的地域主義に基づいて、EU(欧州連合)諸国やカナダ、オーストラリア、ニュージーランドといった価値観を共有する国ぐにと国際的な責任を分有すべきだろう。これらの国ぐにとは、トランプ大統領のアメリカの保護貿易主義に対して、自由貿易の堅持の観点からも共同歩調をとる必要がある。
さらに「台湾有事」や北朝鮮の核・ミサイル問題といった地政学的なリスクにも備えなければならない。ガザ紛争の解決に暗雲が垂れ込め、ウクライナ戦争の和平も不確かな国際情勢のなかで、日本の国際的な責任は重い。
◇野党は連立構想の具体化を進めよ
日本が国際的な責任を果たす外交を展開するには、安定的な国内基盤が欠かせない。ところが今の有権者の政党別支持率は、分散化の傾向を強めている。政党間提携の再編は簡単ではない。それでも分散化傾向の政党を保守対リベラルの枠組みに近づけなくてはならない。非自民の野党勢力は、単一の野党では政権はとれないのだから、理念と政策を共有するどのような連立内閣を構想するのか、その具体化を進めなければならない。
かつて立憲民政党は、総選挙で第一党になったものの、単独での政権復帰と連立志向との間で、党内をまとめきれずにチャンスを逸した。このような失敗を繰り返すことなく、国際社会において責任を果たすことのできる国内体制の確立が急務である。

井上 寿一(いのうえ・としかず) 学習院大学法学部教授(日本政治外交史)
1956年東京都生まれ。一橋大学社会学部卒業。同大学大学院法学研究科博士課程、一橋大学法学部助手などを経て学習院大学法学部教授、同学部長、2014年より2020年まで同大学長。主な著書に『危機のなかの協調外交』(山川出版社、吉田茂賞)、『日中戦争』(講談社学術文庫)、『昭和史の逆説』(新潮新書)、『吉田茂と昭和史』(講談社現代新書)、『山県有朋と明治国家』(NHKブックス)、『戦前昭和の社会 1926-1945』(講談社現代新書)、『戦前日本の「グローバリズム」』(新潮選書)、『戦前昭和の国家構想』(講談社選書メチエ)、『政友会と民政党』(中公新書)、『広田弘毅』(ミネルヴァ書房)、『矢部貞治 知識人と政治』(中公選書)など。共著(著者代表)に『立憲民政党全史 1927─1940』(講談社)など。最新刊に『新書 昭和史』(講談社現代新書)。
と弾劾反対派(右)の横断幕が掛かっていた。韓国社会は分断が一層深まっている=2025年3月11日-800x550.jpg)





-500x500.jpg)