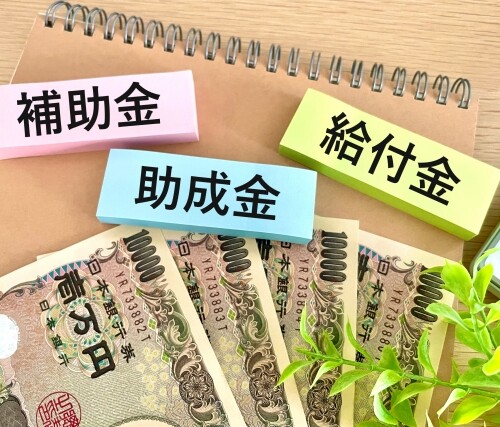佐藤主光教授インタビュー
ルール無き経済がもたらした病状
第2回 経済を強くし財政を健全化するには

財務省
佐藤主光(一橋大学教授、財政学・公共経済学)
◇新政権の課題は経済成長と格差是正
今、自民党総裁選が行われています。政治資金はもちろん大事です。国民はあまりにも政治に対する不信感を持っている。ただ、考えなければならないのは、様々な問題に取り組むために、自分たちの足腰がいかに弱いかということです。例えば中国の軍事力の脅威や安全保障の問題も分りますが、安全保障というには国力を高めなければならない。国力を高めるには、経済が成長しないとどうにもなりません。まずは経済の基盤をどうするかという議論が必要です。
それから、日本社会で格差が広がっていることが大きな問題です。アメリカを見てわかる通り、単に不公平という話ではなく、社会の分断に繋がるからです。実はこれが一番怖いことです。社会の分断を避けるためには再分配が必要なのですが不十分です。格差の話はするにしても不公平だ、かわいそうだという道徳的な観点に留まりません。格差の是正は、実は社会を維持するためであり、究極の安全保障なのです。歴史を見ても国が滅びるときは内部から崩壊しています。それは格差によってです。革命はそうして起きてきました。
自民党総裁選の議論でも、自分たちの足腰をどう強くしていくかが乏しく、表面的な議論が多い気がします。政治資金であれ、安全保障であれ、非常に表面的なところに議論が偏っている印象でした。
確かに、政治への信頼がないと何もできないし、信頼を回復しなければならないのは当然です。ただ、信頼と一言でいっても、二つの信頼があると思います。一つは表面的な信頼、クリーンな政治です。国民の税金を一円たりとも無駄にしてはいけない、自分の懐に入れてはいけない。それは全く当然のことです。ただ、それだけやっているだけでは不十分なのです。
もう一つの信頼というのは、国家の運営能力だと思います。それは高い経済成長を実現することであり、格差のない社会をつくることであり、社会の分断を避けて国家としての一体性を確保することだと思います。国家の運営能力、マネジメント能力が高ければ、国民が政治を信用します。民間企業でも、社長がクリーンでも無能では困るわけです。最後に問われるのは国家の経営、運営能力、管理能力、これこそが政治に対する信頼を持続させる要因だと思います。
誰も正面から財政の話をしようとは思わないかもしれませんが、例えば国家の安全保障を考えるのであれば、あるいは人口減少問題を考えるのであれば、国力がなければ何もできないわけです。経済や財政の問題から目をそらせないはずです。この点ではジャーナリズムの問いかけも必要だと思います。
◇ワイズスペンディング、付加価値を生み出す支出
本当にやるべきことは、生産性の向上です。反対方向なのが、需要を盛り上げることによって経済を活性化し、ひいては雇用を増やして生産力を上げるというケインジアンの考え方です。日本人は皆、この20年間のデフレの中でそういう考え方になってしまいました。需要を盛り上げるのが財政政策の役割だと考えているようですが、アメリカを見ると分かるように、どうやって生産性を上げるかが重要なのです。
企業の生産性を上げ、イノベーションを起こし、新しい雇用を生み出せるかどうか。「需要を増やして雇用を」ではなく、「新しい産業を興して雇用を」という考え方が必要です。新しい産業はIT かもしれないし医療系かも知れない。より生産性の高い産業を育て、労働者の所得を上げていくプロセスが必要なのです。ところが、日本の政府支出はどうしても今存在している企業への補助金になってしまうので、これでは生産性は上がりません。したがって経済成長は持続しないのです。
財政において「ワイズスペンディング」という考え方があります。財政支出の中味を精査して、より付加価値を生み出す支出に重点化していくことです。これまで日本ではあまりありませんでした。例えば新しい産業を興す新陳代謝を促すスタートアップを支援することです。熊本でTSMCの工場ができて熊本の雇用が増えたという局所的な話ではなく、その半導体が産業の裾野を広げて経済全体の生産性を高めるというところまで行って初めて、ワイズスペンディングにかなうことになるのです。
政府で行われている効果検証、政策評価を見ても、 例えば研究開発費などは、企業の投資が増えたかどうかだし、企業誘致にしても、地元でどれくらい消費が伸びたかという、いずれも需要サイドでしか見ていません。重要なことは研究開発投資や半導体投資の結果、どんなイノベーションが生まれたなのです。どんな製品が生まれ、どんな産業が生まれ、どういう形でサプライチェーンが広がったか、それが生産性として測れるのです。
◇段階的な増税の工程表を作る
どうしても税収が足りない、どうしても増税が必要という場合には、どうしたらいいのか。例えば消費税の税率を上げなければならないという際には、政府は国民に対して工程表を公表した方がいいと思います。もちろん、いきなり上げるのは良くないのです。段階的に上げる方が、経済に対するインパクトは抑えられます。経済が成長して法人税や所得税、他の税収が増えれば、例えば社会保障などへ回す余裕が出てくれば、その分だけ、消費税の税率を抑えられますし、最終的な税率を下げることができるわけです。
似た事例が実際にありました。厚生年金の保険料は、2004年の制度改革で約14%から徐々に引き上げ、2017年に約18%で打ち止めにしたわけです。これに帳尻を合わせるためにやったのがマクロ経済スライドです。そうしないと収入が頭打ちになってしまうので。18%に向けて段階的に上げることは保険料の世界でやったことがあります。 では消費税でやったらどうかということです。
それは税収増の場合に還元しやすくする。見える化させるわけです。経済成長した場合、歳出を健全化して抑えた場合、赤字も減るので消費税率の上げ幅も少なくなります。逆に大盤振る舞いしてしまうと、それだけ最終的な消費税率が高くなるわけです。 政治家が無責任に歳出拡大したことのツケの払い方も明確になります。政治的には一番嫌な所だと思うのですが、財政赤字の結果について見える化させることは必要です。
第1回でも述べましたが、この国は財政ルールがないので、国民自身は財政赤字の帳尻を誰がどう合わせるかを知らないのです。それで、自分にとって一番都合のいいように勝手に考えてしまうのです。「公共事業を削ればいい」「国家公務員の給料減らせばいい」みたいな感じです。しかし、どうしても消費税で帳尻を合わせるしかないという姿が見えれば、そのためには経済成長をどうするとか、社会保障給付のどこを減らすかなどの議論をしなければならなくなるのです。政治家も猫の首に誰が鈴をつけるのか、それができる政治家がいるかどうかです。
◇政治家の真価は歴史的な評価で
例えば、1990年代にドイツ社民党政権のシュレーダー首相が労働市場の改革(失業保障から就労促進への転換、企業規制緩和など包括的な改革)をやったことです。当時ドイツは東ドイツを併合したばかりで不良債権を抱え込み「欧州の病人」と言われていました。改革は評判が悪かったのですが、成し遂げたわけです。今年、日本はGDPでドイツに抜かれましたが、強いドイツ経済の基盤を作ったのはシュレーダーでした。その結果が次のメルケル首相のときに花開いたわけです。彼女の政権が長く続いた若干の要因は、シュレーダーで、彼が一番嫌なことやってくれたからだと思います。そのように、評判が悪くとも、歴史的には正しいと言われる政策はあるのです。
今フランスのマクロン大統領は年金改革をやろうとしていて、大変評判が悪いのですが、そこは偉いと思います。レジームを変える所では悪者になるとこともあるということです。吉田茂もそうだったと思います。当時の支持率はひどいものだったのではと思います。民主主義である以上、政治家は、今の国民の支持が必要なのは分りますが、それ以上に意識するべきは未来からの評価ではないでしょうか
◇野党の立ち位置について
野党はもう少し政策論ができるようになってほしい。スキャンダルを暴いて、政治資金問題の追及ばかりでは駄目です。自民党とは違う日本社会の未来像を見せる議論がなければいけない。
かつて社会党が野党第1党の時代には、非非武装中立などを唱える社会党と自民党とのスタンスの差は明白でした。どういう未来像を求めるかということについて国民が選択できたと言ってもいい。その結果として自民党を選んだわけです。今の時代は、野党は経済政策でどういう違いを見せられるだと思います。
そうは言っても、選択肢は限られていると思います。国力を高めるには、国家の安全保障は、などについて、やるべきことは大体決まっていて、与野党で差別化することは意外に難しくなっていると思います。
であれば、むしろ段階的な消費増税を決めた「社会保障と税の一体改革」(2012年、野田佳彦政権時、民主・自民・公明の3党で合意)のように、大事な政策、安全保障とか、経済成長、財政健全化に関する問題、大事であっても国民にとって耳ざわりの良くない課題については、やはり与野党で合意して、それは政治の争点にはしないという形で進めるやり方が大事だと思います。
もちろんその進め方、テンポが違っていてもよく、与野党で議論があってしかるべきです。しかし、方向感だけは合わせておく。もちろんそれに乗らない政党はありえますが。
安全保障にしても財政にしても、根本的なところで合意できたら、政権交代も容易になると思います。海外の事例ではスウェーデンが年金改革を実施したときも、オランダが医療制度と労働市場改革を実施したときも与野党で合意したわけです。政権がコロコロ変わる国でしたから、政権交代で大混乱しないようにという狙いもありました。
日本の場合は、例えば、増税の税率であるとか、給付の水準とか、このあたり議論は当然あってもいい。一方で、給付と保険料のリンク、税金のルール、労働市場の規制を緩和し流動化を進める代わりに保険給付、失業者給付は徹底的にやるなどの改革を進めて欲しい。こうしたことを大体固めておくのです。日本の場合はこれをやらないと政権交代ができないと思っています。社会党の時代と違って今の野党は与党との政策距離が圧倒的に近くなっていますから、不可能ではありません。
◇「生活者目線」と「国民目線」
政治家もそうですし、メディアもそうですが、生活者目線の他に、国民目線が必要だと思います。いわゆる主権者としての国民目線です。例えば財政学者やメディアの皆さんでも、消費税は増税が必要になるとか、予算は健全化しなければいけないと言う人が、いざ自分の所の予算が切られたら文句を言うし、物価が上がると困ると言います。それは生活者目線で、生活者として文句があるのは別に全然構わない。
ただ、政府の意思決定が生活者目線だけでやっていいかは、違います。政府のあり方としては、これからの財政をどう持続させるのか、社会保障をどう維持するのかという国民目線が必要です。もちろん国民目線が過ぎると全体主義的になってしまうので、それは駄目だと思いますが。
幸いにして新聞には政治面、経済面、生活面、社会面などがあるわけで、生活者方目線と国民目線が両方出せるという所がいいと思っています。中で役割分担ができているのです。しかし、新しいメディアの場合、内部での役割分担はなかなか難しい気がしています。
そもそも財政の問題は説明が難しいのです。すぐ「分りました」ということはありません。経済の問題も難しい。私も全部分っているとは言えません。ある意味、みんな迷っていいと思うのです。
一般の国民にとっては、生活も忙しいし、そんなことを考えていたら仕事ができません。そこで政治家がわかりやすい言葉で国民に伝えないといけないのです。議会制民主主義の世界は、国民は政治家に一定の権限を付託しているので、その政治家が実行しなければいけないのです。「これからの社会はこうです、こういう問題がある。我々にはこういう選択肢がある。全体としてみれば社会としてはこっちの方向に進まないといけない」。そういう形で国民に伝えて説得をするのが政治家の役割のはずです。
政治家自身の思考が短期的になってしまっていると思いますが、メディアもネットに現れた声を御用聞きのように伝えていると思考がますます短期的になってしまいます。いろいろな情報を集めて評価し、問題提起して人々にも熟考を促す。長期的な視点で物事を評価する姿勢を政治家にもメディアにも期待したいと思っています。
(取材・構成 冠木雅夫)
佐藤 主光(さとう・もとひろ)
一橋大学教授(財政学、公共経済学)、経済学部長。1969年生まれ。一橋大学経済学部卒業、カナダ・クイーンズ大学経済学部Ph.D.取得。一橋大学准教授などを経て同大教授。政府税制調査会委員・特別委員、内閣府規制改革推進会議委員などを歴任。著書に『地方税改革の経済学』(日本経済新聞出版社)、『公共経済学15講』(新世社)、『日本の財政–危機回避への5つの提言』(中公新書)など。



-1.jpg)