外交裏舞台の人びと
鈴木 美勝(ジャーナリスト)

米軍嘉手納基地
第8回 末次一郎と若泉敬(8)
首相・佐藤栄作の深謀遠慮(下)
◇「核抜き、本土並み、72年返還」
1969年3月になると、「日米京都会議」の先導役を果たした基地研は、米側の核専門家を含む軍事研究者や学者を巻き込んだ同会議の討議を踏まえて、「核抜き、本土並み、72年返還」を骨子とする報告書をまとめ、佐藤栄作首相、愛知揆一外相らにそれぞれ説明した。新聞・テレビなど報道機関を通じて国民にも大々的に発信した。国民世論や学者・研究者を中心とする日米双方の有力者、主な有識者は、沖縄問題に関する日本政府の立場及び認識を共有した。国家の一大プロジェクトとも言うべき沖縄返還問題は、末次の筋書き通りの落し所に収まり、佐藤の11月訪米に向けて大きな流れを作り出した。
と末次一郎(右)(『追想・末次一郎』から)-300x151.jpg)
1969年9月のテレビ座談会「沖縄はどうなる」での愛知揆一外相(中央)と末次一郎(右)(『追想・末次一郎』から)
末次は後に京都会議をめぐる裏話を披露している。「核抜き、本土並み、72年返還」を「ピシッと決めたわけじゃないんですよ。しかし、京都会議で得た感触を基にして……類推するとこの辺までは行けそうじゃないか、というようなことで、われわれの主体的な報告書を書いただけです。その報告書の中に、明確にね、『核抜き、本土並み、72年返還』を謳い込んだ」〔註11〕のが、基地研の報告書だった。
以後、沖縄返還をめぐる外交は、外務省―米国務省を中心とした表舞台での交渉に入る。日米京都会議を機に「沖縄復帰への流れは動き出した」と手応えを感じた末次だが、まだ安心できなかった。「念には念を入れねば」として、69年6月末、再びワシントンへ飛んだ。便宜を図ってくれた下院議員スパーク・松永(後に上院議員)の案内で、モーガン(上院外交委員長)、リバース(同軍事委員長)、ザブロッキー(下院安保小委員長)をはじめ、マンスフィールド(後に駐日大使)ら上院外交委員会の有力議員らと面会、ワシントンポスト紙主幹のブラッドレーらマスコミ関係者とも懇談した。〔註12〕
あるアイデアと行動が正当であると国政レベルで認められるには、それが政策決定者(政治家及び行政担当者)の行動に決定的な影響を与えるための3つの必要条件(無害・有益性、緊要性、実現可能性)がある。沖縄復帰運動に当てはめると、第1の「無害・有益性」に関しては、日本の国家的利益に抵触せず、日米間の友好関係を損なわず、政策の最高決定者――首相・佐藤――が政治的に納得できるものとして提出される必要があった。それを第2の「緊要性」に絡めて言えば、64年の自民党総裁選に出馬した佐藤が――結果は敗北したものの――沖縄問題を政権構想の柱として取り上げた事実に注目する必要がある。末次は、「ミスター沖縄」と言われた「南方同胞援護会」初代専務理事・吉田嗣延〔註13〕とタッグを組み、運動のネットワークを広げるために政治家や学者を固める役割を担った。その働きは、沖縄返還問題を政策決定者レベルに押し上げるのに大きく貢献した。
こんなエピソードが残されている。64年当初、政権を目指す佐藤のブレーン集団は自民党総裁選挙に向け、緊急の政策課題として「中共(中国)」問題を取り上げようとした。が、総裁選が近づいてきたある日、青年運動でのつながりがあった末次を佐藤側近の竹下が訪ねて来て、「沖縄というのは政策の目玉になるか」と聞いた。末次は「目玉になるかならないかというのは甚だ不埒」との思いをこらえつつ、アドバイスした。「(佐藤総裁に)なろうとなるまいと、やるべきだ。これは、必ず国民的な関心が高い問題だから、なかなか難しいけれども、新しい指導者が取り上げるテーマではないだろうか」〔註14〕――と。同じ頃、吉田も、東京帝国大学時代からの友人で佐藤派(後に福田派)の細田吉蔵から同様の相談を持ちかけられていた。
第3の要件の「実行可能性」について言えば、立案の発想が単に興味深いというだけでは政策決定者が本気で取り上げることはない。例えば、国家の対外政策に密接に絡むこの沖縄問題にあっては、その実行可能性の成否は一にかかって米国の出方如何に関わっていた難題。厳しい事情の中で極秘裏に動いたのが、若泉だった。
と大濱信泉(左)-(『追想・末次一郎』から) -300x158.jpg)
日米京都会議での末次一郎(右)と大濱信泉(左)-(『追想・末次一郎』から)
◇回り始めた歯車――起点となった秘密会合
2月中旬のある日、首相・佐藤の最側近、楠田實(総理大臣首席秘書官)に秘密の指示が降りてきた。「外務省の事務当局と会いたい」――官房長官・保利茂からだった。楠田はすぐに外務省と連絡をとって、ホテルニューオータニ(東京・紀尾井町)の一室に会合場所をセットした。
2月18日午後2時、保利と外務省幹部との秘密の打ち合わせ会が始まった。テーマは沖縄問題。出席者は保利以下、木村俊夫(官房副長官)、楠田、小杉照夫(総理秘書官=外務省から出向)、外務省の牛場信彦(事務次官)、東郷文彦(アメリカ局長)、佐藤正二(条約局長)、大河原良雄(アメリカ局参事官)。
保利がまず口を開いた。「今年の後半に予定されている佐藤総理の訪米まで、外務省の方々にはひとかたならぬご苦労をおかけすることになりますが、宜しくお頼み申します。ところで牛場さん、これからのスケジュールはどげんなっとりますか」
これに対して外務省からの説明があった――まず4月後半、東郷アメリカ局長が訪米して、国務省当局と基本的な中身の話に入る。6月初旬、愛知外相がワシントンで米新首脳と会談する。7月頃、日米貿易経済合同委員会を東京で開催する。9、10月頃、愛知外相がニューヨークの国連総会に出席、その際ワシントンに立ち寄り、米国首脳と会談する。
会合では、核心に迫るような結論らしきものは何もなかった。
「そうですか。もうそこまで出来ておりますか、有り難いことです。このうえとも皆で協力し合って、この国家的大事業が立派に完成するよう頑張りましょう」
保利が締めくくり、話はここで終わった。その後、一同はお茶をすすりながら少し雑談して散会した。〔註15〕 楠田は、その場の雰囲気から察して「外務省側は核抜きということは考えていないらしい」と日記に書きつけた。
◇外務省に与えた無言の圧力
保利の指示に基づき会合をセットした当の楠田は、心中、自問した。なぜこのようなタイミングで、仰々しく秘密会合をお膳立てする必要があったのだろうか。この程度の中身なら、毎週月曜日の官房長官への外務事務次官定例ブリーフで用が足りたのではないか。
だが、沖縄問題で保利が前面に出てきたのは、これが初めて。首相・佐藤は、これに先立ち2月に入ると、周辺に自身の意向を漏らしていた。「返還の形式は事前協議を含めて何とか本土並みという形をとりたい。その枠内でどうしても問題が残るという場合には重大な決心をする」〔註16〕――と。
帰りがけ、政治的勘の鋭い牛場はホテルの廊下を歩きながら、ひとり呟いた。「総理も官房長官も核抜きでやろうということですな」。楠田に問いかけているようでもあり、自分自身に言い聞かせているようでもあった。〔註17〕
-300x205.jpg)
末次が始めた「日の丸を送る運動」。喜ぶ沖縄の小学生(『追想・末次一郎』から)
◇機能し始めた佐藤政権・外交ルート
楠田は、この日の会合の意味を思い直した。「政治には言葉を必要としない面もある」。この日の保利の演出が、まさしくそうだった。困難極まる外交交渉が、事前に思い描いたシナリオ通りに運ぶ保証はない。が、沖縄返還交渉が単なる外交交渉にとどまらず、佐藤政権の命運をかける中心的課題になった以上、政官挙げて総力を結集する必要があった。それには、深く関わる者全員が「基本的構図」を共有しておかなければならない。
首相の心のひだに潜む真意までを読み取っている保利のこの日の動き――それは、自らが陣頭指揮に当たることを外務省側に示すことで、外務省も首相官邸と一体となって取り組むように無言の政治的圧力をかけるとともに、併せて沖縄返還交渉に賭ける政治家・佐藤の決意を伝えたものと言えよう。
この会合を機に、佐藤政権の外交ルートが機能し始めた。3月中旬に北米一課長・千葉一夫、4月後半にアメリカ局長・東郷が相次いで訪米。6月初旬にワシントン入りした外相・愛知は、米大統領ニクソンをホワイトハウスに表敬訪問した後、沖縄返還交渉の第1ラウンドとなる国務長官ウィリアム・ロジャースとの日米外相会談に臨んだ。
一方、裏舞台外交のもう一人の“主役”・若泉敬も表舞台の外交の動きを追いかけるように、下準備を始めていた。6月18日午後、事務所がグランドホテル413号室にある楠田と会い、3日後の土曜日、鎌倉の佐藤別邸で首相と懇談する日程を取り付けた。 (つづく)
<註>
〔11〕92年4月14日、琉球放送・具志堅勝也インタビュー
〔12〕末次一郎『「戦後」への挑戦』
〔13〕1910生まれ、沖縄県首里出身。東京帝国大学卒、沖縄県庁に勤務、陸軍服役中に終戦。復員後に同県東京事務所長、GHQ指令で沖縄県廃止に伴い外務省沖縄班長として沖縄県民の戦後処理。53年暮れ、末次が「日の丸」の大国旗を沖縄の小中高校に送る運動で輸送手段に困っていた時、全面的に支援、以来盟友となった。56年、政府に代わって沖縄対策を推進するために設置された南方同胞援護会の初代専務理事に就任。イデオロギー的対立や政治的・経済的思惑が交錯し、多様な組織・グループが共存する沖縄復帰運動の中にあって、「超党派性」を重視、可能な限り広範な勢力を結集しようと、末次と共に尽力した。
〔14〕具志堅前掲インタビュー
〔15〕楠田實編著『佐藤政権・二七九七日』(上)
〔16〕東郷文彦『日米外交三十年』
〔17〕楠田前掲書
<参考文献>『佐藤榮作日記』、『楠田實日記』、『佐藤政権・二七九七日』、末次一郎『「戦後」への挑戦』、同『温故創新 戦後に挑戦―心に残る人びと』、日本国際政治学会編『国際政治』52号(「沖縄返還交渉の政治過程」・渡辺昭夫「沖縄返還をめぐる政治過程―民間集団の役割を中心として」)
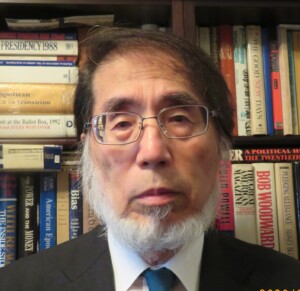
鈴木 美勝(すずき・よしかつ)
ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(以上、ちくま新書・電子書籍)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。



-500x500.jpg)


-500x457.jpg)



