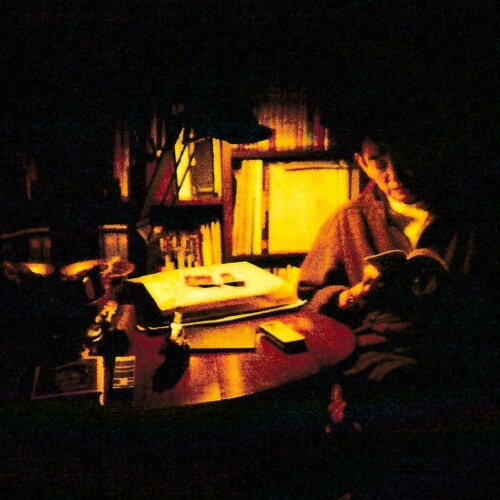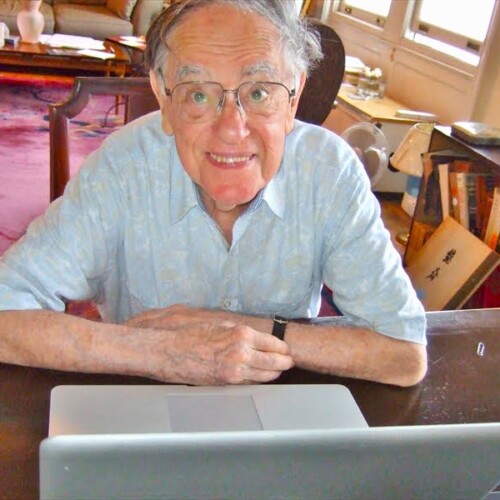米国におけるファクトチェックと
多様性、ウォークの死 <2>
五野井 郁夫(高千穂大学教授)

トランプ大統領再選──MAGA運動
保守系活動家らの政治的圧力、文化的潮流への同調
◇なぜメタ社は倫理観を転換したのか
ファクトチェック以外にも第二次トランプ政権の誕生とともにアメリカで死んだものがある。それは多様性だ。メタは、「多様性・公平性・包括性(DEI)」についても雇用やトレーニングにおいて「サプライヤーの多様性への取り組みを終了する」と社内メモで述べていた。これはメタのビジネスにおけるこれまでの倫理観の転換である。人事担当副社長ジャネル・ゲイルのメモでは「米国における多様性、公平性、包括性の取り組みにかんして取り巻く法的・政策的状況が変わりつつある」ため、方針を変更するというのだ。
ようするにトランプとMAGA(Make America Grate Again)運動による保守系活動家らの政治的圧力のみならず、広く文化的なトレンドに同調しようとする流れの一環である。
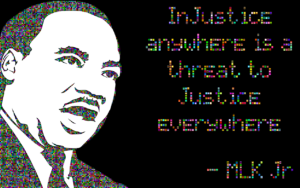
こうしたトレンドを前にして態度を変えたのはザッカーバーグとメタだけではない。トランプが再当選の前後で、マクドナルドやウォルマート、ボーイング、ハレーダヴィッドソン、フォード・モーター、そしてアマゾンなども「多様性・公平性・包括性」の取り組みを中止するとしている。日本でもトヨタ自動車や日産自動車が同様の方針を出している。たとえばマクドナルドは2025年までに世界で管理職に占める女性比率を45%に、人種的・性的少数者比率を30%に引き上げるとしてきた数値目標を取りやめるという。
こうした多様性やアファーマティヴアクション(註1)、ポリティカルコレクトネス「疲れ」は1970年代以降のアイデンティティ・ポリティクスや多文化主義、脱植民地主義の隆盛に対する90年代以降のバックラッシュと同様の側面が認められるが、マジョリティがそれらに「疲れ」て「飽きた」としても、マイノリティを取り巻く不利な状況が改善されるわけではない。
◇テック分野で規制緩和を求める「リバタリアン」の狙いは……
だが、このようなポジティヴな規制と他の社会における規制をアナロジー的に捉えて、テック分野等における規制緩和を求める勢力がいる。それが前回触れたマノスフィア(Manosphere=男の世界、男性界隈、男性文化圏)の一部を構成する「暗黒啓蒙」や「新反動主義者」と呼ばれる人々だ。かれらは政治的イデオロギーは極右や右派の部類に入るが、経済的には規制緩和や撤廃、減税を求めており、きわめてリバタリアン(自由至上主義)的である。

イーロン・マスクに影響を与え続けているピーター・ティールのように、リバタリアンを自認している企業経営者も数多くおり、かれらは人権をはじめとする近代的価値観が技術革新を遅滞させているとして、それら価値観を取っ払うべきだと主張する。これらの人々は「加速主義者」とも呼ばれる。かれらは多くの場合、政治的にはヘーゲルやシュペングラー以来の古典的な西欧中心主義者であるか、素朴なミソジニスト(女性嫌悪・蔑視者)、あるいはその両方である。かれらは政治における表現の自由そのものよりも、政治的自由と経済的自由をリエゾンさせることで、そのじつは自身の企業利益増進のために規制緩和や規制撤廃を求める新自由主義者たちである。
イーロン・マスクやザッカバーグが、地球上でもっとも人権上の規制の強い欧州連合とその規制基準、つまりヘイトスピーチ等の表現の自由に罰則を科し労働者の権利を守る労働法規も厳格な欧州連合(EU)の規制基準に対して、遅かれ早かれ注文を付けることだろう。というのも、いわゆるEUの「規制帝国」としての側面に注目して国際規範形成力を「ブリュッセル効果」と呼ぶが、このブリュッセル効果はEU発の国際基準を制定する力であるとともに強烈な非関税障壁という側面もあるからだ。このような非経済的関心事に基づく制限措置という規制帝国の基準は環境と人権、そしてテクノロジー分野が主な戦場なのである。
◇EUの規制に「適合」しない巨大テック企業
EUが2024年に発効したテクノロジー分野の基準には、欧州で事業を運営する巨大テック企業の活動を制御下に置くことを目途としたデジタルサービス法(DSA)とデジタル市場法(DMA)があるが、これらこそがザッカーバーグらにとって目の上のたんこぶなのである。EUのDSAは、オンラインプラットフォームに規制をかけオンライン上の不正なコンテンツや製品の削減・制限が目的であり、これらは今回トランプ政権下で撤廃されつつあるジェンダー平等やDEIに適合的な必要がある。

またDMAは「ゲートキーパー」に指定された事業者に、オンラインサービスプロバイダーによる消費者へのリーチの際、公正な競争が行われるよう規則を課すものだ。じつはメタは2024年11月14日にこのDMA違反で市場濫用行為を理由に欧州委員会から7億9772万ユーロ(約1300億円)もの制裁金を科されている。
メタが23年11月からヨーロッパで採用を開始した「pay or consent」という、個人データを利用するターゲティング広告を削除希望の場合は有料プランへの加入を必須とし、加入しない場合は当該ターゲティング広告への個人データの利用を同意する必要があるとした二者択一を消費者に迫る広告モデルは、EUのDMA違反であるとしたのだ。ザッカーバーグはこれらのEUの非経済的関心事に基づく制限措置たるDMAなどの事実上の非関税障壁を撤廃するようトランプに求めている。

◇マスクが極右政党、大衆迎合政党を「絶賛」する事情
このような規制を受けるのはマスクのXも同様である。欧州委員会は25年1月17日にマスクが所有するX(旧ツイッター)に対しDSAに基づく監視を強化すると発表したばかりだ。DSA違反が確認されれば、最終的にはXの年間売上高の最大6%相当の制裁金を科すことができるのである。
マスクがドイツの極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」やイギリスの「リフォームUK」の党首ナイジェル・ファラージ(註2)を絶賛しだしたのは、こうした事情によるところが大きい。極右を褒めそやすことでかれらが狙っているのは、政治的な「表現の自由」にリエゾンさせた「経済的自由」、つまりEUにおける規制緩和や撤廃である。トランプが再当選した際、ファラージはリベラル的な価値観を他者に過剰に押しつける人々のことを指す(註3)「ウォーク(woke)は完全に死んだ」 と述べたが、事態はそんな単純な話ではないのだ。
フェイスブックのポリシー変更によって「移民や外国人を排斥する自由」や「マイノリティへの攻撃」が可能になるとして倫理的転換を喜ぶ者たちは、それらを可能にした、政治的には「新反動主義」「加速主義者」でも経済的には「新自由主義者」であるアメリカのマグニフィセント・セブン企業(註4)と経営者たちが、これから欧州その他で規制も著しく緩和させアメリカのテック企業にとって有利な市場環境をつくり、自国民同士を争わせ倫理観を荒廃させ、労働者を脆弱にすること、そして自国の産業競争力を──2000年代の日本における小泉純一郎・竹中平蔵による新自由主義政策が日本の国富を流出させ結果的に日本を貧しくさせたように──台なしにしてしまうことに気付かない。

◇日々の暮らしが破壊されることに気付かない支持者たち
だがこの同床異夢は今後もしばらくは続くことだろう(各国の経済のおける規制というものは公正な競争と国内市場の健全性を担保するために本来は存在しており、これは国家主権の枢要な機能であることは言うまでもない)。
おそらく経済的自由主義者の唱える自由が、政治的自由主義者の各国における自国企業のビジネスを掘り崩しアメリカのテック企業を引き入れる呼び水となり、かれらの日々の暮らしを結果的に破壊するなどと、多くの世界中のトランプ支持者たちは想像だにせず、無邪気にも自分の拠って立つ足下の地盤や自分らの仕事のパイを守ってくれる非関税障壁を掘り崩す下地作りに嬉々雀躍として加担し続けているのだ。(敬称略)
<註>
1)アファーマティヴアクション(積極的差別・格差是正措置)は大学入試選考や女性の優先採用・昇進、外国人の雇用促進など人種や国籍、ジェンダーなどの多様性促進や公平な機会均等の実現を目指すもので、1965年のリンドン・ジョンソン大統領命令 11246 に始まるとされる。
2)イギリス野党・リフォームUKは、「大衆迎合政治家」ナイジェル・ファラージが率いる右派ポピュリスト政党。英調査会社ユーガブが2月3日公表した世論調査ではリフォームUKの支持率がスターマー首相率いる与党・労働党を上回り、初めて首位に立つなど躍進している。
3)ウォーク(woke)はウェーク(wake=目覚める)の過去分詞形「目覚めた」の意味で、社会問題などに対して「意識の高い」リベラル層を揶揄するスラング。
4)マグニフィセント・セブンとは、米株式市場を牽引するアルファベット(Google)、アマゾン(Amazon)、アップル(Apple)、メタ・プラットフォームズ(Meta)、マイクロソフト(Microsoft)、エヌビディア(Nvidia)、テスラ(Tesla)の巨大テック企業7社を指す。黒澤明監督の名作『七人の侍』(1954年)をリメイクした西部劇『The Magnificent Seven』(邦題『荒野の七人』・1960年、ジョン・スタージェス監督)にちなんで付けられたという。

五野井 郁夫(ごのい・いくお) 高千穂大学経営学部教授
1979年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程修了。博士(学術)。専門は政治学、国際関係論、平和研究。日本学術振興会特別研究員PD、立教大学法学部助教などを経て現職。「2013ユーキャン新語・流行語大賞」にランクインした「ヘイトスピーチ」で顕彰。主著に『「デモ」とは何か──変貌する直接民主主義』(NHK出版)、『国際政治哲学』(ナカニシヤ出版、共著)、『山上徹也と日本の失われた30年』(集英社インターナショナル、共著)。翻訳にウィリアム・E. コノリー『プルーラリズム』、イェンス・バーテルソン『国家論のクリティーク』(いずれも岩波書店)。