外交裏舞台の人びと
鈴木 美勝(ジャーナリスト)

沖縄米軍基地ではためく日章旗と星条旗
第6回 末次一郎と若泉敬(6)
稀代のオーガナイザー・末次──沖縄返還問題の軌跡(下)
◇訪米と先見の明
60年安保闘争の翌1961年3月19日、駐日米国特命全権大使として着任した東洋史学者エドウィン・ライシャワーは、当初から沖縄問題に強い関心を払っていた。日米関係を根本から揺り動かす深刻な潜在的リスクだったからだ。沖縄を取り巻く情勢には、南北に分断された朝鮮半島、共産主義国家の中国情勢に加えて、激化するベトナム戦争という三大不安要因があった。米国にとって戦略的重要性が日々増す情況下で、ライシャワーは、早くから沖縄返還をも視野に対日交渉を進めるべきだと考えていた。
「沖縄の怒りを収めなければ、70年を見据えた日米安保条約の期限延長すら危うい」──ライシャワーは、核兵器の配備を含めて在冲米軍基地を使用できることを条件に施政権の返還を検討すべきだ、と本国に積極的に働きかけた。これを受けて、ケネディ政権のホワイトハウスも一定の理解を示した。

国道58号線越しの沖縄米軍用地
一方、日本では65年8月、佐藤栄作が現職首相として訪冲し、「沖縄の祖国復帰なくして、戦後は終らない」との名セリフを残した。末次は佐藤の訪冲を、沖縄復帰への道のりとして「画期的なこと」と評価した。国民に対して沖縄の「潜在主権」を顕在化させ、本土復帰の可能性を印象づけた意義は大きく、その後の復帰運動を大きく盛り上げたためだ。〔註14〕しかし、慎重居士で知られる佐藤の態度は終始煮え切らなかった。
こうした流れの中で、末次は、南方同胞援護会〔註15〕の吉田嗣延(事務局長)と協議し、訪米使節団の派遣を計画した。66年4月、末次と吉田に、国際法に詳しい元外交官の田村幸策(中央大学教授)を加えた3人は米国を訪問、ワシントンを中心に約3週間にわたって滞在した。米政府、議会、アジア・日本の専門家・学者、ジャーナリストなど約200人に会って、沖縄問題に関して意見交換したが、末次らは想定外の冷ややかな反応に直面し、驚きをかくせなかった。
末次によると、第一は特に政府側の態度が予想以上に固く、沖縄の本土復帰について検討している気配は微塵もなかった、第二に在米大使館の「沖縄認識がおどろくほど低いということ」、第三に議会筋の感触がかなり大きく割れており、軍事委員会関係筋の場合などは軍関係者同様、「沖縄では米軍兵士戦死している」として高飛車な態度に出る者もいた。
総括すれば、「アメリカの沖縄への執着はすべて沖縄基地の自由な利用にあること」、そのためには「施政権を握っておかなければならない」というものだった。〔註16〕
現に、沖縄問題に関して前向きな声明(1962年)を発出したジョン・F・ケネディの後継となったジョンソン(大統領)の下では、軍が日本側の対応に反発した。そして、一段と激化するベトナム戦争の展開に歩調を合わせるように、沖縄返還問題は事実上棚上げになっていたのだ。

米ホワイトハウス
◇「問題は米側ではなく日本側にあり」
米側の生の声に触れた訪米の結果を踏まえて末次は、一計を案じた。
米側を説得するには「抽象的感情論では何の効果もなく、具体的、建設的な青写真を示さねばならぬ」「沖縄の祖国復帰のカギは当面ワシントンにあるのではなく、むしろ東京と那覇にある」「ワシントンを説得するための青写真づくりが、何よりも優先する課題だ」。〔註17〕
末次は、復帰への手順や問題点などを整理した「青写真」づくりに着手した。
その後、那覇での動きは「祖国復帰研究会」として、東京での動きは「沖縄基地問題研究会」としてまとめ、世論を盛り上げた。こうした中、沖縄問題を担当する総務長官・森清が、恒例となっている沖縄訪問の際、記者会見で、基地とは無関係の施政権の一部、教育権の分離返還を米政府に訴えた。森発言の問題提起は、これまでも何度か言われてきた構想で新味があったわけではないのだが、世論の盛り上がりもあって大きな反響を呼び、米側にも一石を投じた。ところが、首相・佐藤は例によって黙して何も語らなかった。
森の方も、佐藤から沙汰なしだったことから、教育権の分離返還構想に関する論点整理や諸課題の解決を練るための準備を指示した。そして、総務長官の私的諮問機関として「沖縄問題懇談会」が創設された。常々、佐藤の煮え切らない態度に不満と苛立ちのあった末次らは、首相官邸に対して“圧力”を加える構えをつくってみせたのだった。メンバーは、沖縄返還問題の象徴として担ぎ上げた沖縄出身の大浜信泉(早稲田大学総長)を中心に、末次と吉田が推進役となって前年に発足させた「沖縄を語る会」の中から、各界の有力者が選ばれた。
一方、佐藤はと言えば、翌67年1月になってようやく、「沖縄返還はあくまで施政権の全面返還が狙い」と言明、森発言を全面的に否定した。
◇再訪米とライシャワーの協力
こうした一連の動きを背景に、末次は改めて訪米を計画する。67年3月下旬から4月にかけて、大浜と共に再び米国を訪問した。前年の訪米に続き、その後の情勢を踏まえて対米工作するのが目的だった。出発に先立って、佐藤と会談した大浜は席上、訪米の概要説明と併せて「沖縄問題等懇談会」を首相の諮問機関に格上げするよう要請した。
末次にとって前年に続く訪米となった今回は、手応えのある訪米となった。政府では、ホワイトハウスのW・W・ロストウ(大統領特別補佐官)、国務省のユージン・ロストウ(次官)、議会では、上院議員マイク・マンスフィールド(後の駐日米大使)や民主、共和両党の院内総務などの実力者、幹部たち、さらに政府の政策決定に深く関与している学者や専門家等々とも懇談を重ねた。面会したその数、100人は下らなかった。そして、この時の訪米での大きな成果は、ボストン郊外のライシャワー(前駐日米国大使、ハーバード大学教授)邸での懇談のやり取りの中から生まれた。席上、末次は、旅の途上で思いついた案として「日米学者による接触構想」について、考えを聞いた。すると、駐日大使を辞任し帰国して間もないライシャワーは即座に賛同した――「良いところに気がついた」。そればかりか、近く訪日する機会に、米側の候補者名簿を持参するとまで言ってくれた。
-300x275.jpg)
JICA沖縄国際センターに立つ末次一郎の胸像(鰐渕信一氏所蔵)
これが、2年後に京都で開催する「日米京都会議」の起点となった。
ふり返ってみれば、日本再建の意思を持って上京してからの末次は、「日本健青会」を立ち上げ、沖縄返還問題に関わる布石として「沖縄健青会」を結成、そして「沖縄を語る会」「沖縄基地問題研究会」「沖縄問題等懇談会」等々――脱イデオロギーの視点から果敢に沖縄返還への道を裏方として切り開いてきた。そのオーガナイザーとしての手腕は最終盤の結節点としての「日米京都会議」に至るまで、いかんなく発揮された。そして、地域的な運動が国民レベルにまで高められたその根底には、草の根の心を知る在野の人として戦前戦後の修羅場を生き抜いた、末次のケタ外れの包容力と胆力が起動していたのだ。それは、沖縄の祖国復帰運動に深く関わった稀代のオーガナイザーの半生の軌跡とも言えた。
知的好奇心に溢れ、持ち前の包容力よって、一心岩をも通す胆力で沖縄返還実現に貢献した末次の活動。それは、米側の対日関係エリートを招き入れて開かれた69年の日米京都会議につながるのだが、同会議では、裏舞台外交の中心にいた末次の狙い通り、「核抜き、本土並み、1972年返還」を盛り込んだ報告書にまとめあげられる。その成果は、アメリカの動向をも仔細に見渡し、現実的な着地点に落とし込んだ末次の戦略眼に依拠するところが大きかった。初の訪冲後も慎重姿勢に終始していた佐藤が重い腰を上げる切っ掛けとなったのも、この日米京都会議であった。これについては、ヘンリー・キッシンジャー(大統領補佐官)と秘密交渉をする若泉の裏舞台外交と併せて、次回に詳述する。
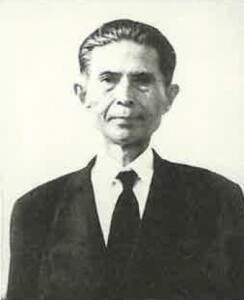
若泉敬
◇結び──対照的な二人の連携
2回にわたった末次らの訪米の際には、若泉がその豊富な対米人脈を辿って紹介した要人が数多くあった。戦後、東京大学に進んだ若泉は在学中から、東大生や早大生ら(後にOBも含む)個々の会員の緩やかな結合を軸に研究会を重ねる言わば知的運動体「土曜会」に所属し、勉学・研究に励んだ国際政治学者だ。対する末次は、陸軍中野学校でのインテリジェンス教育を最後に戦後を迎えた経歴、そして問題を解決するアプローチの仕方などで対極に位置する社会運動家。若泉が理想の灯を片手に鋭く切り込むカミソリなら、末次は大局を見て振り下ろす大鉈。そのような2人が、1967年を節目に沖縄の祖国復帰という戦略目標に向けて連携した。互いの強みを生かし、高め合いながら沖縄返還の実現に独自のアプローチを取って貢献した。沖縄返還問題の裏舞台外交で動いたプレーヤー二人は、米側の変化を外務省よりも的確に把握し、その実現に向けて今何をすべきかを知っていた。
<註>
〔14〕末次一郎『「戦後」への挑戦』
〔15〕1956年、政府に代わって沖縄対策を進める機関として設立された。初代事務局長に沖縄出身の吉田嗣延が就任、沖縄援護の幅広い事業を行った。
〔16、17〕末次前掲書
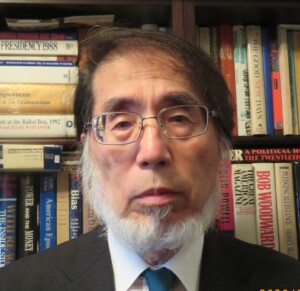
鈴木 美勝(すずき・よしかつ)
ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(以上、ちくま新書・電子書籍)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。
-800x550.jpg)









