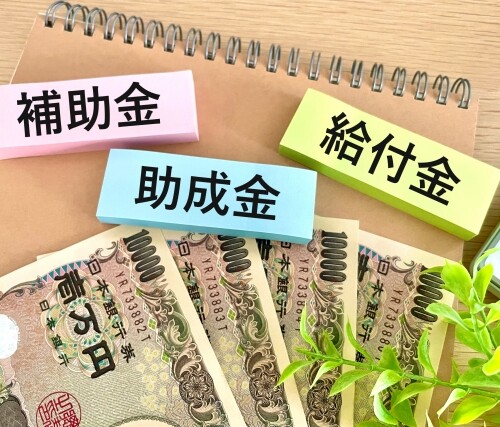歯止めなき財政規律の緩み──
財政法に込められた先人の思慮はどこへ
山本 謙三 (オフィス金融経済イニシアティブ代表)
や議員会館など永田町の風景.jpg)
政権与党が財政規律を甘くすれば、選挙公約は与野党ともに支出拡大のオンパレードに。写真は国会と内閣府など
「例外扱い」が常態化した赤字国債発行
◇なし崩し的に進んだ財政法の形骸化
財政規律の緩みが止まらない。2024年夏に示された政府試算では、「財政健全化目標の『基礎的財政収支の黒字化』が来年度に達成の見込み」とされた。しかし、25年度の当初予算案では、あっけなく覆された。24年秋の大型補正予算で、翌年度以降の支出増も決まったからだ。
国の予算や財政の基本を定める財政法(1947年施行)は、いまも規律ある財政運営を求めている。だが、本来同法が認めていない赤字国債の発行残高は、いまや約774兆円(2024年3月)に達した。実に建設国債の2.6倍(同)に当たる。さりとて、国会が財政法の見直しを正面から議論してきたわけではなく、なし崩し的に法の形骸化が進んできた。財政規律だけでなく、この国の民主主義のあり方が問われている。

財務省
◇戦争危険とインフレの防止
財政法のコンメンタール(平井平治〔当時、大蔵省主計局法規課長〕著『財政法逐条解説 3版』一洋社・1949年)は、法や各条文の趣旨として、①国民生活の安定、②戦争危険の防止、③インフレ防止をあげる。背景には、戦前、国債の発行をテコに軍事費が膨張したこと、また、日銀が国債をいったん全額引き受ける仕組みのもとで、戦中、戦後にインフレが高進したことへの反省があると指摘している。
同法第4条は、本文で、支出(歳出)は税収等の収入(歳入)で賄う原則を定めたうえで、ただし公共事業費、出資金、貸付金に限っては、国債(いわゆる建設国債)を発行できるとした。
国債は、返済負担を将来の世代に課すものである。その資金を道路や橋などの社会インフラに使うのであれば、子や孫の世代も恩恵を受ける。したがって、そうした支出であれば、将来世代に負担を課すことも許される。言い換えれば、社会保障費など、その他の支出を賄うための国債は、将来世代に負担を押し付けるだけとなるので認めない――それが同条の意味である。
したがって、どうしても赤字国債を発行しようとする時には、例外的な扱いとして特例公債(いわゆる赤字国債)を発行するための法律を国会で決議しなければならない。現在国債発行の主体となっている赤字国債は、そうした例外扱いが常態化したものである。
◇積極財政だった安倍第2次政権以降、財政健全化への熱意は薄れた
図は国債発行額の推移である。戦後1964年度までは、国債は一切発行されなかった。65年度、税収不足を受けて急遽赤字国債の発行が行われたあと、翌年度からの9年間は建設国債だけが発行された。しかし、75年度に石油危機後の景気後退をきっかけに赤字国債が発行され、その後十数年にわたり、建設・赤字国債の同時発行が続けられた。
-1024x604.png)
この間、政府は三公社の民営化や消費税の導入などによる財政立て直しに取り組み、ようやく91年度に赤字国債からの脱却を実現させた。しかし、バブル崩壊後の景気停滞を受け、94年度に再び赤字国債が発行されるようになってからは、赤字国債を中心に国債発行が増加の一途を辿り、現在に至っている。
たしかに、2000年代以降はリーマンショックや東日本大震災、新型コロナなどの社会経済的なショックが相次いだ。危機時に財政の出動はやむをえない。しかし、危機の最中にあっては、償還財源を問うことなく巨額の支出が決められてきた。こうなると、危機収束後に財源議論を蒸し返すのは難しい。これが危機発生の都度、国債発行が階段状に増えてきた理由である(前掲図)。

この間、時々の政権が何もしなかったわけではない。財政構造改革法の成立(1997年施行、金融危機の発生を受けて翌年施行停止)や郵政民営化、東日本大震災からの復興のための特別税導入、消費税率引き上げ法案の成立などである。しかし、2012年末に成立した安倍晋三第2次政権以降は、積極財政の運営が目立ち、健全化への熱意はそれ以前に比べ薄れた印象がぬぐえない。
1990年代半ば以降、赤字国債の発行が定着したのは、与野党の政権交代と無関係でないだろう。選挙の都度、票を集めやすい財政支出の拡大策が競われるようになり、財政規律は緩み続けてきた。とくに、政権与党が財政規律に甘めの姿勢を示すようになれば、選挙での公約は与野党ともに支出拡大のオンパレードになる。これが最近の政治状況である。
◇規律が緩むと箍も外れる──「防衛費は税収で」の不文律も反故に
先人たちは、財政規律の維持を財政法第4条に書き込んだだけでなく、規律が緩まないよう、いくつもの箍をはめてきた。
例えば補正予算は、同法第29条で「とくに緊要となった経費の支出を行う場合等に限る」としている。「とくに緊要となった経費」とは災害復旧のための経費などを指すだろう。しかし、最近の補正予算の中には「投資立国及び資産立国の実現」(24年度補正予算)など、本来ならば当初予算の段階で審議されるべきではないかとみられる支出も多く含まれ緊要性に疑問符が付く。コロナ後は補正予算の規模の大型化も目立つ。
また、先人たちの知恵で、防衛費だけは税収により賄わなければならないとの不文律が、戦後長く維持されてきた。借金をあてに防衛費が拡大することを避ける趣旨からである。しかし、これも岸田文雄政権下の23年度当初予算で、自衛隊の隊舎整備や艦船建造などの支出に建設国債の発行をあてることが容認された。
あるいは、特例公債法に基づく赤字国債の発行は、あくまで例外的な位置付けとして、当初は毎年度法案を提出し、審議のうえ、決議していた。しかし、これも最近は先行き5年分をまとめて決議するようになった。いったん財政規律が緩むと、先人たちがはめた数々の箍も一つひとつ外されている。

◇財政規律を緩めた日銀の国債買い入れ
こうした財政規律の緩みにさらに輪をかけたのが、日銀による国債の大量買い入れだった。異次元緩和の期間中(2013年4月~24年3月)、日銀の国債保有は約464兆円も増加し、残高は4.7倍に膨れ上がった。増加額は11年間の新規国債発行額の9割に相当し、いわば政府の財政赤字をほぼ丸ごとのみ込んだ形である。
財政法第5条は、「日銀による国債引き受け(いわゆる財政ファイナンス)」を禁止している。異次元緩和の期間中に日銀が行った国債の購入は、あくまで市中からの買い入れであり、法解釈上引き受けには当たらないとされている。しかし、日銀は巨額の買い入れが可能となるよう、国債発行の翌営業日には買い入れを可能とする仕組みを採用しており、経済機能的には財政ファイナスとほとんど変わらない。
日銀自身は、大量買い入れについて、金融政策のために行うものであって、財政ファイナンスとは目的が異なると説明してきた。しかし、財政規律が緩むかどうかは、政府や政治、社会が国債の発行にどれだけ難しさを感じるかで決まる。日銀が行ったように金利ゼロ近傍、かつ期間中の新規国債発行にほぼ匹敵する規模を買い上げれば、日銀が目的をどう説明しようとも、国債の発行に難しさを感じる者はいなかっただろう。日銀の国債買い入れが、財政規律を緩める方向で作用したことは間違いない。

日本銀行
◇民主主義のあり方が問われる
国の借金残高は、2024年3月末時点で約1297兆円に達した。このうち赤字国債の発行残高は6割を占め、建設国債をはるかに凌駕している。
また、日銀の国債買い入れは巨額に達し、国の借金のかなりの部分を日銀が支える構図になっている。中央銀行による財政ファイナンスの禁止は、内外の苦い経験をもとに、人類の共通の知恵として多くの国が採用しているが、異次元緩和はこの基本原則を危うくするものだった。近世の欧州の王室は、放漫財政を自ら貨幣(通貨)を発行して賄った。日銀と国のバランスシートを統合すると、あたかもその姿によく似ている。このような姿を見て、市場や人々はいつまで日銀と国に信頼を寄せ続けてくれるだろうか。
幸い、日本と通貨(日本円)に対する信認は、先人たちが築き上げてくれた信頼のおかげで、これまでのところ維持されている。しかし、信認のありようは心理的な要素が大きく、財政がどこまで悪化すれば閾値を超えるかは明らかでない。
例えば、日本が地政学的リスクに巻き込まれるような事態が起きれば、人々の心理は揺らぐ可能性がある。そうなれば、円相場は急落し、物価は高騰へ向かう。財政法はそうした事態が繰り返されることのないよう、国民にあらかじめ規律ある財政運営を求めたようにもみえる。
なし崩し的な財政法の形骸化は、この国の民主主義のあり方を揺るがす。今国会では、野党の一部から「新たな支出を提案する際には、財源もセットで提示する」との新たな動きがみられた……。しかし、与野党による修正協議は高校授業料の無償化や「年収の壁」の見直しに集中。結局、25年度予算はこれらの施策を取り込みつつ、全体では減額修正され、赤字国債の追加発行も回避された。もっとも、国債の増額回避は予備費削減などによる辻褄合わせの感が強く、財源をめぐる本格的な検討は先送りされた。
悲惨な歴史をふまえ先人たちの思慮を私たちは軽んじてはならない。

山本 謙三(やまもと・けんぞう) オフィス金融経済イニシアティブ代表
1954年生まれ。東大教養学部教養学科卒。76年、日本銀行入行。金融市場局長、米州統括役兼ニューヨーク事務所長、決済機構局長、金融機構局長、理事などを歴任。NTTデータ経営研究所取締役会長、日本公認会計士協会 品質管理審議会委員、三菱UFJフィナンシャル・グループ リスク委員会外部専門家などを経て、現在はブリヂストン、住友生命保険相互会社、ゆうちょ銀行の社外取締役をはじめ、公益財団法人・富山文化財団理事、日本証券業協会 規律委員会委員などを務める。近著に『異次元緩和の罪と罰~私たちはこれからどんなツケを払うのか』(講談社)。